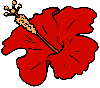 沖縄のこと
沖縄のこと
☆ 文学青年の頃その4 佐里温泉を擁する相知町佐里地区の青年団は 昭和39年9月7日、東京オリンピック開幕を一ヶ月後にひかえて、台風のため
一日遅れた聖火はカラリと晴れあがった沖縄に到着した。この日、まだ夏の
名残を惜しむような南国の太陽がギラギラと照りつける沿道には、朝早くから
聖火を迎えようと押し掛けた人々が聖火搬送隊の到着を今や遅しと待ち受けて
いた。 さすがに、さわやかな風だけは秋の訪れを示すようにそよいでいた。
しかし、人々はそうした機構の変化に振りむこうともしない。沖縄が日本に
復帰してから久しいことになるが、米軍主要基地としての使命を負わされて
きた沖縄は、日本国でありながら今なお政府を異にし、半占領国のような
立場に甘んじてきた。 やがて、そのざわめきを掻き分けるようにして先導車が進んで来た。
トーチを掲げて、その頬に感激と誇りを露わにして、逞しく走る若者の姿を
見たとき、そのランニングシャツの胸に鮮やかに描かれた日の丸を見た時に、
人々の歓呼と拍手は最高に達した。彼らは、この時ばかりは沖縄に生まれた
喜びを感ずることができた。開催国として、最初に「世紀の祭典」と言われる
東京オリンピックの聖火を迎えることができたのであるから…
人々は、長かった今日までの忍従を振り返ってみる。日本という国に属した
かった。「自分は日本人だ!」と叫びたかった。人々はそれらのことが一度に
実現したかのように錯覚し狂喜した。
彼らは、今こそ自分が日本人であり平和が彼らを包んでいることを、その目で
確かめることができた。
|

|
桟を揺すりながら、身を乗り出すようにして何かを叫んで
いる老婆がいることに気づくものはただ一人としていなかった。 気でも狂って軟禁されているのであろうか。伸びきった白髪を振り乱し、檻に しがみついて吠える猿のように猛り狂っている老婆は、目の前を通り過ぎようとする 聖火隊に向かって絶叫しているのだが、その声は人々の歓呼にかき消されて、その 意味を解することはできなかった。 その枯れた手に、それほどの力があろうかと思うほど木桟を揺さぶっているのだが、 やがてその桟は、執拗なまでの力に耐えかねたようにポッキリ折れて、しがみついていた 老婆の痩身を蔵の窓から路面へ放り出した。彼女はいつ替えたか判らぬような、 しかも排泄物をあちこちにくっつけた着物を引きずって、裾を乱して人混みの中に 駆け込んで行くのだ。
「息子が帰って来た。健太だ! 健太が帰ってきた。ケンタぁっ!」彼女はそう
叫んでいる。息子の戦死に気が狂った彼女は、あれから19年、今日の小旗の波に
凱旋してくる息子の影を見たのであろうか。遠ざかっていくランナーを追って、彼女は
やっとたどりついた人混みの中の黒人にしゃぶりついて、なおも叫び続けた。
老婆は、この日のために舗装がなった路面に鈍い音をたてて頭から落ちた。
驚くべき言葉が老婆の口を衝いて出たのはこの時である。 この頃、別編「T子への求婚状」で記した経過を経て、私は今の連れ合いとの結婚を 意識していたので、彼女を誘って一緒に参加した。 今はやりの婚約旅行などというしゃれたものではなかったが、その旅を終えた暑中 見舞い状として、私たちはお互いの親しい人達に、連名で婚約を報告したものだった。 それから更に28年。この四月から、その沖縄に連れ合いが転勤して、私や娘の 往来が多くなったのも、また一つの縁であろう。 |
.
 随筆集・目次へ 戻る
随筆集・目次へ 戻る