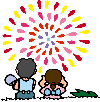 うら盆の頃
うら盆の頃|
我がふるさと相知町佐里地区は、松浦川の流れに沿った山あいの約200世帯 の小さな集落である。昔から、村の中に初盆を迎える家があると、盆の13日まで には初盆供養のお線香代を届ける習わしである。僕の小さい頃は、ばあちゃんに その家の前まで連れられて行き、「仏様にあげて下さい」とか、きちんと口上を 述べてすいかやキャンディをもらうのが楽しみであった。この頃はそれが、 缶ジュースか袋菓子が一般的なようである。
また、当時は青年団がお盆の3日間をかけ、初盆の家の庭先で盆踊り供養
の盆踊りに回るのであった。観衆もちゃんとコースを知って随いていくし、
その家では飲み物やつまみをふるまって、しめやかな中にゆかしい光景であった。
相知の各部落には、それぞれ口伝の盆くどきがあり、口説き手に合わせて
盆踊りは進行する。決まって蛇目傘の下で口説くのは、傘がスピーカーの
役割をするのだと、ずーっと後で知ったことであった。 例えば、佐里の場合「揃うた揃うたよ 踊り子が揃ぅた〜秋の出穂より 色よく揃ぅた」 盆くどきが始まると 三々五々の人の群から踊り手が輪をなしながら踊りを始めてゆく…私は、この 瞬間が好きだった。幼い頃からこの盆踊り風景を見ていた私は、これが普通だと 思っていたが、風習民俗に詳しい先生の話では、東松浦地方に一部残っているだ けで全県的には珍しい風習だとのことである。
盆くどきには数曲(節)あり、昔は女郎哀歌や悲恋物語など
浪曲のように物語を楽しむものとしても伝えられていたようである。
更に佐里では、音楽に堪能な先輩の工夫もあり、民謡や都々逸・戯れ歌のような言葉も
加えられて、都合6曲ほどを織り交ぜて歌い | 
|
継ぎ、踊り継いでいくのである。 また、くどき手がビールを呑みたくなれば ”みんなどなたも どなたも様も えーご調子 ここらでちょいと 一休みしましょ”で、踊りの輪は崩れることとなる。
… この盆踊りも、青年団員の減少その他で、初盆回りは婦人会や公民館行事として、
暫く耐えたが、この頃では小学校校庭での合同慰霊祭と盆踊り大会へと変わり、スピーカーも
レコードも使うものとなっている。しかし、里帰りする人々の楽しみなものには変わりがない。
私は町内に残っているこれらの盆踊りの継承大会や全国でも同様の風習を持つ 市町村との交流大会などを提唱しているが、県内の専門家の先生が私に尋ねるくらいだから、 この種の情報にはまだ手を出しかねている。県内では、同様の「田植え歌」を テーマに国際交流を併せて、既に大きな実績を挙げつつある西松浦郡西有田町がある。 このイベントの難点は、全国各地で持ち回り開催したとしても、いずれも時期が 地元の本番と重なることであるが、各地の風習や方言が入り交じった楽しいものになることは 間違いないのだから、主催者の意気込みと工夫で何とかなるはずだと思っている。 そう言いながら、私自身が頓挫しているが、どこが最初に「全国盆くどき交流大会」を 呼び掛けるかであろう。 |
.
 随筆集 目次 へ 戻る
随筆集 目次 へ 戻る