|
1.窯の種類
|
|
一般的に窯跡という場合には、今日では本焼き用の登り窯を指すことがほとんどである。製品の生産過程では、ほかにも素焼き用の素焼き窯や上絵焼付用の赤絵窯などが用いられるが、これまでのところほとんど実態は明らかになっていない。
素焼き窯は工房の一角に設置された窯で、登り窯の一部屋を取り出したような形状をしている。本焼き前に900℃ほどで素焼きすることにより、取り扱いが容易になるとともに、繊細な描画が可能になる。また、本焼きの際の変形も防止することができる。
赤絵窯も各工房に設置された小さな窯で、本焼き焼成した製品に上絵具で文様を描き、800℃ほどの温度で焼き上げる。構造的には、天井のない筒形の窯で、横に焚口を設けている。窯は二重構造になっており、炎は外窯と内窯の間を抜けて上に上っていくため、内窯に窯詰めされる製品には直接炎は当たらない。
これから説明する登り窯はこれらの窯とは異なり、山の斜面に築かれた大規模なものである。そのため、通常は焼成室ごとに所有者が異なり、共同所有されている。
|

登り窯の窯焚き風景
(職人尽し絵図大皿/有田陶磁美術館蔵)
|
|
2.登り窯の形状と規模
|
|
肥前で用いられた登り窯は、当初から窯の内部を隔壁で小さな部屋に区切っていたことに特徴がある。こうした窯は、日本では肥前ではじまり、次第にほかの地域へと伝わっていった。当初は割竹式と称される竹を半裁したような形状の窯が用いられたが、江戸初期にはすでに連房式と称される団子を連ねたような形状のものが一般的になる。
全長は割竹式で10数〜20数メートル。連房式はかなりばらつきがあるが、有田の場合、江戸初期の小さいものでも30数メートル程度、大きいものでは60数メートルを超える。しかもこの規模は時代とともに大きくなり、江戸後期には150メートルを超えるものまで築かれるようになる。
このように連房式では規模の大きなものが可能な理由の一つは、割竹式に比べ、構造上、地形の変化に対して柔軟に対応できるからである。つまり、窯の占地面積が増えるほど、当然ながら、一定の条件が整った地形は得にくくなる。よって、逆に窯の方を複雑な地形に対応させる必要がある。ところが、上面も側面も直線的な割竹式では、途中に大きな変化がある地形には造れない。しかし、連房式の場合には、団子状の焼成室を連ねるため、上下、左右どちらにも比較的自由に調整が可能なのである。
|
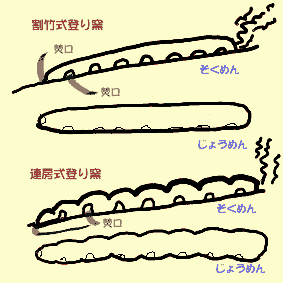
|
|
3.登り窯の内部構造(1)
|
|
登り窯の内部は、隔壁によって小さな部屋に区切られている。各焼成室内部は、前方から薪を焚く火床と製品を詰める砂床に仕切られており、連房式の登り窯では、通常その境に粘土製の火床境が造られている。また、火床の片側の側面には、出入り口を兼ねた焚口が設けられており、そこから薪を火床に投入する。製品を詰める部分を砂床と称すのは、床に並べた窯道具などが熔着しないように全面に砂が敷かれているからである。
各焼成室は、原則として時期とともに規模が拡大する。1630年代以前の窯ではまれに横幅が1m代のものもあるが、通常は2〜3m、奥行きも同程度である。また、17世紀後半〜18世紀前半頃には横幅5m代前後、奥行きは4〜5m代程度、18世紀後半以降は横幅7〜8m代、奥行き5m代前後となる。このように規模の拡大が可能になったのは、17世紀の窯では全体を粘土で塗り固めて構築するが、18世紀以降の窯ではとんばいと称される耐火レンガを積んで造る方法に代るからである。
また、床の傾斜も当初奥壁に向かってやや高くなるものが一般的であったが、次第に水平になり、江戸時代後半には逆に奥壁側に向かって下がるものが一般的である。
|
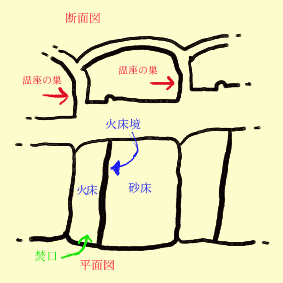
|
|
4.登り窯の内部構造(2)
|
|
登り窯の各焼成室間は、通常は階段状に床が段々に高くなっている。この段差は割竹式では0〜30cm前後と低く、しかも焼成室によるばらつきは比較的少ない。しかし、連房式の場合は地形に応じてばらつきが大きく、一つの窯でも0〜1m以上までさまざまである。
各焼成室の間は、下端、つまり火床の前面に下室と仕切るための隔壁が設けられている。この隔壁には、温座の巣(おんざのす)と称される小孔が横一列に配置されており、焼成の際の炎や熱はこの穴を通って上室へと伝わる。この温座の巣は瀬戸や美濃では狭間(さま)と呼ばれており、横狭間、斜狭間、縦狭間など、時代によって構造が変化するが、肥前の場合は時代を問わず横狭間のみである。
|
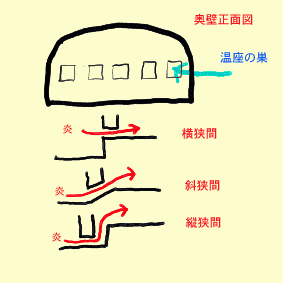
|
|
5.製品の窯詰め
|
|
製品を焼成する際の窯詰めには、いくつかの方法がある。肥前の場合には、基本的に朝鮮半島の李朝時代の窯場と共通しており、製品のレベルによって用いられる方法が異なる。
最も高級な製品は、肥前でボシと称される器状の匣鉢に入れて焼成される。この方法は製品が灰を被らず温度も均一にできるが、その分焼成室の占有面積が大きくなる。
中級品は、トチンやハマと称される焼台に一点ずつ載せて焼成される。高さの違う焼台を使用することにより、空間をいくらか有効に使うことができる。
下級品は、同じ種類の製品を目を挟んで複数直接重ねて焼成される。目は団子状にした粘土(胎土目)や砂(砂目)が最も一般的であるが、ほかに貝殻(貝目)や陶石・砂岩(陶石目)、団子状の粘土塊の下に砂を敷いたもの(砂胎土目)なども、特定の地域や器種によっては使用される。この方法では、一種の窯傷である目跡が残るが、たとえば皿などの場合には10枚程度も重ね焼きが可能なため、焼成室の占有面積は少なくてすむ。
具体的には、ボシやトチン、ハマといった窯道具を焼成室の砂床に配置し、そこに製品を置いて焼成する。その際にそのままでは窯道具に製品が熔着してしまうため、製品と接する面には、やはりあらかじめ砂が敷かれている。
|
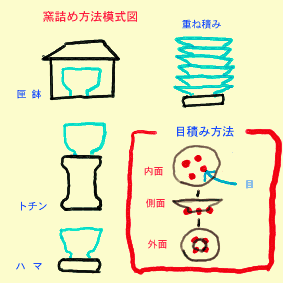
|
|
6.物 原
|
|
登り窯は、山の斜面に築かれる。通常、側面に設けられた各出入り口の先は谷になっており、焼成に失敗した製品はそこに投棄される。したがってこの谷には製品がたくさん散らばっているため、一般的に物原と呼ばれている。
物原は製品が焼成されるたび、あるいは窯が修復されるたびに失敗品や窯壁片が投棄されるため、徐々に埋まって浅くなる。こうして埋まって平らになった面に、また新しい窯が築かれていることも珍しくない。物原層の厚さは窯場によってかなり差があるが、長期間使用された窯場では、10m以上堆積している場合もある。
この物原に堆積している土層は、大別すると3つのパターンに分けられる。すなわち、窯の大規模な修復や造り変えが行われた場合には、窯の床下の地山を削るため、黄色土が大量に混入する。また、小規模な修復や製品焼成後には、窯内を触るため、焼土を大量に含む赤い土層が堆積する。さらに、窯が一定期間使用されなかった場合には、黒色に近い自然堆積層が形成される。こうした土層の堆積状況を見ることにより、窯場が使用された期間の状況を知ることができる。
|
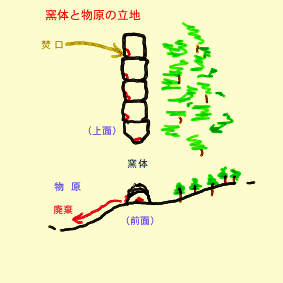
|
|
1.窯跡資料の特徴
|
|
窯跡は、生産、流通、消費という一連の経済システムに当てはめれば、生産遺跡ということになる。また、同様に生産の一連の工程から言えば、成形を行った窯焼き跡や上絵付けを行った赤絵屋跡なども生産遺跡に含まれる。しかし、窯焼きや赤絵屋の工房跡では、生産が行われると同時に、そこで日常的に生活が営まれている。つまり、生産遺跡であるとともに、一面では消費遺跡でもあるのだ。ところが登り窯は、製品の本焼きの際のみに用いられる非日常的な空間なため、消費遺跡としての性格は極めて弱い。
こうした差によって、具体的に発掘調査を行った場合、どのような違いが現れてくるのだろうか?
まず一つは、登り窯で出土する遺物は、ほとんどそこで生産されたものであるが、工房跡等で出土するものには、相当量ほかで生産されたものが含まれる可能性が高いのである。
もう一つは、工房跡等で出土した製品は、場合によっては使用期間を考慮する必要があるが、登り窯の出土製品は、原則として焼成の際に失敗して廃棄されたものなので使用期間が伴わないのだ。
つまり、登り窯跡の出土資料は、遺存状態と発掘調査方法の条件が整えば、そこの窯場で生産した製品をかなり客観的に、しかも綿密に捉えることができるのである。
|

登り窯の発掘風景
(小溝上窯跡/有田町)
|
|
2.年代把握の方法(1)
|
|
もちろん登り窯の調査を行えば、さまざまな情報が入手できる。しかし、これをすべて説明はできないため、ここではひとまず出土する製品の年代(つまり窯の操業年代でもあるのだが)の捉え方について説明してみることにしよう。
窯場から出土する製品を大別すると、物原から出土したもの、焼成室床面に遺存していたもの、その他に分けられる。この中で年代を考える上で特に重要なのは、物原と床面の出土品である。
物原から出土したものは、それが廃棄されたままの状態であれば、原則として下の層に含まれているものほど古い。つまり、焼成と失敗品の物原への廃棄が繰り返されるため、新しいものほど上に堆積することになるからである。したがって、物原の最下層に堆積しているものは、その窯で最初の焼成品か、少なくとも廃棄された製品の中では最も古いことになる。
一方、焼成室の床面に製品が残るという状況は、以後その焼成室が使用されなかったことを意味している。したがって窯体の部分的な廃棄でない限り、その製品はその窯の最後の焼成品ということになる。
つまり、原理から言えば、各物原層から出土したものを下から順番に並べ、最後ないしは物原の最上層と同列に焼成室床面の出土品を位置付ければ、その窯の操業期間の状況を捉えることができるのだ。
|
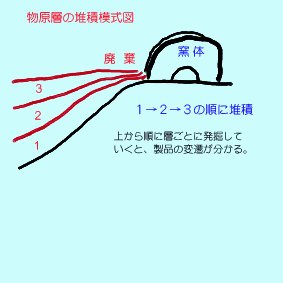
|
|
3.年代把握の方法(2)
|
|
窯跡の調査で、もちろんそこで生産されたすべての製品が出土するわけではない。あくまでも失敗して廃棄されたものの中で、たまたま発掘した場所に残っていたものだけである。では、なぜ、これで出土していない製品の年代まで分かるのだろうか?
それは、一言で言えば世の中が刻々と変化しているからである。つまり、時期ごとに流行もあるし、より時流に適合するために、技術的な進歩や変革が常に繰り返されているからなのだ。
具体的に言えば、まず、同じ土層から出土した製品に用いられているさまざまな技術をはじめ、文様や描法などの多様な要素を抽出する。そしてそれを他の土層の要素と比べると、時期ごとの変化が分かるのだ。
このようにして、各要素の時期的な変化が把握できれば、同じものでなくても要素どうしの比較によって、時代の判別が可能になるのである。
|
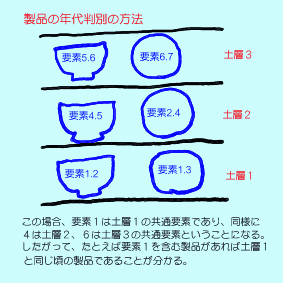
|
|
4.年代把握の方法(3)
|
|
こうした要素の比較検討は、同じ要素を持つ資料が多いほど確実性が増す。また、同じ要素の製品を内包する土層の発掘例が増えるほど、一時期の要素のバリエーションを鮮明に捉えることができる。そのため、次の過程として、個々の窯内の比較だけではなく、他の窯の発掘資料とも比較を行うのである。
各窯は、それぞれ作られている製品に特徴がある。しかし、操業時期に重なりがあれば、やはりどの窯でも部分的には、共通した要素を有している。この共通項を比較することによって、多くの窯の時期的な前後関係を捉えることができるのだ。
また、この操作を繰り返すことによって、より長い期間に渡る製品の変遷を捉えることができるようになる。
|
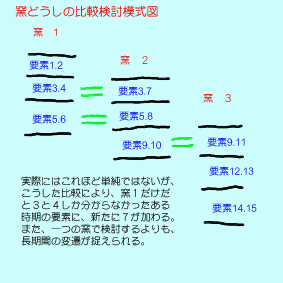
|
|
5.年代把握の方法(4)
|
|
ところが、これだけでは実際の年代は不明のままなのがお分かりだろうか?何が何より古いなどという順番が分かっただけである。こうした年代は前後関係を表すため相対年代と言う。一方、1999年などという実際の年代は、実年代、暦年代などと呼ばれる。通常用いられるのは、この実年代である。こうした実年代を探るには、さまざまな方法が用いられる。というよりも、使えるものは何でも使って、この相対年代の各区分に実年代を当てはめていくのである。
いくつか掲げてみると、一つは窯の調査の際に出土することのある、年号の書かれた資料である。これがどの層から出土しているかによって、土層の年代を推定できる材料になる。また、特定の層の共通要素は捉えられているため、年代の記されたものであれば、世間に伝世しているものでも構わない。
それから、文献史料も忘れてはならない。窯によっては開窯時期や操業年代が記載されたものがあり、発掘調査成果との整合性があれば、有力な材料になる。しかし、この文献史料の関連では、直接生産地ではなく、消費地の遺跡の資料に有効なものが多い。それは、文献から年代の分かる火事層や火山灰層などが発見されている遺跡である。こうした遺跡は数が多いので、うまく組み合わせれば、かなり年代を捉える材料を得ることができる。ただし、消費遺跡の常として、使用期間の問題は十分に考慮する必要がある。
|
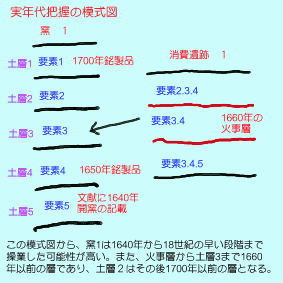
|
|
6.陶磁器の年代が分かれば…
|
|
このようにして陶磁器の年代が分かるということは、年代そのものが知りたい人にとっては、それ自体意味のあることだ。しかし、たとえば考古学のほとんどの時代の研究が、まずはやきものからスタートするのには、その他にもそれなりの理由がある。
やきものは、腐らない。やきものは、流行に敏感である。やきものは、たくさん消費されている。やきものは、いろんなところで使われている。やきものはいろんな階層の人たちに使用されている。
つまり、どこでもたくさん出てくるので、一つの時代を同じ物差しで計る上で、極めて便利なものなのである。たとえば、ある時期に流行した陶磁器が分かれば、その時期の思想や経済状況の一端を知ることができる。しかも、直接陶磁器から分からないことでも、陶磁器の年代が把握されることにより、出土数が少なく、それ自体では年代の把握できない物などの年代を捉えることができる。
このように陶磁器の歴史的な利用方法は、目的により無限大にあるのだ。たかが陶磁器、されど陶磁器なのである。
|
 物原層堆積状況 物原層堆積状況
(小溝上窯跡/有田町)
|