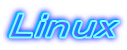朻尟俇丂僽乕僩儘乕僟偺愝掕
乣 偩傟偐偺偍偐偘偱慜偵恑傔傞帪傕偁傞 乣
乣 偩傟偐偺偍偐偘偱慜偵恑傔傞帪傕偁傞 乣
俇丏侾丂僽乕僩儘乕僟丠抦傜傫側傽丅
丂丂偙偺愡偺榖偼丄棟夝偟側偔偰傕俷俲偱偡丅旘偽偟偰丄師偺愡俇丏俀偵峴偭偰傕偐傑偄傑偣傫丅
丂丂乽僽乕僩儘乕僟偭偰壗側偺丠乿偲偄偆媈栤偵丄傾僶僂僩偱偡偑摎偊傑偡丅
丂丂偨偲偊榖偱幵偺僄儞僕儞偺巒摦偺夁掱傪榖偟傑偟傚偆丅幵偺僄儞僕儞傪摦偐偡偨傔偵偼丄僙儖儌乕僞乕偲偄偆儌乕僞乕偱僄儞僕儞偺撪晹丄擱從婡娭偵抏傒傪偮偗偰丄偦傟偐傜摦偐偡偟偔傒偵側偭偰偄傑偡丅
丂丂俴倝値倳倶偵偍偄偰丄偙偺僙儖儌乕僞乕偵憡摉偡傞偺偑丄僽乕僩儘乕僟偲偄偆僾儘僌儔儉偵側傝傑偡丅
丂丂幵偺僄儞僕儞偑僙儖儌乕僞乕傪昁梫偲偡傞偺偲丄俴倝値倳倶偑僽乕僩儘乕僟傪昁梫偲偡傞棟桼偼彮乆堎側傝傑偡偑丄杮懱傪摦偐偡偨傔偵曗彆揑側傕偺偱慜張棟傪偡傞偲偄偆偙偲偼丄帡偰偄傑偡傛偹丅
丂丂堦斒揑側僽乕僩儘乕僟傊偺擣幆偼丄乽暋悢偺俷俽傪擖傟偨偲偒偵丄偳偭偪偺俷俽偱僐儞僺儏乕僞傪婲摦偝偣傞偐慖戰偡傞僾儘僌儔儉丅僐儞僺儏乕僞偺揹尮傪俷俶偵偟偨偲偒偵尰傟傞丅乿偲偄偆傛偆偱偡丅
丂丂妋偐偵崅婡擻側僽乕僩儘乕僟偵偼丄偦偆偄偆堦柺乮婡擻乯傕偁傝傑偡丅俴倝値倳倶偺堦斒揑側僽乕僩儘乕僟偱偁傞俴俬俴俷傗俧倰倳倐傕偙偺婡擻傪帩偪崌傢偣偰偄傑偡丅偟偐偟丄尩枾偵偼丄忋婰偺捠傝偺俴倝値倳倶傪婲摦偡傞偨傔偺慜張棟傪峴偆僒僽丒僾儘僌儔儉偱偁傞偺偱偡丅
丂丂偙偺庤偺榖傪徻偟偔抦傝偨偗傟偽丄乽僐儞僺儏乕僞偺婲摦偺夁掱乿傪挷傋傟偽暘偐傝傑偡丅
僐儞僺儏乕僞偵揹尮傪擖傟偰丄俛俬俷俽偑撉傑傟丄俫俢俢偺俵俛俼乮儅僗僞乕僽乕僩儗僐乕僪乯偑撉傑傟丄俷俽偑棫偪忋偑傞丒丒丒偲偄偆曈傝偺榖偱偡偹丅
俇丏俀丂僽乕僩儘乕僟偺愝掕
丂丂偝偰丄俴倝値倳倶傪柍帠僀儞僗僩乕儖偡傞偙偲偑崱夞偺栚揑偱偡丅棟榑偼偦偭偪偺偗偱丄幨恀偮偒偱愢柧偟偰偄偒傑偟傚偆丅
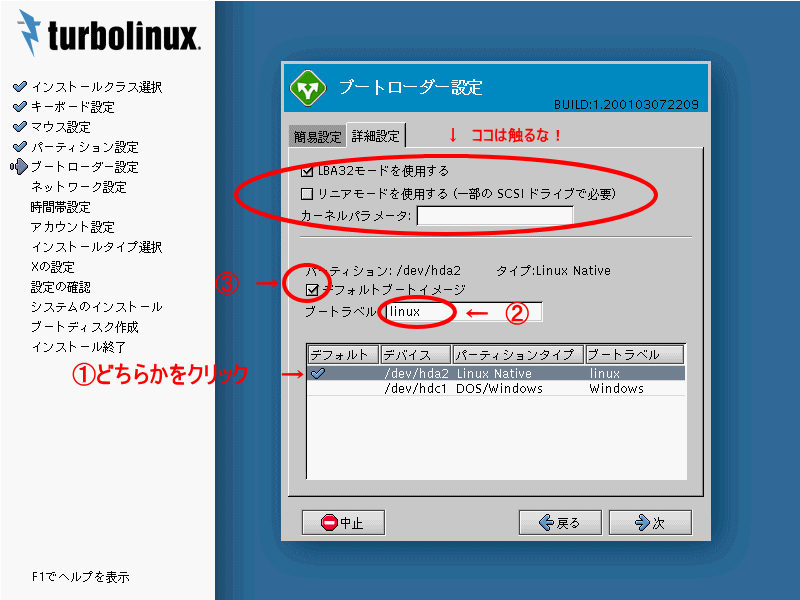
張棟庤弴偼師偺捠傝丅
俽俿俤俹侾丗丂丂嘆偺傛偆偵丄偳偪傜偐傪僋儕僢僋
俽俿俤俹俀丗丂丂嘇偺傛偆偵丄俷俽偵岲偒側柤慜傪偮偗傞丅偙偺幨恀偵廗偭偰傕偄偄丅
丂丂丂丂丂丂丂嘆偑巜偟帵偟偰傞偲偙傠偺丄乽僽乕僩儔儀儖乿偺棑偵斀塮偝傟傞丅
俽俿俤俹俁丗丂丂嘊偺傛偆偵丄偳偪傜偐偺俷俽偺傪僋儕僢僋偡傞丅
丂丂丂丂丂丂丂嘆偑巜偟帵偟偰傞偲偙傠偺丄乽僨僼僅儖僩乿偺棑偵斀塮偝傟傞丅
丂丂丂丂丂丂丂僐儞僺儏乕僞偺揹尮傪俷俶偵偟偨偲偒丄俷俽偺慖戰夋柺偑尰傟傞丅
丂丂丂丂丂丂偦偺偲偒偵壗傕慖偽側偄偲丄偙偙偱乽僨僼僅儖僩乿偵巜掕偟偨俷俽偑帺摦揑偵婲摦偡傞丅
俽俿俤俹係丗丂丂嘆偵暋悢偺崁栚偑偁傟偽丄偦傟偧傟偵懳偟偰丄俽俿俤俹侾乣係傪孞傝曉偡丅
丂丂僆僗僗儊偲偟偰偼丄俽俿俤俹俁偺僨僼僅儖僩偺俷俽偼Windows偑擖偭偰傞側傜丄Windows偵偟偰偍偄偨傎偆偑偄偄偲巚偄傑偡丅側偍丄偙傟偼昅幰偺宱尡榑傗丄岲傒偱偡偺偱丄嫮惂偱偼偁傝傑偣傫丅
丂偝傜偵丄愝掕偼恑傒傑偡丅
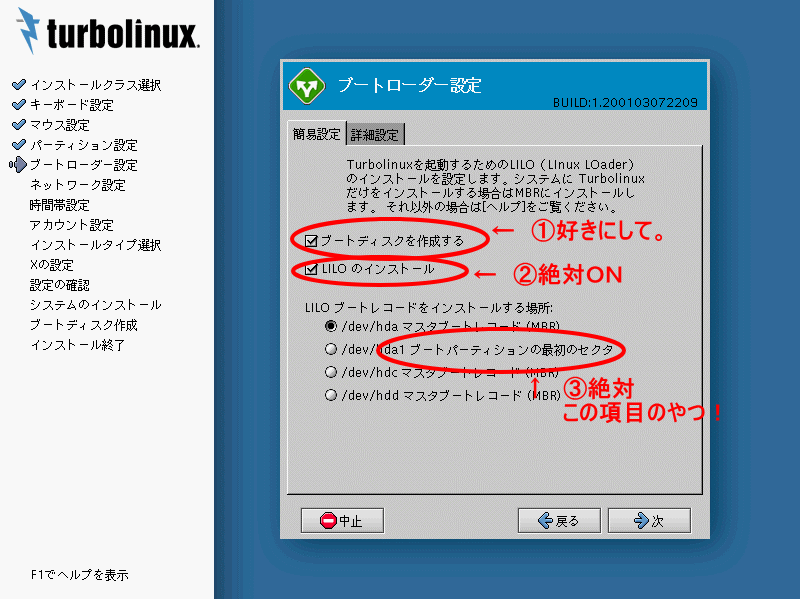
丂偙偙偵偍偄偰丄拲堄偟側偗傟偽側傜側偄偙偲偼俁偮丅
偦偺堧丗丂丂嘆偺傛偆偵丄僽乕僩僨傿僗僋偼岲傒偱嶌偭偰偄偄偱偡偑丄
丂丂丂丂丂丂丂Windows偱僼僅乕儅僢僩嵪傒偺僼儘僢僺乕侾枃偑昁梫偱偡丅
偦偺擉丗丂丂嘇偺傛偆偵丄偙偺愝掕偼昁偢俷俶偵偡傞偙偲両両
丂丂丂丂丂丂丂乽俴俬俴俷乿偱側偔丄乽俧俼U俛乿偲側偭偰傞偐傕抦傟傑偣傫丅俧倰倳倐偼俴俬俴俷偺恑壔宍偱偡丅
丂丂丂丂丂丂丂偳偪傜偱偁傠偆偲丄俷俶偵偟偰偔偩偝偄丅偙偺僾儘僌儔儉側偔偟偰俴倝値倳倶偼婲摦偟傑偣傫丅
偦偺嶲丗丂丂嘊偺傛偆偵丄昁偢偙偺乽僽乕僩僷乕僥傿僔儑儞偺嵟弶偺僙僋僞乿傪慖傇偙偲両
丂丂丂丂丂丂丂儅僗僞乕丒僽乕僩丒儗僐乕僪乮俵俛俼乯偼丄僩儔僽儖偺壩庬偱偡両両
丂丂俴俬俴俷傪偳偙偺応強偵僀儞僗僩乕儖偡傞偐丠
丂偙傟偵偮偄偰傕丄昅幰偼幐攕択傪偐傜傔偰彮乆擬偔岅傟傞偺偱偡偑丄偦傟偼偄偮偐偺島庍偱丒丒丒丅
 丂
丂 |

|
丂
|