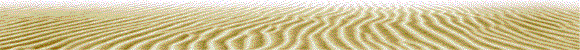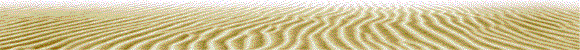
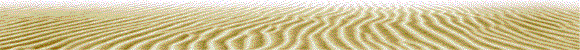
浄土真宗を開かれたのは親鸞聖人であります。
しかし開祖といっても、自分でひとつの宗旨を開こう
などという意志をもって教えをひろめられたものでは
なくて、あくまでも、みずから如来の本願を信じ、
そのお慈悲を生きるひとりの行者として、また恩師
源空上人を慈父のように慕い、そのよき弟子として
終始されたことは、「本師源空あらわれて浄土真宗を
ひらきつつ」とうたわれた『和讃』のうえにもあきらかに
うかがわれます。
また「浄土真宗」ということばにしても、ただ単に
ひとつの宗派をあらわす宗名としてではなくて、
よき師である源空上人からうけたまわった、真実の
教えをあらわされたものにほかなりません。
人間というものは、すこしでも人からほめられると、
とかく思いあがるものであり、まして人の師と
仰がれるようにでもなれば、弟子の数を一人でも
多くかぞえたい名利欲や、”わが弟子である”という
執われ心がおこりがちなものであります。
ところが聖人は、立派な弟子がたくさんあったにも
かかわらず、「 親鸞は弟子一人ももたず候う 」
(歎異抄)といい、「 なにごとををしへて弟子といふ
べきぞや、みな如来の御弟子なれば、みなともに
同行なり 」 (口伝鈔)ともいっておられます。
そして自分自身では、真宗の正しいみ教えは、
七人の高僧がたが受け伝えてくださったたまもの
であると高く仰いで、「七高僧はねんごろに
釈迦のみこころあらわして 弥陀の誓いの
正機をば われらにありとあかします」とたたえ、
「このみさとしを信ずべし」(しんじんのうた)という
姿勢を生涯つらぬいていかれました。
そのように執われのない謙虚な人柄は、かえって
多くの人びとの信望と尊敬とをあつめ、「同一に
念仏して別の道なきがゆえに、遠く通ずるに、
それ四海の内みなきょうだいとするなり」(往生論註・
七祖篇)というように、ひとつの教団が自然にかたち
づくられ、それが今では「浄土真宗」という一大教団
にまで発展してきたのであります。
そしてその「ご開山さま」として七百余年このかた、
幾千万の人びとから敬い慕われている人こそ
わが親鸞聖人であり、このことは浄土真宗という
教団を知るうえで、きわめて重要なことであると
いえましょう。
いまこの偉大な ”野のひじり” ともいわれる
親鸞聖人の、波乱にとんだ生涯を点描して、
そのご苦労をしのぶとともに、人間の生き方を
学んでみようと思います。
聖人は、平安時代の末にあたる承安三年(1173)
四月一日、太陽暦にして五月二十一日、京都の東南に
あたる日野の里でお生まれになリ、幼名を松若丸と
よばれたと伝えられます。
父の名は日野有範といい、藤原氏のわかれで
官職は皇太后宮大進でありましたが、のちに出家して
三室戸大進入道とよばれ、日野から四キロほど南に
行った三室戸に身をひそめられたようであります。
有範卿が出家された動機については、仕えていた
皇太后がなくなられたことや、そのころ藤原氏と平氏
が権力争いをつづけているあいだに、平家を討とうと
する源氏の動きもおきはじめ、宮中ではさまざまな
対立や分裂が生じて、日野家一門の立場に不利な
できごとがおこったために、役職を辞任して入道され
たものと思われます。
その後かなり長命して、親鸞、尋有、兼有などの
子どもが成人してから世を去られました。
このことは、兄弟がそろって父の喪に服し追慕し
ながら『仏説無量寿経』の本文に訓点を記された
ことがあって、それを正平六年(1351)に写した
ものが、本願寺に現在も保存されていることで
うなずけます。
また生母については、その名を吉光女といって、
源氏の一族である義親の息女とか、義家の孫に
あたるとかいわれ、聖人が八歳になられるとき
死別されたものといい伝えられておりますが、
史実にはあきらかでありません。
聖人が生まれ、幼時をすごされたところは日野の
法界寺あたりといわれ、境内にある阿弥陀堂は、
日野家の五代の祖である資業の発願によって
建てられたものです。
この堂を東にのぼると日野家の墓もあるところから、
本願寺第十九世本如上人は、この地を親鸞聖人
ご誕生の聖地として顕彰につとめられ、ちかくは
昭和六年に「誕生院」も建ち、、「聖人幼童の御影」が
おさめられてあります。
おもえば聖人が生きられた時代、とくにその
幼年期から青年期にかけては、わが国の歴史の
流れが大きな転換期に向かっておりました。
すなわち、藤原氏を中心として長くつづいていた
貴族政治が、新しく頭をもたげてきた武家政治に
かわろうとする、時代の大波がうねり狂うときで
あったのです。
聖人が生まれられた承安三年、それは平治の乱に
よって平家が政権をにぎってから十四年目であり、
その勢力がもっとも盛んであったときにあたります。
だから聖人の生れが藤原氏の一門ということで
あっても、その威光はすでにおとろえ、斜陽の
かすかな光りをとどめていたにすぎません。
そういう状況のなかで、父をはじめ兄弟すべてが
出家しなければならないという、一家にとって
悲しいできごとがつぎつぎとおこり、幼い聖人の
生活は、けっしてしあわせなものではなかった
ようであります。
そうした内部の事情にあわせて巷では、
院政のゆきづまりから戦乱がひきづづき、
たびたびおそいかかる天災地変や悪病の流行で
人びとは不安におびえながら苦しい生活をおくって
いました。
たとえば聖人が四歳になられた春と、七歳の秋には、
大きな地震がおきて多くの家が倒れ、五歳の春には、
京都の三分の一を焼失するほどの大きな火災が
ありました。
また養和元年(1181・聖人九歳)には、前例のない大飢饉が
おそって、それは翌年までつづき、みやびやかな
はずの都大路は、死体のにおいがただよい、廃虚の
街になりはてたといわれています。
そういう騒ぎをさらにかりたてるように、治承四年
(1180・聖人八歳)には、日野家と関係の深い
源頼政と以仁王が平家を倒そうとして戦をはじめ、
しかも宇治川で敗れて戦死しましたから、そうで
なくても落ち目になっていた日野家が、いよいよ
悲境に追い込まれてゆきました。
この宇治川の合戦をさきがけとして、古代社会における
最後の政権を担当した平家も、滅亡の一途をたどる
のであります。
このように騒然とした生きにくい時代に成長された
聖人は、九歳の春、伯父の範綱卿につれられて
東山の青蓮院をたずね、慈円僧正の坊舎であわただしく
得度の式を受けられ、名まえも範宴とあらためられました。
生きてゆく目標も立ちかねる、移り変わりの
はげしい時代に、しかも、人の世のさまざまなつらさを
心にだいて成長された聖人は、人びとが追いかけ
求めている財産や地位というものが、どんなに空しく、
はかないものかということを、いやというほど見せつけ
られていましたから、世のなかがどんなに変わっても、
けっして変わることのない幸福をえたいと願われた
ことでありましょう。
得度の式がのばされようとしたとき、
明日ありと 思う心のあだざくら
夜半に嵐の吹かぬものかは
という歌を示して、式をいそがれたと伝えられるのも、
そういう願いの切実さをあらわしているのでしょう。
そして聖人は、幼いときから仰いでは、心をひかれて
いたあこがれの比叡山に、のぼっていかれたので
あります。
そのころの比叡山は、天台宗の根本道場で
あったばかりでなく、日本における仏教の最高学府
として、東堂,西塔,横川にたくさんな僧院をもち、
数多くの僧侶があつまっていました。
そうした僧侶集団の身分は、学生と堂僧と堂衆に
分かれていたようであります。
学生というのは貴族や殿上人の出身者で、
小僧都から僧都へ、そして未来の天台座主へと、
はなばなしい栄達の道をすすむ、それこそ
”えらばれた人びと” でありました。
堂衆は、学生がつれてきた従者が法師になった
もので、道を求める心もあまりなく、堕落するものも
あって ”山門滅亡、堂衆合戦” とか ”叡山の
荒法師” といわれ、一般の人びとから恐れられた
のもこの一群でした
そして堂僧というのは、山内の諸堂に奉仕をする
役僧や、常行堂で不断念仏の行をはげむ念仏僧を
総称したものであります。
範宴とよばれるようになった聖人は、どんな身分で
あったかといいますと、大正十年に本願寺の宝庫
から発見された、聖人の内室である恵信尼さまの
手紙に、
「殿が比叡山で堂僧をつとめておいでになりました
・・・・」とあることから、下山のまえには堂僧で
あったことが明らかになりました。
藤原氏のわかれであり、父が正五位下という、
あまり高くない身分ではあっても、貴族・殿上人に
ちがいはないので、聖人も当然学生になられたはずで
あります。
それにもかかわらず堂僧の道をすすまれたという
ところにも、仏道修行への思いが、いかに一途な
ものであったかをうかがえましょう。
伝教大師最澄によって比叡山が開かれてから
二百年、中興の祖である良源座主の時代を頂点として、
この一大法城も宗教的に退廃し、堕落していきました。
一見うつくしくみえていた山上も、深くはいりこんで
みれば俗世間とかわらず、みにくい欲望や、嫉みや
争いが渦をまいていたのです。
僧侶の姿はしていても、心から道を求めている真の
仏弟子はまれでした。
そのときの心境は、晩年につくられた『悲歎述懐和讃』
にあらわれています。
このような環境への失望にあわせて、もっと根本的な
そして深刻なものは、自分自身に対する挫折感で
ありました。
ただ身をそこにおくだけで、なんの自覚ももたず、
その日その日をすごしている人びとのなかで、聖人は
自分を見失わず、ひたすら仏のさとりを求めて、
それこそ夜を徹して経典を読み、血のにじむような
修行に専念されました。
しかし学問が深まれば深まるほど、厳しい修行を
つめばつむほど、いままで気づかなかった自分の
おこないの内容のまずしさが知られ、浄らかさも、
まことも、もちつづけることのできない、あさましい
心のすがたが目立つばかりでありました。
聖人は、自分の力で心をみがき、行をはげんで
仏のさとりにたどりつこうとする、聖道自力の教えが
どんなにむずかしいものであるかを知るにつれて、
しだいに心を浄土教に向けてゆくようになられました。
さいわい横川には、かつて源信僧都という浄土教の
先覚者がおられました。
東塔や西塔が栄華をきわめ堕落したときでも、横川
だけが本来の面目をたもちつづけ、山の念仏は源信
僧都によって伝統がまもられ、ひろめられていたと
いわれています。
恵信尼さまの手紙と、『伝絵』の「楞厳横川の余流を
たたえて・・・・」とをあわせ考えてみると、横川の
首楞厳院で堂僧として、不断念仏の行をはげまれた
ことがうかがわれます。
不断念仏というのは、仏の救いにあずかるために
道場にこもって、身はつねに阿弥陀仏のお像のまわり
をめぐり、口はつねに阿弥陀仏の名を称え、心はつねに
阿弥陀仏を念じつづけることによって、阿弥陀仏と行者
がひとつに融けあう、三昧の境地にいたることができると
いうものです。
そのためには、いっそう堅固に戒律をまもり、心を平静
にたもち、正しい智慧によって真理をさとらねば
なりませんから、その行者としての聖人は、戒律と
禅定と智慧という三学に達した聖僧として、いままで
にもまして刻苦精進されました。
こうして自分の心を清らかに静めてゆくことによって、
いつかはかならず心のなかに阿弥陀仏があらわれ、
救ってくださるにちがいないと信じられたからであります。
しかし聖人はただのいちども、救われた境地にひたることは
できませんでした。
そこで修行のやりかたを変えて、一心不乱の称名を
説く『阿弥陀経』にもとづき、また源信僧都の『往生要集』
に示された「往生の業は念仏を本となす」の指導によって、
「南無阿弥陀仏」「南無阿弥陀仏」と仏の名を称え
られました。
こうして仏の名を称えて一心に救いを念じておれば、
仏はその願いにこたえて、きっと自分を救ってくださる
ものと思われたからであります。
だが、どれほど一心不乱に念仏を称えても、救われた
よろこびの心をもつことはできなかったのです。
聖人の心には苦悩の闇が深まるばかりでありました。
くろぐろと巨大にそびえる山の端に、天を斬るような
上弦の月は光っていても、このなやみを解決して
くれる教えも人も、もはやこの比叡山には見あたらぬ
ように思われるのでした
そうした聖人の心をしきりによぎるのは、うわさに聞く
吉水の法然房源空上人のことでありました。
源空上人がいままでの浄土教から独立して、
浄土宗という一派を立てて専修念仏をとなえられたのは、
安元元年(1175)であり、聖人がまだ三歳の時でしたが、
それから二十六年を過ぎてその教化は各地におよび、
とくに後世の問題を解決する上人として、吉水には
聴聞者がつめかけていました。
そして後白河法皇が源空上人を先達としてお経を
写し、それを首楞厳院に奉納されたことや、関白九条
兼実公が聞法受戒されたことや、源平の合戦で
勇名をはせた熊谷直実が弟子になったことなど、
都では大きな話題をよんでいたのです。
まことの救いに望みの絶えたいま、いっそのこと
山をおりて、その ”うわさのよき師” に会ってみたい
と、聖人の思いはかりたてられるばかりでありました。
”比叡山であれほど深く学問にうちこみ、きびしい
修行をはたしながら、観想をこらすどころか、一心不乱の
念仏さえ困難であった。
特に幼少のころより恋いしたっている両親のいます
後世(浄土)のことは、まったく解決されていない。
まず、このわたくしの問題が解決されて、あらゆる人
の後世に対する不安が除かれることが、ほんとう
の救いでなくてはならない・・・・・”
そういう問題が心にわだかまっていた聖人は、
二十九歳の春、在家仏教の先達である聖徳太子
にゆかりの深い、京都の六角堂の救世観音に
このことを念じて、自分のすすむべき道をたずねる
決心をされました。
「 殿が比叡山をおりられ、六角堂に百日間おこもり
になり、後世のたすかるように祈念あそばされましたら、
九十五日目の明け方、夢の中で、聖徳太子が偈文を
唱えられて、後世の問題を解決する道をお示しください
ました。
後世のことは、よき人にもあしきにも同じように
迷いをはなれる、ただ一つの道である」
(恵信尼消息)ことを領解せられたのであります。
つまり聖人は、この救世観音のお示しから、これまで
悶えつづけてきた問題に、ひとつの示唆を感じとられ
たのでありましょう。
「すぐ、その夜明けに六角堂をお出ましになり、
後世のたすかるご法縁にあわせていただくため
お訪ねあそばして」吉水の草庵で源空上人に
遇われたのであります。
それから聖人は、「また百日の間、雨の降る日も
炎天の日も、どんなお具合いの悪い時でも、
上人の許へお通いになって」つぎつぎおこる
不審を問いただし、得心のゆくまで吉水に
通いつづけていかれました。
源空上人から、”弥陀の本願は、もとより凡夫を
救うためにおこされたものであるから、信じてみ名を
称えるばかりである ” と聞かされて、聖人は
この簡明な念仏の教えを、大きな驚きをもって
心に受けとめられたことでありましょう。
そして心の闇に大きな光りを点ぜられたので
あります。
その結果はじめて、 ”源空上人の行かれるところ
ならば、それがたとい地獄であろうとも、わたくしは
よろこんでついてゆく ” という思いをきめられるまで
になられたのであります。
おもうに、聖人が六角堂に百日こもられたことは、
過去の自分に区切りをつけて新しい道を求める
ための願いからであり、さらに吉水に百日通って
聞法されたことは、よき師にめぐりあえたのちの
求道心がいかに真剣であったか、ということの
あらわれであります。
けっして源空上人に遇うなリ、即座に本願他力に
帰入されたのではなくて、そういう道程のはてに
こそ、「 しかるに愚禿釈の鸞、建仁辛酉の暦、
雑行を棄てて本願に帰す 」(「教行信証」後序)
という、一生にただ一度の心の大転換が、
もたらされていることを見落としてはなりません。
このとき聖人は二十九歳であり、源空上人は
六十九歳でありました。
源空上人の教えは、” 末法の世の人間は
智慧も力もおとっているから、どれほど修行に
はげもうとしても、思いがつづかず、雑念がまざり、
行がたち切れて、自分の力でさとりきれるもの
ではない。
そこで、救いのてだての一切をすでに用意して、
この自分を求めていてくださる阿弥陀如来の
本願のこころを聞かせていただき、その救いを
信じて生きることである。
この道こそ、力づよい如来の願力だから、迷いに
沈み罪にけがされている身であっても、きっと
生死を離れて、さとりに至らしめられるただひとつの
道である ”というものでありました。
聖人はこのようにしてはじめて如来を信じ、
念仏の道にはいり、如来とともに生きる、何もの
にもくじけないあたらしい人生に向かうことが
できたのであります。
源空上人の門弟となり、名を綽空と改められた
聖人は、さらに教えの奥義をきわめようと、たゆまぬ
努力をつづけ、門弟のなかで、しだいに頭角を
あらわされるようになりました。
そのころ書き写されたものと思われる『観無量寿経
集註』 『阿弥陀経集註』は、聖人の青年時代の筆跡
をとどめる貴重なもので、『観無量寿経』 と 『阿弥陀
経』の本文をたくましい筆致で写し、その行間や上下の
空白に、関係のあるいろいろな仏典から、参考になる
ことばを引用して、ぎっしり書き入れてあります。
いかに熱意を燃やして勉学にいそしまれたかが
しのばれます。
万事につけてそのように熱心であり、ゆきとどいている
弟子の綽空を、源空上人がどれだけ重くみられたかは、
九条兼実公の求めによって著わし、 ”一読されたのちは
焼くなリ埋めるなりして、机上に遺さないように ”と、
公開することをとめたほどの『選択本願念仏集』を肖像
とともに、三十三歳のとき特に書き写すことを許し、また
それに署名しておられることでもうかがわれましょう。
それは聖人にとって大きな栄誉でありました。
この感激を主著である 『 教行信証 』 の化身土巻の後序
に銘記して、生涯忘れられることがありませんでした。
この年の閏七月二十九日に名まえを善信と改め、
源空上人がみずからその名を書きおくっておられます。
そのほか、『歎異抄』のおわりや『伝絵』にのせられて
いる信心についての諍論で ”源空上人の信心と善信
の信心とおなじであって、すこしもかわりはありません。
自力の信ならば、智慧のちがいや、念仏の経験の
長い短いで信心もちがってきましょう。
しかし、他力の信は如来よりたまわった信心だから、
みなおなじであります ” と聖人がいわれたので、
弟子たちのあいだで論争がはじまりましたが、源空
上人は善信の主張に賛成されたことや、別に『伝絵』
の信行両座のいい伝えも、この師と弟子がおたがいに、
いかに深く信頼しあっていたかを物語るものであります。
よき師にめぐり遇い、そのひざもとですごされた
聖人の、このような平穏な生活も、乱れた世間の
波が容赦もなくおそいかかってきて、そう長く許し
てはおきませんでした。
源空上人の説かれる念仏の教えが、さかんになって
ゆくことを快く思っていない比叡山や奈良の僧侶たち
は、ことあるごとに吉水の教団を非難してきましたが、
元久元年(1204)になると延暦寺の僧徒たちは、
一部の念仏者の非行を口実にして、吉水教団の
解散を要求しました。
それに対して源空上人は、ただちに七ヶ条の
起請文を書き、門弟一八九人の署名をそえておくられ
ましたので、延暦寺もそれで一応なっとくし、
さいわい事なきをえました。
しかし翌年になると、こんどは奈良の興福寺から
専修念仏を禁止するよう、九ヶ条の奏上文を
朝廷にさしだしたので、ついに念仏を禁じ、教団
を解散せよという命令が出されたのであります。
「ひそかにおもんみれば、聖道の諸教は行証
久しく廃れ、浄土の真宗は証道いま盛んなり、
しかるに諸寺の釈門、教に昏くして真仮の門戸を
知らず、洛都の儒林、行に迷ひて邪正の道路を
弁ふることなし。
ここをもって興福寺の学徒、太上天皇、後鳥羽の院と
号す、諱尊成、今上、土御門の院と号す、諱為仁、
聖暦、承元丁卯の歳、仲春上旬の候に奏達す。
主上臣下、法に背き義に違し、忿りを成し怨みを
結ぶ 」 (教行信証・後序)と、激しい調子で
しるしてあります。
(参考・・・・以下、9行は、第27版の意訳の文章
「 聖道門の諸寺の僧侶たちは、教法にくらくて
真仮の別があることを知らず、都の学者たちも、
行法の正邪の区別をわきまえない。
こういうわけで興福寺の学僧たちは、太上天皇
(後鳥羽)今上天皇(土御門)の御代、承元丁卯
の歳、仲春上旬のころ奏達した。
主上も臣下の者も、正しいおきてによらず正義に
違って、忿り怨みの心を起こした」と、『教行信証』
の後序に激しい調子でしるしてあります。・・・・
参考を終わる)
そして七十五歳の源空上人は、藤井元彦の
俗名で土佐に、三十五歳の聖人は、藤井善信
の俗名で越後の国府に流罪となりました。
その時代は、どんな理由があっても、出家を
罰することはできなかったので、いったん還俗
させて俗名をつけてから刑を行ったのであります。
このうえなく美しい師弟愛でむすばれ、 ” 源空
上人のゆかれるところならば、それがたとい地獄
であろうとも、わたくしはよろこんでついてゆく ”
とまでいわれた聖人とその ” よき師 ” は、
冷たい権力によって東と西に遠くへだてられ、
その後はこの世で再会される機会はありません
でした。
七百年もむかしの越後は、淋しい田舎でありました。
低くたれこめる黒雲と、北海に狂う荒波は、そうで
なくてもわびしい流刑の身の、旅愁をそそらずには
いませんでした。
膚をつく寒風のなかに光る配所の月は、人生を
甘く美しく装っていたものをみな打ち消して、
ごまかすことのできない人生の実相を、赤裸々に
てらしだしているのです。
聖人はこの思いがけぬ逆縁のなかで、すこしも
ひるむことなく、いよいよ自己をみつめ、信心を
深めていかれました。
そして「非僧非俗」の境地を自覚し、
「愚禿」と名のられたのであります。
そのころ、律令制度のもとでは、僧は寺院に
あって、もっぱら戒律をたもち、学行に励みながら、
国家の安泰と興隆を祈念していましたので、
自由に民衆に接し仏法を説くことなど、きわめて
稀でありました。
だから、聖人が「僧に非ず」といわれたのは、
そういう国家権力による僧ではなくなったことを
あらわし、「俗に非ず」とは、律令僧のかたちは
とらないけれども、内には深く如来を信じ、外には
その喜びを、何はばかることもなく伝えてゆける
僧侶になられたということの表明であります。
また「愚禿」と名のられたことも、「僧侶の身分を
奪って俗人の姓名をつけて遠い所へ流した。
私もその一人である。それゆえ、もはや僧でもなく
俗でもない。
こういうわけで、禿の字を用いて姓としたのである」
(「教行信証」後序)と、不当な弾圧を加えた
外部の権力に向かって表明されただけのもの
ではなく、「愚」という字がつけられている
ところからうかがいますと、自分自身に向けられた、
きびしい内省のことばでもありました。
「禿」ということは、外見は僧の姿であっても、
その心と行いは世俗の人とかわらない、
みにくい、あさましい凡夫であるということで
あります。
聖人が八十三歳のころに書かれた『愚禿鈔』
のなかに、
「賢者の信を聞いて、愚禿が心を顕わす。
賢者の信は、内は賢にして外は愚なり。
愚禿の心は、内は愚にして外は賢なリ」
とありますが、そういう感懐は、人間の良心的な
反省といった底の浅いものではなくて、限りない
如来の慈悲の光りに照らしだされて、わが身の
愚かさ、至らなさが知らされるとともに、しかも
そのままが如来の大悲におさめとられていると
いう、身のしあわせをよろこばずにはいられない、
慚愧と感謝の思いが「愚禿」の二字にこもって
いるのです。
そして聖人は、流罪という逆縁を転じて、都を
遠く離れた民衆に如来の本願を伝える良縁とし、
「もし、われ配所におもむかずんば、なにによって
か辺鄙の群類を化せん。これなお師教の恩致なり」
(伝絵)と、うけとめていられるのであります。
聖人の結婚については、まだ不明な点も
残されておりますが、一般に越後の地で一人の
女性と結婚し、家庭をもたれたといわれています。
その人は兵部大輔三善為教の息女で、のちに
恵信尼さまとよばれるお方であります。
聖人より九つ年下の寅年の生れであると、自分で
いっておられることや、聖人が三十九歳、恵信尼
さまが三十歳の三月三日に、信蓮房が生まれて
いることからして、流罪後ほどなくして、結婚されたと
うかがわれます。
なお恵信尼さまの手紙がみつかるまでは、
関白九条兼実公の息女、玉日姫が聖人の奥方で
あるといわれておりました。
しかしそれに該当する女性は、九条家の系図にも、
兼実公の日記『玉葉』にもみあたらず、外部の
資料もないというのが史家の定説であります。
そこで玉日の説話について考えられることは、
聖人が吉水の源空上人をたずねる動機となり、
また後に妻帯にふみきられる決意ともなった
六角堂における救世菩薩の示現の文が
「仏道の修行者であるそなたが、妻帯するように
なれば、わたしが玉女の身になって結ばれよう
そして一生よく仕えて人生をととのえ 命終わる
ときには浄土に導こう」という意味のものであった
ことから、聖人の妻となる人は「玉女」、すなわち
玉日姫と伝えられたものと思われます。
さて恵信尼さまの生家である三善家は、
南北朝時代から室町時代の三百四十年に
わたって、越後に名をとどめている豪族であり、
恵信尼さまの父の為教という人は、九条家が
越後にもっている荘園を、ある期間あずかって
いたこともあるらしいので、恵信尼さまは京都の
生れか、あるいは九条家に仕えて、都ぐらしを
されたことがあるらしく、気品と教養をかねそなえた
女性でありました。
二人の家庭生活が、どんなに深い尊敬と信頼に
みちた、立派なものであったかは、恵信尼さまの
手紙によってうかがうことができます。
その手紙は、聖人がなくなられてからのち、
恵信尼さまが八十二歳から八十七歳までの
あいだに、末娘の覚信尼さまにあてて書かれた
もので、父の信心上の苦悩や、源空上人の
教えを聞くようになられた動機や、日ごろの
言行が手にとるようにしたためてあり、わが子に
求道者としての父のすがたを伝えるとともに、
その父の求めたものを忘れないようにと
願う、念仏者としての母の態度が示されていて、
さすがに敬服せずにはおられません。
また、聖人一家が常陸の下妻に住んでおられ
るとき、源空上人は勢至菩薩の化身であり、
親鸞聖人は観音菩薩の化身であると、夢の
なかで知らされたことを書かれた手紙の終わ
りの部分に、「殿が観音菩薩の化身であらせら
れる夢のことは申しあげませんでしたけれども、
それ以来、心の中では普通の人とは思わず
お仕えして参りました。
あなたさまもこのようにお心得おきください」と
したためておられますが、聖人の人柄が
しのばれるとともに、恵信尼さまがいかに
敬愛の心で、夫である聖人に仕えられたかが
しのばれます。
当時の女性としてはめずらしく高い教養と、あふれる
気品をもったよき妻として、聖人の偉大な行跡を
内助してゆかれた恵信尼さまこそ、まことに
宗門の母とよぶにふさわしいお方でありました。
| どうぞ一言(伝言板) | ホームページトップへ |