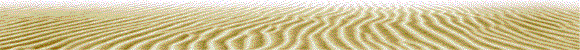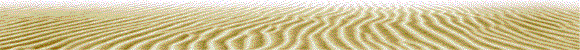
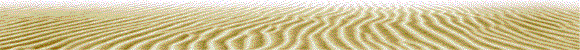
流罪から五年たった建暦元年(1211、
聖人三十九歳)十一月十七日、聖人は源空上人
と同じ日付けでその罪を赦されて、自由の身に
なられましたが、そのまましばらくこの地にと
どまって、京都へは帰られませんでした。
それは源空上人が、赦免からわずか二ヶ月後に
なくなられたことや、信蓮房が生まれて一年にも
満たなかったためと思われます。
しかし建保二年(1214)、四十二歳になると妻子を
つれて、七年間すごしてきた越後をあとに、信州を
経て、関東の常陸(茨城県)に移られました。
そのころの関東一帯は、新しい鎌倉時代を
迎えて、ようやく活気づいてきたとはいえ、農民
たちの多くは、土地を支配する武士や地主の
圧制と、毎年のようにおそいかかる天災のもとで、
苦しい生活をつづけていたのです。
そういう悲惨なすがたが、聖人の心をよほどつよく
痛めたのでしょう。
建保二年(1214)のころ、旅の途中で衆生利益
のために、「三部経」を一千部読もうと思いたたれ
ました。
しかし、”念仏のほかに、なにの不足があって
お経を一千部も読もうとしたのであろうか。
自ら信じ、人を教えて信じさせることこそ、まことに
如来のご恩に報い、その徳に感謝することである”
と、思いなおして中止されたことがありました。
みじめな状態におかれている民衆、その救いよう
のない苦しみを目のあたりにして、「三部経」を
一千遍読むことでなんとかなればと、聖人が
思いたたれたのも無理のないことであります。
また、それから十七年すぎた寛喜三年(1231)
四月十四日から四、五日、聖人は風邪をひいて
高い熱を出し、夢うつつのなかで『大無量寿経』を
読もうとして、思いとどまられたことがありました。
このふたつのことを思いあわせて、”自力の執われ
ごころが、どれほど抜けにくいものであるか、よくよく
注意しなければならない” と、正しい信心のありかた
を反省して、きびしく自分をいましめておられます。
そうして、この民衆の苦しみも、そういう気休めの
ものではなく、人びとの心に信心の灯をともし、苦悩
から開放しなければならないという、使命感をいっそう
強くいだかれるのでありました。
常陸にはいられた聖人は、下妻・小島や稲田などに
住んで、二十年にわたって伝道にはげまれました。
その努力が実をむすんで、徳を慕い、教えを求める
人びとは、常陸を中心に、遠く奥州方面にまで
およんだのであります。
しかし聖人は生涯にひとつの寺院も建てず、縁に
したがってあつまる人びとを、身分の上下で
へだてることなく、おん同朋、おん同行とよびかけ、
あるときは道ばたのお堂で、またあるときは民家の
炉ばたで、膝をまじえて仏法を語り合われました。
ですから聖人の場合、布教伝道といっても、
辻に立って弁舌さわやかに教えを説くとか、広間に
あつまった大衆に、大導師よろしく説法するとか
いうものではなくて、咄々として真実を語りかけ、
また相手のことばに耳をかたむけていかれたようで
あります。
それはけっして消極的な方法ではなく、むしろ、
あまりにも苦しい生活に追われ、日常的なことに
埋没していた人びとに、自分の苦悩を自覚させ、
問題をみつめる意識をよびさまし、その心の底に
如来の大悲がじゅんじゅんと浸み透ってゆく、
真に心のふれあう教化でありました。
山伏として祈祷をすすめる弁円が、鬼神や
魔神を拝まず、祈祷やまじないを行わないようにと
説かれる聖人を恨み、板敷山で待ちぶせて、
何度も殺そうとしましたが果たせませんでした。
そこで稲田の草庵におしかけましたが、聖人の
大空のように広い心にふれると、たちまち害心が
消え失せ、その場で弟子になって、明法房という
名をいただきました。
”明法房も、もとは不可思議のよからぬことを
考えたりしたのであるが、のちにその心をひるが
えして、このたびはめでたく往生をとげました”
これは後年になって明法房がなくなったとき、
聖人が門弟におくられた手紙の一節であります。
そのほか、村びとから悪四郎といってきらわれ
ていた乱暴ものが、聖人に導かれて弟子となリ、
もちまえの才知と手腕を発揮して聖人の伝道を
たすけた横曽根門徒の長老性信房や、名主と
いう立場にありながら門弟になって念仏生活に
生き、財政の面から聖人の教化をささえた高田の
真仏房など、みな聖人の教えによって信を決定
した人びとでありました。
これらの人は聞いたことを心に深く刻んで忘れず、
弟子の一人唯円房は聖人の教えを正しく伝える
ために『歎異抄』を著わしましたが、この書に
接する万人のうえに、聖人の体温がじかに
伝わってくるようであります。
寄り合い談合しては、聖人とつよく結ばれ、
心に灯をともされた民衆は、権力によって支配
される社会ではなく、ゆるぎのない如来の本願を
土台にした念仏者の同朋集団を、関東一帯に
築いていきました。
聖人の直弟子は四十四人、孫弟子のなかで
お会いして教えを受けたものと、聖人の手紙や、
その他の書面に名まえがでているものを合わせれば、
七十人前後の門弟があったことになります。
この門弟がまた、それぞれの在所で聖人の教えを
ひろめて、性信房を中心とする横曽根門徒、順信房
を中心とする鹿島門徒、真仏房を中心とする高田
門徒というようにひろがって、念仏の同行は十万を
こえたといわれます。
この人たちは、源空上人の命日にあたる毎月
二十五日、それぞれ寄り合って仏法を聞き、念仏
することによって、門徒としての自覚と誇りを深め、
その思いのうえから、生活上のいろいろな ”たしな
み” を、自主的に申し合わせていったのです。
”仏法の集まりには、酒や賭けごとをつつしみます。
”在所の風習をまもり、他から非難されないように
心がけます”
”商いに、法外な利益をとりません”
などという素朴なものでありますが、それらはみな、
手前勝手で気まぐれな人間同志が定めた規則や、
権力におしつけられた規律ではなく、仏心に
いだかれて、おのずからうまれてきた、自律的な
たしなみの心の表れでないものはありません。
聖人はこのようにして、人びとに教えを伝え、
法をひろめながらも、源空上人の十三回忌にあたる
元仁元年(1224)五十二歳のとき、常陸の稲田で
『教行信証』六巻を執筆されましたが、のちに
真宗教団が成立して、親鸞聖人を開祖と仰ぐように
なってから、この元仁元年を立教開宗の年と定め、
この書が一宗の根本聖典であるところから、『本典』
とも 『本書』ともよぶようになりました。
二十年あまり関東に住んで、真実の教えを
ひろめられた聖人は、六十二、三歳のころ、
家族をつれて京都に帰られました。
長い年月をかけて、せっかく育ててきた多くの
同行や門弟をおいて、帰洛を思い立たれた原因に
ついては、いろいろの説がありますが、
(一) たびたび弾圧される念仏の教えが、正しい
りっぱなものであることを内外に明らかにするため
にも、すでに草稿のできあがっている『教行信証』に
手を加え、完成しなければならないとおもわれたこと、
(二) 急激にふえてきた関東の門弟が、いつしか、
”師”とよび、”聖人”と仰ぐようになったことが、人の
師と仰がれることをきらわれた聖人に、この地を
居づらいものにしたこと
(三)嘉禄の念仏弾圧(1225)によって、東山大谷に
あった源空上人の墓所が破壊されたばかりではなく、
隆寛・幸西などの指導者が流罪となって、しだいに
荒廃しつつあった京都の教団を見捨てておけなかった
ことなどがあげられています。
しかしその京都では、鎌倉幕府によってふたたび
念仏禁止令がだされ、念仏者に対する迫害が
つづいていましたので、表だった教化もできにくく、
住居も五条西洞院や、三条富小路などを転々と
されなければなりませんでした。
そういう状況のなかで聖人は、のちの世の人びと
に、浄土真宗の教えを伝えようと、ひたすら著述
にはげまれました。
『教行信証』の改訂が一段落すると、文字もあまり
わからぬ人びとのために、わかりやすい和文の
書物を書きはじめられたのであります。
宝治二年(1248)七十六歳のときには、
『浄土和讃』『高僧和讃』をつくり、八十三歳のとき
『尊号真像銘文』を、八十五歳になってもなお
『一念他念文意』や『正像末和讃』など、数多くの
書物を執筆しながら、かわるがわる関東から
訪ねてくる門弟に面接し、また念仏生活の
ありかたや、教義をわかりやすく説明した手紙を
出されました。
そのなかで現在のこっているものだけでも
四十、二,三通もあります。
それらをあつめたものが『末灯鈔』とか
『御消息集』と名づけられる書簡集であります。
聖人が京都へ帰られてからのちの、三十年に
ちかい生活のなかで特筆すべきことは、わが子の
善鸞(慈信房)を義絶されねばならなかった事件で
あります。
善鸞は、はじめ聖人が関東にのこしてこられた
門弟たちを教化するために、いわば聖人の代行
として、東国におもむかれたのでありますが、いつ
しか門弟や同行の統率者になろうという望みをいだ
き、”みんなが今まで聞いてきた教えは、父親鸞の
真意ではなく、正しい法義は、ある夜ひそかに自分
ひとりが父から授かった〝 と吹聴しはじめたのです。
いかに善鸞が、師である親鸞聖人の実の子で
あっても、ことは信心と教団にかかわる大切な
問題でありますので、在来の門弟や同行としては
黙って見のがすことはできません。
動揺しはじめた関東の主だった代表者は、聖人に
会って真偽を問いただそうと、はるばる十余カ国の
境を越えて上京してきました。
その人たちに対して聖人は、善鸞のいう密伝の
うわさを否定するとともに、「親鸞におきては、ただ
念仏して弥陀にたすけられまゐらすべしと、よき
ひとの仰せをかぶりて信ずるほかに別の子細なき
なり」(歎異抄)と、ご自身の信念をあきらかに
されました。
一方、善鸞は、その野望がなかなか果たされ
そうもないことを知ると、たまたま鎌倉幕府が、
神祇や諸仏を軽んじたり、人倫の秩序を乱すと
いって、念仏者を取り締っているのにつけこんで、
自分の意志にそわない有力な門弟たちをその
該当者として訴え出たのです。
その結果、性信房や入信房などがとらえられ、
重大な事態におよんだことを知られた聖人は、
〝 親について無実のことをいいふらし、下野や
常陸の念仏者を動揺させ、幕府や六波羅
に訴えた罪は許せない〝
として、ついに建長八年(1256)五月二十九日
をもって、父と子の縁を切ることを善鸞に告げる
とともに、性信房など主だった門弟にもこのことを
通告せられました。
その義絶をいいわたされた手紙が、現に伝え
られておりますが、そのなかの、「今は親という
ことあるべからず、子と思うこと思いきりたり、
三宝神明に申しきり終りぬ。悲しきことなり」
という一句にいたっては、じつに血涙のしたたる
ような文字であります。
正しい法をまもりぬくことと、断ちがたい親子の
情との間に立って苦悶しながら、義絶までせね
ばならなかった八十四歳の聖人は、まことに
断腸の思いであったことでしょう。
このできごとがおこった当初、すなわちおそくとも
建長六年(1254)ごろ恵信尼さまは、聖人の身の
まわりの世話を末娘の覚信尼にたのんで、生まれ
故郷である越後の米増に帰られました。
それは、三善家から相続した土地や財産を管理
しながら、こどもや、親に先立たれた孫たちの
生活を世話するためであったと思われます。
「・・・・こちらには、親のない小黒の女房の
女の子と男の子がおります上、益方の子ども
も、ここばかりにおりますので、私はなんとなく
母親になったような気がいたします」
「としこそ恐ろしいほどかさねましたけれども、
咳もでませんし、つばをはくこともございません。
腰や膝をさすってもらうことも、今日まではござい
ません。まるで犬のように動きまわっております
・・・・・」
お手紙のはしばしでもうかがえるように、越後
での恵信尼さまの生活は、多くの家庭と、七、八
人もの傭人をかかえ、しかも凶作によって作物を
損じたり、災害で土地を失い、物が不足したりして、
老いの身には重すぎるほどの、目まぐるしい
労苦の日々がつづきました。
このような一家の経済的な事情があったにせよ、
敬慕してやまない夫と、はるかへだてて暮らさねば
ならなかった恵信尼さまの、つらく淋しい心情は、
察するにあまりあるものがあります。
そして、そのまま夫の臨終にも死後にも、京都へ
帰られる機会はついにありませんでした。
善鸞の背信、動揺する関東の教団、幕府の
念仏者への弾圧と、ひきつづく事件にもめげる
ことなく、それこそ〝身を粉にし、骨をくだく〝
思いで、精力的に著述をつづけていかれた
聖人も、恵信尼さまが越後に下られてから
七,八年のちの弘長二年(1262)十一月
二十八日(太陽暦では翌年一月十六日)弟の
尋有僧都の善法院で、念仏のうちに静かに
息をひきとられました。
そのときのようすについて、『伝絵』には、
つぎのようにのべてあります。
「仲冬下旬の候より、いささか不例の
気まします。それよりこのかた、口に世事
をまじへず、ただ仏恩のふかきことをのぶ。
声に余言をあらはさず、もっぱら称名たゆる
ことなし。しこうしておなじき第八日午時、
頭北面西右脇に臥したまひて、つひに
念仏の息たえをはりぬ」
臨終の枕べには末娘の覚信尼と、越後
から上京した三男の益方入道、門弟では
高田の顕智房や、遠江池田の専信房などが
見まもっておりました。
おもえば九十年、一世紀にちかい聖人の
ご一生は、じつに〝いばらの道〝 で
ありました。
しかし、「大悲の願船に乗じて光明の広海に
浮かびぬれば、至徳の風静かに、衆禍の波
転ず」と 『教行信証』にのべられているように、
弥陀の本願を信じ、念仏に生かされることに
よって、この〝いばらの道〝がそのまま、
真実への白道だったのであります。
二十九日に東山の延仁寺で火葬、三十日
に鳥辺野の北の大谷に納骨して、墓標を
建てた喪主の覚信尼さまは、ただちに越後の
母にこれらのことを報らせられました。
「昨年十二月一日付のお手紙は、同月
二十日過ぎに、確かに拝見しました。
なにはおいても、殿がお浄土にご往生遊ばされ
ましたことは間違いなく、あらためて申すまでも
ございません」(恵信尼消息)
雪深い越後で、悲報を手にした恵信尼さまは、
夫と別れた悲しみをおさえて、このような返事を
だしておられます。
そこにはひとすじに生きぬいた、夫への深い
信頼と思慕とその精神を、子や孫に受け継いで
もらいたい、母の大きな願いがあったからで
ありましょう。
文永五年八十七歳のとき、〝お念仏を大切に
相続して、ともにお浄土で会いましょう〝 という
手紙を書いておられたことも、そうした願いの
あらわれのように思われます。
この手紙を最後にして恵信尼さまはほどなく、
聖人の待たれる浄土に帰ってゆかれました。
聖人がなくなられてから、いままでその
教えをあおいでいた、関東や京都の人びとが、
徳を慕って墓所にあゆみをはこび、参詣する
人の数は年ごとにふえていきました。
そうした同朋同行の便宜を考え、高田の
顕智房や門徒の協力によって、墓所を改め
るとともに、六角のお堂を建てて聖人の影像
を安置し、覚信尼さまとその子孫が大谷
留守職として、お堂をまもることになりました。
しかし、敷地や建物は門弟たちの共有にして、
みんなの力で維持することにしたのです。
これが大谷本廟とよばれるものであり、聖人の
教えを仰ぐ人びとの〝心のふるさと〝 として、
次第に発展して本願寺教団の基になりました。
聖人を見真大師とよぶのは、一生をかけて、
◎真実に生きる道を◎見出すために、ひとすじに
生きぬかれた聖人の全人格と、幾千万の人びと
に、まことの救いの光りを恵まれた功績をたたえて、
明治天皇からおくられたものであり、わたくしたちが
報恩のあゆみをはこんで御影堂にぬかずくとき、
正面頭上にかかげられている巨大な額がそれで
あります。
まことに親鸞聖人こそ、見真の聖者でありました。
聖人がなくなられたあと、聖人のご子息や
門弟たちの努力によって、教えは次第に
ひろまってゆきます。
信者の合議によって運営される講組織ができ、
寄りあって聞法・談合するための道場ができ、
懇志をだしあって教団を維持してきました。
聖人の曾孫にあたる覚如上人は、『本願寺
聖人親鸞伝絵』などをあらわし、教えが正しく
伝わることに努力されました。
ことに、本願寺第八代蓮如上人は、応仁の
乱前後の戦国乱世といわれる時代に、戦乱に
あけくれ動揺する人びとに親しく接して、教えを
わかりやすく説き、それを簡明な文書に
したためて各地の門徒を教化されました。
それらの文書は、のちにまとめられて『ご文章』
とよばれ、いまでも日々拝読されております。
また、親鸞聖人の著述のなかから、『正信偈』や
『和讃』を刊行され、朝夕のお勤めに拝読する
ならわしとされたのも、蓮如上人であります。
このような熱心な活動により、真宗は爆発的に
ひろまり、それにつれて門徒の組織をもとに、近畿、
北陸、東海地方などに、一揆が続発しました。
これがいわゆる一向一揆ですが、ことにはげし
かった加賀(石川県)では、守護大名の富樫氏を
倒して、門徒の合議による自治を一〇〇年間も
続け、近畿の地方にも勢力をふるいました。
しかし反面では、こうした発展にともなって、
圧迫も加わります。
まず比叡山の僧徒が東山にあった本願寺を
破壊したので、蓮如上人は近江(滋賀県)から、
遠く加賀(石川県)や越前(福井県)に移ら
れねばなりませんでした。
しかしそのために、かえってこの地方一帯に、
浄土真宗がひろまることになったのです。
上人はその後、京都の山科に本願寺を
再建され、その教えは庶民の間に浸透して
ゆくのであります。
しかし各地の領主のなかには、真宗を
禁制するものもあり、幾多の苦難と信徒の
殉教のなかに、念仏の声は全国にひろ
まっていくのであります。
蓮如上人の没後、山科の本願寺は
ふたたび戦乱にまきこまれて焼かれたため、
淀川河口の要地である石山(いまの大阪城
付近)に移りました。
そこでもまた、十一代顕如上人の時代に、
天下統一をめざす織田信長は、その寺地の
あけ渡しを要求してきました。
本願寺はそれを拒絶したため、信長はこれを
機会に真宗の巨大な力を一挙につぶそうと
考え、石山本願寺を包囲攻撃したので、教団
は危機に立ちました。
この一大法難を聞いて多くの僧侶や門徒が、
文字どおり命がけで全国から馳せ参じました。
その人たちのなかには、刀や弓の使い方さえ
知らぬものも少なくなかったのですが、ひとつの
信にかたく結ばれて、教団を守りぬこうと戦い
ましたので、さすがの信長の軍勢も、十一年と
いう長い年月をかけて攻めながら、ついに
本願寺を破ることができませんでした。
信長と和睦ののち本願寺は、鷺森(和歌山市)
貝塚(大阪市)天満(大阪府)などに移りましたが、
豊臣秀吉が土地を寄進したので、ふたたび
京都に帰ることになりました。
それが堀川六条にある現在の場所であります。
顕如上人の没後、大谷派本願寺が
別立されます。
信長との石山合戦が、正親町天皇の仲裁
により和議が成立したさい、門主顕如上人の
長男教如上人は、和睦に反対してあくまで
信長と戦うことを主張し、隠退の身と
なられました。
父の顕如上人がなくなられたあと、教如上人
は徳川家康より土地の寄進を受け、烏丸七条
に移られたのです。
それはわが本願寺がいまの地に移ってから、
約十年後のことであり、これによって大谷派
本願寺が別立することになります。
全国の宗勢は二分されましたが、その教えに
違いがあったわけではありません。
江戸時代に入ると、教団は充実期に入ります。
幕府は、一面ではキリシタン禁制、鎖国政策
のため、仏教を保護しましたが、他面でその
活動に厳重な制約を加えました。
宗学の研究が盛んになるとともに、学僧たちが
熱心に教えを説いたため、妙好人とよばれる
篤信の信者が育てられました。
しかし、寺院の本末関係が整備され、寺檀
関係が固定化するとともに、教団の体制は
封建化され、それまでのような活動力を
失ったこともいなめません。
明治になると、維新政府は、江戸時代の
保護政策とはうってかわった、はげしい排仏
政策(いわゆる廃仏毀釈)をとりました。
本願寺は、仏教諸宗の先頭に立って奔走し、
信教の自由を守りぬきました。
また、有能な青年僧侶を欧米に派遣して
見聞をひろめ新知識を吸収して帰らせたり、
公選による宗議会を開設してひろく意見を
宗政にとり入れるなどしました。
そして、新しくひらけた北海道や、海外
移住者とともにアジア、アメリカの各地に
開拓伝道を行い、学校を建て、対象別の
教化団体を結成し、刑務所の教誨、
職場の布教など、広範囲の活動を
展開してきたのです。
聖人によってひらかれた本願念仏の
み教えは、内には、わたくしの心により深く、
外にむかってはよりひろく、生きるよろこびを
よびさましてゆくことでしょう。
| どうぞ一言(伝言板) | ホームページトップへ |