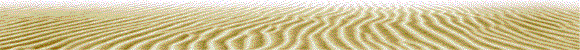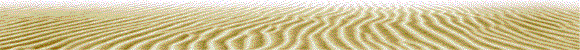
これが基本 ③ (3/5)
浄土真宗・必携 13ページ~ (第27版)
釈 尊 と そ の 教 え
これあるゆえにかれあり、これ起こるゆえにかれ起こる。
これなきゆえにかれなく、これ滅するゆえにかれ滅す。
(雑阿含経)
釈 尊
誕 生
ところは北インド、はるかにヒマラヤの銀嶺を
のぞむ高原に、釈迦族と呼ばれる気品と勇気を
そなえた種族が、カピラ城(カピラバッツ)を中心に
小さな国をつくっていました。
城主は浄飯王(スッドーダナ)といいましたが、その妃
マーヤーは、出産のために里帰りの途上にありました。
春のおそい北インドで、一時に咲いたさまざまな花が、
野山を色どっていましたが、途中にあるルンビニーの
花園のうつくしさは、人びとの目をうばうほどでありました。
ときは紀元前五世紀のなかば、四月八日のことです。
マーヤー夫人の一行は、しばらくこの庭園で
休息することになりました。
夫人がやおら立って、無憂華の一枝を手にしようと
したとき、すばらしい王子が誕生されたのです。
その名は、シッダッタ(悉達多)とつけられました。
経典の伝えるところによれば、シッダッタは生れると
すぐ七歩あるいて天と地を指さし、「天上天下、
唯我為尊、三界は皆苦なり、われまさにこれを
安んずべし」と高らかに叫ばれ、天は感動して
甘露の雨を降らしたといいます。
だれも、自分の生れたときのことを記憶して
いる人はいません。
ものごころついてから、それをいい聞かせるのは
母親ですが、マーヤー夫人は、産後七日目になくなり、
シッダッタは、母の口から自分の出生のときの
ようすを聞くことはできませんでした。
誕生についてのさまざまな奇瑞は、あるいはのちの
仏伝編集のとき創作されたものかもしれませんが、
それにしてもこの偉大な聖者の誕生を語るには、
まことにふさわしい物語といえましょう。
六歩は、迷いの六道をあらわし、七歩あゆまれたとは、
すでに迷いの世界を過ぎ、人びとを救う仏の出現で
あったことを象徴しているのであります。
その誕生日である四月八日は、花まつりとして
祝われております。
出 家
王子シッダッタは、学問にも武芸にも早くから
抜群の力量をあらわし、父王や国民の希望を一身に
になっていました。
少年のころ、小鳥についばまれた虫が、もがき苦しむ
さまをみられ、さらにその小鳥がたかにおそわれて
餌になるという、生きているものが相互に殺しあい
食いあうすがたをみて、ふかくもの思いに沈まれた
といいます。
こうした多感なシッダッタ太子の心をひきたたせようと、
父の浄飯王は、はなやかな王宮の生活を準備し、
成人すると美しいヤソーダラーを妃にむかえました。
しかし太子は、外見はなやかな生活のなかで、
かえってもの思いに沈みがちな日をおくられました。
あるとき太子は、城外の視察を思いたちカピラ城の
東門からでたとき、ひとりのやせおとろえた老人を
みて、「自分もこのように老いてゆかねばならないのか」
と、心を暗くしました。
また南の門からでたとき病に苦しむ人にであい、
西の門をでたときは悲しい葬列にゆきあい,人生が
常なく、苦しみであることをしりました。
最後に北の門からでたとき、そこで一人の修行者に
あいました。
そのけだかいすがたにシッダッタ太子の心はつよく
うたれ、出家の決意を固められたと伝えられています。
やがてヤソーダラー妃との間に王子が生れととき、
「わが求道のための妨げ(ラーフ)ができた」と
つぶやかれましたので、子はラーフラ(羅ご羅)と
名づけられました。
しかし道を求めようとする思いはいよいよつのり、
二十九歳のとき、王子の地位も家族への愛着も
ふりきって、ついに修行者たちの仲間にはいられた
のであります。
成 道
いまは王服をすてて一修行者となった
シッダッタは、一路南にくだって、マガダ王国の
都である王舎城(ラージャガハ)の森にゆかれ
ました。
広漠としてつづく平坦な平原のなかで、ここだけは
山脈が走り、古い火口原に位置する王舎城には、
新興国の活気があふれており、これにひかれて、
インドの各地から自由な思想家たちがあつまって
おりました。
シッダッタは、その教師たちを歴訪しては教えを
請いましたが、どの教説も満足できるものでない
ことがわかったので、ひとりで真理を求めようと、
ウルべーラー村の苦行林におもむき、徹底した苦行に
入りました。
ときには一粒の米で一日をすごし、あるいはまったく
食を断たれることもありました。
一時は倒れて意識もなく、死亡の誤報が父王のもとに
とどいたことさえありました。
苦行をつづけること六年、身も心も衰えるばかりで、
これではとてもさとりに達することはできないと知り、
山を下って尼連禅河(ネーランジャラー河)でその身を
清め、村長の娘スジャーターの供養した乳がゆで
体力を回復されました。
あらたな勇気をふるいおこしたシッダッタは、
ガヤ市の郊外の、とある大きな菩提樹の下に座し、
さとりをひらくまでは決してこの座より立つまいと誓い、
瞑想に入られたのです。
それを見てそれまで苦行をともにした五人の修行者は、
シッダッタは堕落したものと思い、みすてて立ち去って
しまいました。
シッダッタの成道のときが近づくと、魔王があらわれ、
空中から炎をあげた剣をもって脅迫し、あるいはまた、
なまめかしい美女となって誘惑し、成道を妨げようと
しました。
けれども魔王のすがたであらわされた外からの脅威にも、
内からの煩悩にもうちかって、十二月八日、あかつきの
明星がひときわ強くまたたくとき、老・病・死の苦悩の
根源である無明をうち破って、真実の智慧をえられた
のでした
このとき三十五歳でしたが、それいらいシッダッタは、
釈迦牟尼世尊(釈迦族の聖者の意、略して世尊という)とも、
仏陀(覚られたものの意)とも呼ばれるようになりました。
「人は、生れによって聖者であるのではない。
その行為によって聖者となるのである」とのちに
釈尊はのべておられます。
いまわたくしたちがこのシッダッタを釈迦牟尼世尊と
仰ぐのは、そのさとりの内容と行為の尊さによる
からであります。
伝 道
釈尊は成道ののちも、しばらく菩提樹のもとに
すわって、さとりのよろこびをかみしめておられました。
たったひとつの原理を発見しても、そのよろこびに
躍りあがって、はだかで街を走った学者が西洋には
あったといいます。
まして釈尊の場合、万法があきらかになったのですから、
そのよろこびはいかばかりか大きかったことでしょう。
もともと釈尊は、慈愛と威厳にみちた容姿端麗な方で
ありましたが、このよろこびにあふれた尊いすがたを
後世の芸術家たちは、あるいは光明であらわし、また
三十二相などの仏像彫刻の類型によってあらわす
ようになったのであります。
やがて釈尊は、このよろこびを人びとに伝えようと
座を立たれ、まずその対象として、これまで苦楽を
ともにしてきた五人の修行者をえらばれました。
かれらはガヤから二百キロ以上もはなれたベナレス
郊外の鹿野苑(ミガダーヤ)で、あい変わらず苦行を
つづけておりました。
五人は釈尊の姿をみて 「道をすてたもののことばは、
決して聞くまい」と申しあわせました。
けれども、自信にみちた釈尊の説法にしだいに
耳をかたむけ、ついにその最初の弟子となりました。
この歴史的な説法を、初転法輪といいます。
ここにはじめて仏・法・僧の三宝がそろったのです。
ここで「僧」とは、僧伽(サンガ)の略で、釈尊を
中心とした弟子たちの集団をいうのです。
釈尊は、僧伽にインドの社会に根づよく力をもって
いた身分の階級制度をもちこまぬよう、とくに気を
くばられましたので、すべての人は平等に和合して
ゆきました。
釈尊は、ときと相手に応じて真実の法をたくみに
説法しながら伝道の旅をつづけられました。
あるときはマガタ国の王舎城に、あるいは舎衛国の
祇園精舎に、またあるときは貧しい信者の家を
おとずれて、教化をつづけてゆかれたので、釈尊を
心の師と仰ぐものは、あらゆる階層におよび、国境を
こえた教団ができあがっていきました。
偉大な先覚者や天才は、概して世に受け入れられず
悲劇の生涯を送ることが多いのですが、釈尊の
場合は例外でした。
ときには敵となった人もありましたが、その憎しみも、
釈尊の円満な人柄のまえに自然にやわらぎ、
いつしか帰依者に変わっていくのが常でした。
なかでも最大の事件は、釈尊の従弟にあたる提婆達多
(デーバダッタ)が、釈尊にかわって教団の主導権を
にぎろうとして反逆したことです。提婆は、マガダ国の
阿闍世太子(アジャータサッツ)をそそのかし、その父
頻婆娑羅王(ビンビサーラ)を殺させ、母の韋提希夫人
(ベーデーヒー)を幽閉し、国の実権をにぎらせて,
その力をかりて精神界の王者となろうとしたのです。
しかしその企みも失敗し、かえってそれが機縁となって
釈尊が『観無量寿経』を説かれ、尊い念仏の教えが世に
現れるもととなりました。
釈尊の円満な人柄のまえには人びとの憎しみも自然に
やわらぎ、いつしか帰依者に変わって行くのが常でした。
こうして釈尊は、生涯たゆまず法輪を転じていかれた
のです。
涅 槃
八十歳の高齢となられても釈尊は、なおもたゆまず
王舎城よりベーサーリを経由して伝道の旅をつづけて
おられました。
この旅は中途で終わりました。
めざすところは舎衛城の祇園精舎であったでしょうか、
あるいは故郷のカピラ城でもあったでしょうか。
釈尊はこの旅の途中で病気になられました。
病が回復にむかったとき、つねにおそばに仕えていた
アーナンダは、勇気をだしておたずねしました。
「世尊よ、一時はこのままおかくれになるのではないかと、
わたくしは心痛いたしました。
しかしまだ、弟子たちの中から教団の統率者を選び、
かれに秘伝を託されることもないので、おかくれになる
ことはあるまいと安心していました」
このアーナンダのことばをたしなめて、釈尊は
いわれました。
「アーナンダよ、いまさらわたくしになにを
期待するというのか。
わたくしはすでに、ことごとく真理の法を説きあかして
きたではないか。
アーナンダよ、如来の教法には隠しておかねばならぬ
秘伝というものはないのである」
そして釈尊はつぎのように示されたのであります。
「自らをともしびとし、自らをよりどころとして、他をより
どころとしてはならない。
法をともしびとし、法をよりどころとして、他をよりどころと
してはならない」
その後、旅をつづけられた釈尊は、その途上で
ふたたび病にかかられました。
この偉大な教主、釈尊といえでも、諸行無常の法を
のがれることはできません。
やがてクシナーラの沙羅双樹の下に横になり、最後の
説法ののち、静かに息を引きとられました。
「弟子たちよ、諸行は無常である。怠りなくつとめねば
ならない」
これが最後のおことばでした。
釈 尊 の 教 え
縁 起
釈尊が,菩提樹の下でさとりに到達されるまでの
内面の過程は、うかがい知るよしもありませんが、
深い瞑想ののち、縁起の法をさとられました。
縁起の法とは 「 あらゆるものが相互にあい縁り
あいまって存在すること 」 をいいます。
「わたくしが世にでるとでないとにかかわらず、この
縁起の法は常住である」と、釈尊ご自身がいって
おられるように、これはだれもが納得せずにはいられ
ない基本的な法則です。
仏教の教理の根本を流れるのが、この縁起の思想
ですから、仏教ではいかなる場合でも奇蹟を
みとめません。
当面した問題を解明するのには、かならずすじみちを
たててその因果をあきらかにしていくのです。
「これあるゆえにかれあり。これ起こるゆえにかれ
起こる。・・・・これなきゆえにかれなく、これ滅する
ゆえにかれ滅す・・・・・・」
こう繰りかえしながら釈尊は、人間の背負っている
苦悩の原因をたどり、ついに「無明」こそそのもとで
あることをさとり、その解決の道を自問しあきらかに
していかれました。
「あきらかにする」ことを「諦」という字であらわしますが、
それはしばしば誤解されているように、いわゆる
仕方がないとアキラメルのではなく、あきらかに
見きわめていくことなのです。
成道の直後、鹿野苑での最初の説法は、中道・
四諦・八正道の教えであったと伝えられております。
まず釈尊は、快楽を追い求めることの愚をたしなめ、
また反対に、極端な苦行の無益であることをさとし、
両極端にとらわれることを排して正しく道を修めて
ゆくよう、中道をとかれました。
つづいて説かれた苦・集・滅・道の四つの諦とは、
つぎのような教えであります。
人生の実相 - 苦諦 -
釈尊は、まずありのままに人生をみることから
出発されました。
そうしてみれば、うわべははなやかにみえても、
人生は苦そのものであることが実感されてきます。
生・老・病・死の四苦にくわえて、愛するものと
別れねばならぬ苦、憎いものにあわねばならぬ苦、
ほしいものが得られぬ苦、生命力(五蘊)が盛んで
あるが故に起こる苦、の八苦は、今日でもなお解決
することのできない永遠の苦として、わたくしたちを
悩ませています。
この苦諦は、人生をみる、ある一つの見方ではなく、
いかに目をおおってもかくすことのできない、人生の
実相そのものであります。
なぜなら、たとえよろこびのひとときをもっても
それは永続せず、希望的な見とおしをたてて努力
しても結局、思うにまかせぬのが人生だからです。
苦悩の原因 - 集諦 -
病気をなおすには、病源を正しく知って適切な
手あてをせねばならないように、苦悩を解決する
には、まずその原因を知らねばなりません。
集とは招き集める意味ですから、集諦とは、苦を
まねき集める原因があるということをいうので
あります。
その原因とは、わたくしたちの煩悩のことで
あります。
煩悩は、あの除夜の鐘の数にあらわされるように
多数ありますが、なかでもつよくわたくしの心を
煩わすのは「むさぼり・怒り・愚かさ」の三つで
あります。
貧欲のために、どれだけ多くの人がみずから
苦しむだけでなく、家庭や他人を泣かせている
ことでしょう。
怒りは、どんなに社会を住みにくいものにして
いることでしょう。
正しい道理を知らぬ愚かさのために、どれだけ
無益なことに精力をついやしてきたことでしょうか。
この三つの煩悩の源をさらにさぐっていけば、
ついに我執につきあたります。
つねに自己を中心にして物事を判断し、何でも
自分の思うとおりになることを望んでやまない、
はげしい自我拡大の欲求が我執であります。
こうして釈尊は、苦悩の病源をあきらかにされ
ました。
苦悩を超えよ - 滅諦 -
こうして苦の原因がわかったからには、
我執の心をなくして、なにものにもわずらわされない
平静で自由なさとりの境地=涅槃を求めねば
なりません。
涅槃とは、煩悩の火が吹き消された状態をいい、
滅度と訳されます。
これが三番目の滅諦であります。
仏教では、根本的な原理として、諸行無常、
諸法無我、涅槃寂静の、三つの旗じるしをかかげ、
これを三法印といいます。
諸行無常とは、「すべてのものはうつりかわる」と
いうことであり、
諸法無我とは、「すべてのものには、不変の実体が
ない」ということであり、
最後の涅槃寂静が、ここにいう絶対安楽のさとりの
境地=滅度にほかなリません。
苦悩を超える道 - 道諦 -
苦悩をいかにして超えるか、これが仏教の根本の
課題であり、その方法として釈尊は、つぎの八正道を
説かれました。
一、正 見 (正しい智慧)
二、正思惟 (正しい思索)
三、正 語 (正しいことば)
四、正 業 (正しい行為)
五、正 命 (清らかな生活)
六、正精進 (正しい努力)
七、正念 (正しい思いをもちつづけること)
八、正定(心の安定をたもつこと)
このほか、仏教の実践行として戒、定、慧の
三学や、布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧の
六波羅蜜が説かれ、仏道修行の規範とされて
きたのであります。
教 え の 流 れ
経典の編纂 - 結集 -
釈尊は、その生涯に数多くの人びとに法を説
かれました。
しかし、その説法は、文字にとどめられるという
ことはありませんでした。
釈尊の説法は、対機説法とか応病与薬などと
いわれるように、聞く人に応じて説かれたため、
聞いた人びとの法に対する理解も異なっていた
ようであります。
そうしたなかには、釈尊の存在をうとましく思う
ものもあったようです。
「この人がなくなって、やっとわたくしは自由に
なった」とつぶやいた仏弟子がありました。
場面はこともあろうに、あの釈尊がなくなられ、
人もけものも、昆虫から草木のたぐいまで、偉大な
聖者との別離の悲しみに、うちふるえている
さなかでした。
しかし、この不心得なことばが、さいわいにもすぐれた
仏弟子大伽葉(マハーカッサバ)の耳に入りました。
大伽葉は「われなきあとは、法をよりどころとして
生きよ・・・・」といわれた釈尊のおことばをかみしめ
ながら、その「法」を聞きながら内心反発していた
ものがすでにあることをしっておどろきました。
大伽葉はかねて、釈尊が生涯にのこされた教えを、
整理し再確認しておかねばならぬと考えていた
でしょうが、ここにいたって仏弟子たちにそのことを
提案しました。
こうして、経典編纂の大会議=結集がひらかれた
のです。
結集の後、仏弟子たちは、国の内外にむかい、
勇躍して教えをひろめていったのであります。
その大事業の物心両面のお世話を、みずから請うて
引きうけた人こそ、かつては父の王を殺し母を幽閉して
王位をうばい、釈尊にまで危害をくわえて、人びとから
おそれられた悪逆の王、阿闍世その人でありました。
仏典編纂はその後何回も行われ、文字に記録され、
今日みる人類の貴重な宝である大蔵経(一切経)と
なりました。
大乗仏教と浄土門の課題
インドからひろく国外へ伝えられた仏教は、主として
二つの方向をたどってゆきました。
ひとつは、スリランカ(セイロン)、ビルマ、タイなどの
南方仏教であり、もうひとつは、パミール高原を北に
こえて、いわゆる西域地方から中国へと伝わった
北方仏教であります。
この流れのなかに、中国から日本へ伝わった
大乗仏教がありました。
釈尊の定められた戒律を型どおり守って、みずからの
智慧をみがいていこうという小乗的な修行法に
あきたらず、釈尊の真意をくんで、よりひろい立場から、
一切の衆生がともに解脱をえようとするのが大乗仏教
です。
大乗仏教はおもに温帯諸国にひろまり、たくさんの
人びとの、文字どおり命がけの伝道と求法によって
中国大陸にもたらされ、経典も漢訳されました。
そうして六世紀には、ついに日本にまで伝え
られたのです。
その間に、教えの流れは幅をひろげ深さをまして、
人びとの心にしみとおってゆきましたが、やがて
聖道門と浄土門にわかれてゆきました。
聖道門は、「一切の衆生はことごとく仏性をもつ」
という立場から、自分のもっている仏性をみがきだし、
この世でさとりをひらいて仏になろうとするもので、
それにはすさまじい身心の努力を必要とするので、
自力聖道門とも、難行道ともいわれます。
しかし、いっぽうでは、時代は釈尊をへだたること
すでに遠く、仏性をもつといわれてもこの自分を深く
みつめてゆけば、みがけば光るどころか、皮をめくる
ほどみにくい自己の本性に絶望するほかありません。
その、もっとも身近な事実から出発して、そういう
わたくしをこそ救わずにはおかぬとはたらきかける、
阿弥陀如来の本願力に救いとられ浄土に生まれて
仏になるのが、他力浄土門であり、易行道とも
いわれます。
聖道門、浄土門と道はちがっていても、迷いをはなれて
仏になることを目ざす点においては、いずれもちがいは
ありません。
ことに浄土門は、わたくしたちのような愚かなものも
悪人も、如来の本願力によって平等に救われていく
点において、すべての人類に門戸をひらいて釈尊の
真意を伝えてゆきました。
その大乗仏教 - 浄土門という、仏教の幅と深さの
展開の頂点に立たれたのが、浄土真宗の宗祖、
親鸞聖人であります。
七 高 僧
教主釈尊からこのわたくしにまで教えがとどくには、
二千五百年もの時間と、幾千キロの距離をとおして、
無数の高僧や先覚の信者たちの努力が、つみ重ね
られてきました。
そういう先輩たちのなかから、親鸞聖人はとくに七人の
高僧をえらんで、教えの師と仰いでゆかれました。
「正信偈」や「高僧和讃」にうたわれている七高僧が
それで、インドの龍樹大士、天親菩薩、中国の曇鸞大師、
道綽禅師、善導大師、日本の源信和尚、源空上人です。
この七高僧はいずれも、大乗仏教・浄土門の教えを
正しく伝え、多くの著書をのこされました。
なかでも七番目の源空上人は、別の名を法然上人とも
いいますが、親鸞聖人は直接にこの源空上人によって、
念仏にみちびかれるのです。
この源空 -ー親鸞の出あいは、のちにくわしくの
べますが、日本史上におけるもっともすばらしい人間の
出あいであったといえましょう。
聖徳太子と日本仏教
日本に仏教を定着させた第一の功労者は、
聖徳太子であります。
親鸞聖人は太子を「和国の教主」という呼び名で
たたえておられますが、教主とは釈尊のことですから
「日本のお釈迦さま」という意味の、最大級の敬称です。
聖徳太子は、内政、外交、文化と、多方面にわたって
功績をのこされた日本文化の父ですが、そうした大きな
業績は、つねに仏教精神の基盤の上に築かれていき
ました。
太子は、重要な政治問題の判断を迫られたときとか、
裁判にのぞむまえには、経典をひもといて瞑想され、
仏心をもってこれらのことにあたられたと伝えられて
おります。
当時、一般の仏教の理解のしかたは、仏を異国の
珍しい神としてまつるか、あるいは凶作や疫病を
とりのぞく呪術としてうけとられるような状態でした。
そのなかで、教えによる自覚をとおして生きる姿勢を
きめるという、太子の仏教に対する理解はさすがに
すばらしいものでした。
奈良時代になると、聖武天皇によって建てられた
東大寺や、藤原氏の氏寺である興福寺などを
中心として、僧侶が養成され、仏教の学問が
はじめられました。
けれどもこの時代の大寺は都市に建てられ、国家や
貴族の保護になれて堕落のきざしがみえてきたので、
京都へ都が移されたのを機会に、最澄と空海は、
山の上に新しい修行の道場をひらきました。
なかでも最澄は、平安京を見おろす比叡山に延暦寺
を建て、「一隅を照らす」人材の養成をはかりました。
いらい比叡山は、仏道修行の根本道場として、多くの
人材を育ててきましたが、なんといってもけわしい難行
の道であり、限られた一部の人しかその教えに浴する
ことはできませんでした。
さきにのべた聖徳太子は、すぐれた仏教の理解者で
ありましたが、その後の為政者はその精神を生かすこと
ができず、また国家の力で維持された奈良、平安の
仏教は、その理想はともかく現実には、庶民が入門
するのはきわめてむつかしい状態でありました。
仏教が日本に定着し、真に人びとの心のともしびと
なるのは、鎌倉時代の新仏教をまたねばなりません
でした。
動乱の平安末期から鎌倉時代にかけて、源空、
親鸞、道元、日蓮などの諸師は、いずれも比叡山に
学びながら相ついで山をくだり、庶民のなかに仏教を
伝えてゆくのですが、なかでも源空上人は、それまで
他の諸宗で修行の付属的な地位しか与えられていな
かった念仏を、浄土への行法としてえらびとって浄土門
の独立を果されました。
そして親鸞聖人は、念仏の本義は真実の信心に
きわまるのであり、浄土真宗が真実の教えであること
をあきらかにして、すべての人びとに仏教の門戸を
ひらかれました。
都市から山に上った道場が、ふたたび人間の巷に
おりてきたわけです。
国家権力から独立したこの鎌倉時代の新しい仏教は、
いずれも強い伝道性をもち、日本のすみずみから、
後にはさらに海外へもひろまっていくことになるので
あります。
「釈尊とその教え」終り
(これが基本③の終り)
「これが基本①」のトップへ
浄土三部経表紙へ
南無阿弥陀仏とは (これが基本 ② )
親鸞聖人の生涯と教団の歴史 (これが基本 ④ )
「浄土真宗の作法と行事」 (知らなかった ② )
内容を転載する場合は、本願寺出版社の了解が必要です。
| 私も一言(伝言板) | トップ |
掲載者 妙念寺 藤本 誠