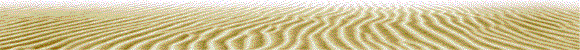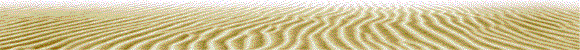
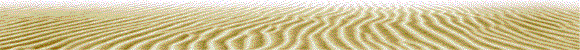
一一のはなのなかよりは
三十六百千億の
光明てらしてほがらかに
いたらぬところはさらになし
(浄土和讃)
|
|
○ 如来さまへのごあいさつは、合掌に
はじまり合掌でおわります。
○ 礼拝は祈ることではなく、仏徳への感謝と
讃嘆ですから、「お礼をする」ともいいます。
力まず自然な気持ちで、しかも怠りなく
つづけましょう。
○ 念珠は、仏前に礼拝するときにかける
法具です。
○ 念珠は大切な法具ですから、ていねいに
取り扱ってください。
投げたり、畳の上に直接おいたりしないように
したいものです。
○ 家族のひとりひとりが、かならず念珠を
もちましょう。
○ 念珠は自分にふさわしいものにしましょう。
服装やほかの持ちものにくらべて、あまり
粗末でない品をえらぶことが大切です。
○ 念珠のもちかた
合掌のときは両手にかけて、ふさを下に
たらし、親ゆびでかるくおさえます。
合掌しないときは、左手にもちます。
○ 両手を胸の前に合わせて、
指をそろえて約四十五度上方に
のばし、念珠をかけて親ゆびでかるく
おさえます。
○ 肩、ひじをはらず自然に、目は御本尊の
方にむけ、そして静かに念仏します。
念仏は、「南無阿弥陀仏」と数回
となえます。
○ 礼拝は、合掌したまま上体を約四十五度
かたむけてお礼をし、上体をおこしてから
合掌をときます。
○ 立って行う場合、焼香卓の二,三歩てまえで
御本尊に一礼し、
進んで香を右手でつまんで、
いただかずに香炉のなかに一回入れ、
合掌・念仏・礼拝し、
二、三歩さがり
一礼して退出します。
○ 焼香のとき、導師の前を通るときは
一礼します。
○ すわって行う場合もおおむね右に
準じます。
○ 焼香のときの注意
・ 香をたくまえには合掌しない
・ 香を、おしいただかない
・ 香をたくのは、一回でよい
・ 焼香のとき、りんをたたかない。
○ 仏壇とは、迷える私たちをお救いくださる
阿弥陀如来さまをご安置するために置くもので、
最も尊厳な場所であり、家庭生活の
中心となるものです。
○ うちには亡くなった人がいないから、仏壇は
まだいらないと考える人がいますが、
とんでもないまちがいです。
仏壇は、死者や位牌のためのものではありません。
日々を生きる力のもとである如来さまのお慈悲に、
私があう場所なのです。
○ 仏前に家族そろっておまいりして、謙虚に如来さまの
大悲を仰ぐ家庭こそ、本当に幸せな家庭と
いえるでしょう。
○ 仏壇はそまつにならないで、しかも
みんなに親しみやすいところに
おきましょう。
○ 仏壇をもとめることについて、さまざまな
迷信や誤解があるようですが、そんな
ことにとらわれないようにしましょう。
新たに仏壇をもとめることは、家庭に
心のともしびがともるめでたいことです。
そのときにはご住職に相談して、入仏式
(入仏法要)をおつとめいたしましょう。
○ 新夫婦が別な場所で世帯を持つ場合は
仏壇を、それができぬ場合は御本尊と
「浄土真宗聖典」およびこの「浄土真宗必携」
だけでももたせ、その地のお寺や別院で
教えを聞くよう、すすめたいものです。
○ 浄土真宗のご本尊は阿弥陀如来です。
この阿弥陀如来を、親鸞聖人は、
南無阿弥陀仏(六字名号)とも
南無不可思議光如来(九字名号)とも
帰命尽十方無碍光如来(十字名号)とも
示されました。
○ 掛け方は、ご本尊を中央に、
向かって右側に十字名号、
左側に九字名号を掛けます。
または、中央にご本尊、右側に親鸞聖人の
ご影、左側に蓮如上人のご影を掛けます。
○ 絵像と名号は、本山・参拝部の法物係に、
それぞれの冥加金をそえて申し出れば
交附されます。
また、ご住職に相談すれば、取り次いで
もらえます。
○ 仏壇には、他宗のお札、お守りなどは
置きません。
○ お荘厳というのは御本尊を中心とした
いろいろの「おかざり」のことです。
○ 仏壇の中の仏具などの名称と、その配置は
御住職に相談ください。
○ 花瓶一対、ろうそく立一対、香炉一の
五点でかざるのを五具足といいます。
○ 足の三本あるものは、その一本が
てまえにくるようにおき、耳のあるものは
正しく左右にむけます。
○ 報恩講、年忌、新年、盆など、あらたまった
場合に五具足を用い、ふだんは三具足に
しておきます。
○ 五具足のうち花瓶一、ろうそく立一、
の二点をはぶいたものを三具足といいます。
○ 仏壇の上段に上卓のあるものは、
四具足を置きます。
○ 四具足の華瓶には、樒など青木の
ものをもちい、色花はさしません。
○ 仏事などの特別のときにかけるもので、
ふだんはしまっておくならわしです。
○ 冬・合用と夏用があります。
○ 色を使いわけることは家庭ではむりかも
しれませんが、よろこびのときや一般の
仏事には色ものや金色の系統のもの、
悲しみのときには白や銀色のものをつか
います。
○ 前卓の花瓶の花は、四季それぞれに
適当なものを供えますが、毒花やとげの
あるもの、悪臭のあるものはさしひかえます。
造花はつかいません。
○ 葬式、中陰など、悲しみのときには、赤い
色の花はさけます。
○ 香は、インドに起源をもつ礼拝の要具で、
塗香、割香、抹香、線香などがあります。
○ 線香は立てずに、みじかく折って横にして
たきます。
本数に規定はありません。
香は、かおりに価値があるのですから、
いやなにおいのものはさけて、良質の
香をたいてください。
○ 抹香や割香などは、香炉にあらかじめ、
炭火を入れておき、焼香のときたきます。
○ お仏飯は、毎朝お供えします。
下げるのは昼まえにするのが原則ですが、
朝のうちに下げて、暖かいのをいただいても
かまいません。
○ 水やお茶は供えません。
○ 日常はお仏飯だけを供えますが、
報恩講など仏事のときは、打敷をかけ
お供物を供えます。
○ 中央に近いところに、もち、両側に菓子、
果物の順に、それぞれ対にして供えます。
○ 魚、肉のたぐいやお酒は供えません。
○ 仏壇は欠かさず掃除いたしましょう。
羽ぼうきでかるくほこりをとり、花瓶の
水をかえたり、花をさしかえたりします。
○ 金箔のところは手を触れたり拭いたり
しないように気をつけます。
○ 報恩講・新年・彼岸・盆・年忌法要などの
ときに、とくに入念な掃除をし、仏具を
みがき、香炉の灰をきれいにします。
○ 家庭は人間が和合し、安らぐために
最も大切なところですが、その中心は
御本尊です。
○ 家庭はこどもの心を育てるには最も
大切な場所です。
とくに人間の心が失われつつある時に、
朝夕の仏参がこどもの人格形成に実に
大きな役割を持つことを、改めて考えたい
ものです。
○ 朝夕のお参りは欠かさずいたしましょう。
そして事情の許すかぎり家族そろって
おつとめをし、如来さまへ朝夕のあいさつ
をします。
○ 花をかえたり、お仏飯をあげたりすることを
お給仕といいますが、こどものいる家庭では、
その年齢に応じてこどもにお給仕を
させましょう。
それが教えを「身につける」もとになるのです。
○ 口をすすぎ、手を洗い、衣服をととのえて
仏前にでます。
○ 灯明をあげ、香をたき、仏飯を供え(夜は
供えない)、合掌・礼拝して勤行を
はじめます。
○ おわりに合掌・礼拝し、灯明を消して
退席します。
○ 勤行は、正信偈と和讃六首ずつを繰り
読みし、御文章を拝読、領解文を唱和
するのが正式ですが、ときに応じて左の
いずれかを組み合わせてつとめても
かまいません。
これらはいずれも、「浄土真宗聖典」に
のせてあります。
勤 行 拝 読 唱 和
正信偈・和讃 御 文 章 領 解 文
讃 仏 偈
重 誓 偈 浄土真宗の法語 生活信条
意訳勤行
和訳正信偈 まことのことば 仏教讃歌
十 二 礼
○ 食事のはじめに合掌し、「食前のことば」を
唱えます。
食事がすんだら合掌し、「食後のことば」を
唱えます。(浄土真宗聖典・194頁参照)
○ 食前・食後の合掌は毎日のことであるだけに、
感謝の心を養うために大きな働きをいたします。
家庭の情操教育はこんなところに
あるようです。
○ どんなに忙しくても、合掌と「いただきます」
「ご馳走さま」と礼拝だけは忘れぬように
したいものです。
○ 毎月十六日は、親鸞聖人のご命日に
あたるので、家族そろって仏前にお参り
し、その日は精進料理にして生命の尊さと
宗祖のご恩を思うのが真宗門徒の伝統です。
○ 月々の故人の命日を月忌といいます。
この日はお寺からお参りされる習慣のところも
あります。
できるだけ都合をつけて、家族いっしょに
勤行をしましょう。
○ 一年のうちに報恩講・元旦会・彼岸・
宗祖降誕会など、いろいろの行事が
ありますが、次の「お寺での行事」を
よく読んで、家庭でもお荘厳をして、
お勤めをしましょう。
なお、家庭での報恩講と元旦会について
述べておきます。
○ 報恩講はもっとも大切な仏事であります
から、掃除もおみがきも入念にし、
荘厳は最高のものにします。
お年寄りからこどもに至るまで、できれば
ご縁のある人を招いて、正信偈をいっしょに
おつとめし、法話を聞きます。
そのあとお斎をされるところもあります。
食事の習慣はすたれつつありますが、
せめて年に一度は心のこもった食事の
なかで仏縁を結びたいものです。
世の中が忙しくなって、すべてが
能率的で簡略になっていますが、
それでは人の心が育ちません。
○ 一年の計は元旦にあります。
家族そろって御本尊にお礼をし、
新年のごあいさつをします。
仏壇の荘厳は、打敷をかけ、
鏡もちをお供えし、花は松の真に
花をさします。
三が日が終わったら平常の荘厳に
もどします。
○ 浄土真宗は聞法がを第一としますから、
教えを聞くということがもっとも大切で、
○ 多忙な毎日ですが、一大事を聞くの
ですから、お寺で法座があるときは
時間をさいて、聴聞しましょう。
○ お参りするまえには、できるだけ体調を
ととのえておきましょう。
せっかくお参りしても、体が苦しくて聞け
なかったり、いねむりするようでは
おしいからです。
○ 念珠、聖典、門徒式章などを忘れぬよう
持参しましょう。
○ 勤行に唱和しましょう。
しぜんに聞法の心がととのえられます。
○ できるだけ講師の近くで、しかも正面に
すわり、講師の顔をみつめて聞きましょう。
たとえ話や因縁話ばかりを聞くのではなく、
仏法の要、南無阿弥陀仏のいわれを
聞くのです。
○ たばこなどは、法話中はもちろん遠慮します。
○ 休憩のときや帰りの道中で、おたがいに味わった
ところを語り合いましょう。
○ 初めて参られた方があったら、やさしく
声をかけ笑顔で迎えてあげてください。
○ 新年を祝うとともに、真実の教えに
生かされる身のしあわせをよろこび、
念仏もろともに報恩の生活の第一歩を
ふみだす法要です。
○ 年のはじめに御仏前にお礼をし、
心を新たにするのは、意義深いことです。
○ 親鸞聖人のご命日(一月十六日)に
あたって、聖人のご苦労をしのびつつ、
未信の人は如来の本願を聞きひらき、
獲信の人は味わいをふかめさせていただく、
真宗門徒にとっていちばん大切な法座です。
○ 年中でもっとも寒い季節ですが、身の引き
しまる寒さのなかで、ともに勤行し、法話を
聴聞し、親鸞聖人のご一生をつづった
御伝鈔を拝聴します。
○ 彼岸とは仏の国の意で、彼岸会とは、迷いの
この岸をはなれて、さとりの彼の国にいたることを
願う法要です。
春秋の二季、春分、秋分の日を中心に
行われる法座です。
○ 年中でもっともよい季節に、自分の生活を
省み、如来さまのご恩を謝し、本願の船に
のせられてさとりの彼の岸にいたる身の
しあわせをよろこぶのです。
○ 四月八日、釈尊の降誕を祝うたのしい
行事です。
○ 花御堂のなかに誕生仏を安置し、参詣者は
この像に甘茶をそそいでお参りします。
○ 「教主世尊は弥陀仏の誓い説かんと生れ
たもう」(しんじんのうた)と、親鸞聖人が
たたえておられるように、釈尊の出現が
あってこそ真実の経典が説かれたのです
から、心からお祝いしたいものです。
○ 釈尊に関する記念日としては、このほかに
さとりをひらかれた日を記念する成道会
(十二月八日)、ご入滅の日の涅槃会
(二月十五日)があります。
○ 五月二十一日、親鸞聖人のご誕生日を
お祝いする行事です。
聖人は承安三年(1173)のこの日、
京都の日野でお生まれになりました。
○ 聖人のご誕生があったればこそ、
わたくしたちが本願を聞くことができるの
ですから、そのご恩をよろこびながら
つとめます。
お寺によって、いろいろ趣向をこらした
慶祝の行事がもよおされますので、
参加しましょう。
○ 盆会には、なくなった人を追慕し、報恩の
おもいのなかに、家族ぐるみでまことの
み教えを聞きましょう。
それが、親も子も祖先もともに迷いから
救われて、まことのよろこびを得る道です。
供養するためにではなく、報恩の意味で
盆の行事をつとめさせていただきます。
○ わたくしたちの盆は、礼拝と聴聞を
大切にします。
家庭の仏壇だけでなく、必ずお寺に
参詣しましょう。
また、お墓にもおまいりしましょう。
○ 大体において関東では七月、関西では
八月の十五日を中心につとめられ、
このとき遠くはなれている家族たちも、
故郷に帰る習慣があります。
○ 盆会は盂蘭盆会を略したもので、釈尊の弟子
目連尊者の母が、仏法によって餓鬼の世界
からすくわれたという故事からおこったと
いわれており、歓喜会ともいいます。
また盆おどりも、目連尊者が、その母の
救われたことを躍りあがってよろこんだ姿に
由来するともいわれています。
○ 一月の御正忌報恩講には、門徒・僧侶
ともども本山に参拝するのがたてまえなので、
一般の寺院では取りこして一月以前に
つとめます。
「おとりこし」「お引きあげ」ともいわれるのは
そのためです。
○ 御正忌に準じた形式でつとまり、お斎の膳が
だされるところがあります。
○ 永代経は、忌日ごとに永代読経して
聴聞する行事で、本山では毎日行われて
いますが、一般の寺院では年に一回ないし
二回、法座をひらいて行われるのが通例です。
○ この法要は、死者に追善回向する意味
ではなく、故人を縁として所属の寺院に
参詣し、故人を追慕し報恩の営みを
するとともに、自身が聞法のご縁を
いただきます。
○ 永代経のため懇志を納めますが、これは
永代にわたって法座や諸堂の維持など
教化活動にあてられます。
○ 大みそかの夜、一年の行事のしめくくりと
してつとめられ、梵鐘のある寺では除夜の
鐘をつきます。
一月一日 元旦会 (修正会・しゅしょうえ)
一月八日 大御身(おおごしん)
(親鸞聖人御影像のお身ぬぐいをする)
一月九日~
十六日 御正忌報恩講
御正忌報恩講中の日曜日 本山成人式
三月 春分の日を
中心に七日間 春季彼岸会
四月八日 花まつり
四月十三日~
十五日 立教開宗記念法要 (春の法要)
四月十七日、十八日 大谷本廟永代総追悼法要ー納骨・戦没者ー
五月二十一日 宗祖降誕会 (しゅうそごうたんえ)
八月十四日、十五日 盂蘭盆会 (うらばんえ)十五日ー戦没者追悼法要
九月 秋分の日を
中心に七日間 秋季彼岸会
十月十五,、十六日 龍谷会 (りゅうこくえ) (大谷本廟の報恩講)
十一月二十一日~
二十三日 全国門徒総追悼法要 (秋の法要)
十二月二十日 御煤払(両堂の大掃除)
十二月三十一日 除夜会
人生の節目には、その意義をたしかにし、
人間としての自覚を深めるため、宗教による
儀式がもたれています。
しかしわたくしたち真宗門徒はそういう場合、
便宜や都合で他の宗教の儀礼を行ったり
しないよう、こころがけましょう。
仏式の行事は、ただ形だけの儀礼ではなく、
深い教えの裏づけにもとづいて、その人の
一生を意義あるものにするよう計画されて
おります。
詳細はご住職に相談してください。
○ こどもが生まれたことをよろこび、
所属のお寺に初めてお参りして受ける
式です。
一ヶ月から百日目ぐらいまでの間の
適当な時期につれて参ります。
○ お寺によっては、その年に生まれたこどもを
いっしょに集めて初参式をし、みんなに
紹介しお祝いするところもあります。
○ 誕生日や入学、卒業のときには、家族で
いっしょに仏前に参り、お祝いするとともに
成長の思い出や将来について話しあいましょう。
○ 家族間の断絶をふせぎ、豊かな情操を育てる
には、平素からこういう話しあいの積み重ねが
大切です。
○ 結婚という人生の新しい門出を、二人が
仏前に誓いあうことはすばらしいことです。
○ 結婚式のことを華燭の典といいますが、
その名にふさわしく厳粛華麗な式典を
もつことができます。
○ み教えに帰依し、真宗門徒の一員として
その本分をつくすことを、仏前に宣誓する儀式
で、各寺院で住職が行います。
そして、そなえつけの門徒名簿にあなたの
名前が記載されます。
○ 帰敬式は、浄土真宗の門徒として、
仏祖のまえに帰敬のこころをあらわす
式で「おかみそり」ともいわれています。
親鸞聖人のお得度にならって、
ご門主さま(またはお手代わりの方)から
「おかみそり」を受け、法名をいただきます。
○ 本山において行われますが、場合によっては
他の場所で行われることもあります。
○ 記念に、門徒式章・念珠などをいただきます。
○ 御本尊をはじめて安置したり、新たに仏壇を
もとめたりした場合には、よろこびの行事、
慶讃法要をつとめます。
○ 慶讃法要には住職を招いて勤行をし、法話や
お給仕の心得をききましょう。
○ その他、新築落成など、よろこびのときに
慶讃法要をつとめます。
○ 建築の定礎、起工、上棟なども、仏前に
これを報告して報恩感謝のこころから式を
いたします。
○ 屋外などで行事を行う場合には、かならず
御本尊(小型のでもよい)を安置して行う
ことを忘れぬようにしましょう。
○ 転居するときは、お寺へその転居先を
とどけておきましょう。
近くでしたら引きつづき教化・仏参の連絡が
受けられますし、遠方へ引っこした場合には、
その地のお寺や別院を紹介してもらうことが
できます。
○ 深い縁に結ばれた人との、人生最後の
厳粛な別離の儀式ですから、意義深く
つとめます。
わたくしたちは、ただ形式的に葬儀を
行うのでなく、また見えにとらわれてむやみと
華美にわたることなく、浄土真宗のみ教えに
反しないよう行わねばなりません。
なき方をしのび、浄土に往生させずには
おかぬ如来の大悲を仰いで、心から念仏
しましょう。
○ 葬儀にまつわりがちな迷信やまじない
(たとえば日の吉凶、逆さ屏風、魔除け、
守り刀、旅装束や六文銭、茶碗を割る、
塩をまく、一本箸をさしたご飯、満中陰が
三月にわたってはいけない、など)
にとらわれてはなりません。
○ なくなられたら、仏壇に灯明を点じ香をたきます。
花は樒か青木のものととりかえます。
○ 遺体をととのえ、顔を白布で覆い、釈尊の
入滅にならって頭を北にするならわしがあり
ますが、方角は家屋の都合で、決して
こだわることはありません。
○ 遺体のまえには、ろうそく、お花、供物などの
荘厳はしません。
荘厳をする場合は、御本尊を安置します。
○ 関係者に知らせるとともに、急いでお寺に連絡し
臨終勤行をお願いして、葬儀の日時をうちあわせます。
○ 通夜は、近親知友が集まっておつとめをし、
故人を偲びつつ静かにすごしましょう。
○ 自宅から葬場へでるときは、出棺勤行をしますが、
それはわが家の御本尊への最後のお礼ですから、
勤行は棺の正面でなく仏壇に向かっていたします。
○ 式場には、かならず御本尊をお迎えします。
○ 勤行は御本尊に向かって行います。
○ 荘厳は紙華一対、香炉、ろうそく立一対
(そうそくは銀か白)の五具足とし、打敷(銀襴か白)
をかけ、供物は赤色をさけ、焼香卓を置きます。
○ 勤行はつぎのとおりですが、「浄土真宗聖典
-勤行集ー」に収録してあります。
しずかに唱和してください。
出棺勤行 帰三宝偈
葬場勤行 正信偈・和讃二首
火屋勤行 火葬にするとき 重誓偈
収骨勤行 遺骨を拾うとき 讃仏偈
還骨勤行 遺骨をもちかえったとき 仏説阿弥陀経
御文章(白骨章)
○ 命日から数えて四十九日間を中陰の期間とし、
その間、七日目ごとに仏事をつとめ、
四十九日を満中陰といいます。
○ 死亡の翌月の命日を初月忌といい、おつとめをします。
また百カ日にも勤行をいたします。
○ 翌年から祥月命日に行う仏事を、年忌
または年回法要といい、つぎのように
数えます。
一周忌 死亡の翌年
三回忌 死亡の年を一として数える
七回忌 以下 上に同じ
十三回忌
十七回忌
二十五回忌
三十三回忌
五十回忌 以後 五十年目ごと
また、地域によっては、二十三回忌、二十七回忌、
三十七回忌などもつとめます。
○ 法事は、死者への追善供養ではありません。
命日を縁として故人をしのび、経典をいただき仏徳
を讃嘆し、仏恩をよろこぶ行事で、聞法を
大切にいたします。
○ 法事の本質をはずして、飲食やおみやげ
ばかりに重点がかからぬように注意しましょう。
○ 料理は、精進料理にいたします。
せめてこの日だけでも生命の尊さを思い、
仏道に精進しようという気持ちからです。
○ 会席での話題も、故人の思いでと、み教えを
中心にして話し合いましょう。
法事とは、法の行事ということですから、
怠らずつとめましょう。
○ 法事の日時をきめるときは、まずご住職の
都合をたしかめてからにしてください。
○ 墓は、死者を埋葬した目じるしとして、
大切に扱ってきました。
墓参りについては、それを縁として、
如来さまの前に手を合わせ、自身が
教えにあうことが何よりも大切です。
○ 墓石の正面には、「南無阿弥陀仏」の
名号を刻みましょう。
または、「倶会一処」とか「釈○○」などの
法名を刻みましょう。
他の面に、俗名、死亡年月日、年齢、
建立者名などを刻みます。
○ 歴代の先祖の法名を別の石板に刻む
こともあります。
そのとき、「霊標」とか「霊誌」など「霊」の
字を使わず、「○○家法名碑」などと
刻みます。
○ 名号以外の文字の場合は、墓前の勤行
のさい、御本尊を安置してつとめます。
○ 納骨は、土地の風習によってもちがいますが、
満中陰(四十九日)以後に墓地に納める
ところが多いようです。
○ お骨の一部を分骨して、親鸞聖人の御廟で
ある大谷本廟に納めましょう。
○ 墓をつくる時期や、いわゆる墓相などに
ついて、こだわってはなりません。
ご住職などから正しい教えを聞き、お念仏の
こころを依りどころに生きることが大切です。
○ 帰敬式(おかみそり)を受けますと、ご門主
さまから「釈○○」という法名をつけていた
だきます。
法名とは、法の名、つまり釈尊の弟子と
なって信に生きるものの名です。
○ 帰敬式を受けていない人がなくなった場合は、
住職が法名をつけます。
○ 浄土真宗では法名といい、決して戒名とは
いいません。
戒名とは、受戒して戒律を守っている人に
つけられる名で、戒律をもたないわたくしたち
ですから、戒名とはいわないのです。
○ 院とは、がんらいお寺のことですが、
そこに住居した人に、その院の名で呼んだのが
院号でした。
現在では、教団の護持につくした人や
社会のために貢献した人におくられる
敬称として、用いられています。
○ 人がなくなったら法名、俗名、命日等を
過去帳に記入しておきます。
ただし、過去帳は礼拝の対象ではありません。
なぜなら、真実の教えを聞き、本願を信じて
念仏するものは、浄土に生まれて阿弥陀
如来と同じ仏となるのですから、御本尊を
礼拝することがそのまま浄土に往生された
方にお礼をすることになるからです。
○ 位牌はまつりません。
たとえ前からあったとしても、ただそれに
よって故人をしのび、ご恩に感謝しつつ、
御本尊を礼拝いたします。
位牌のなかに、死者の霊がこもっていると
考えてはいけませんし、したがってかげ膳
なども据えません。
○ 仏旗は六金色旗ともいい、世界の仏教徒
共通の旗です。
○ そのデザインは、涅槃経の説にもとづいて、
アメリカの仏教徒オルコット氏がデザインした
ものです。
○ 布施は、インドのことば「ダーナ」(檀那)
の訳語であり、施すことをいいます。
布施する人、布施する物、受ける人の
三つが清浄でないと、本当の意味での
布施行にならないとされています。
○ 心の糧である教法を説きあかすことを法施
といい、財物を施すのを財施といいます。
○ 僧侶に差し上げる包み紙に「御布施」と
上がきするのは、財施だからです。
○ 原則として、本堂に持参して御本尊に
供えるものですから、その場で差しだす
ときは、「おことずけして失礼ですが」と
ことわって、盆にのせ、施主(主人)が
みずから差しだすのが作法です。
○ 金額は、施主の懇念ですから、いくらと
いうきまりはありません。
○ 御布施に使う水引の色は、よろこびの
ときは金または赤、一般のときは
赤、悲しみのときは銀、黒または
黄にいたします。
一、宗名 浄土真宗本願寺派 (西本願寺)
一、宗祖 見真大師親鸞聖人 (1173~1262)
一、本尊 阿弥陀如来 (南無阿弥陀仏)
一、経典 浄土三部経 《仏説無量寿経(大経)
仏説観無量寿経(観経)仏説阿弥陀経(小経)》
一、教義 南無阿弥陀仏のみ教えを信じ、必ず仏に
ならせていただく身のしあわせを喜び、つねに
報恩のおもいから、世のため人のために生きる。
一、宗風 宗門は同信の喜びに結ばれた人びとの同朋教団
であって、信者はつねに言行をつつしみ、人道
世法を守り力を合わせて、ひろく世の中にまことの
み法をひろめるように努める。
また、深く因果の道理をわきまえて、現世祈祷や、
まじないを行わず、占いなどの迷信にたよらない。
平成20年 4月~ 新しい教章にかわりました。
浄土真宗の教章 (私の歩む道)
宗名 浄土真宗
宗 祖 (ご開山)
親鸞聖人 (しんらんしょうにん)
ご誕生 1173年5月21日 (承安3年4月1日)
ご往生 1263年1月16日 (弘長2年11月28日)
宗 派
浄土真宗本願寺派 (じょうどしんしゅう ほんがんじは)
本 山
龍谷山 本願寺 (西本願寺)
本 尊
阿弥陀如来 (南無阿弥陀仏)
聖 典
・釈迦如来が説かれた浄土三部経
『仏説無量寿経』 『仏説観無量寿経』 『仏説阿弥陀経』
・宗祖親鸞聖人が著述された主な聖教
『正信念仏偈』 (『教行信証』行巻末の偈文)
『浄土和讃』 『高僧和讃』 『正像末和讃』
・中興の祖蓮如上人のお手紙
『御文章』
教 義
阿弥陀如来の本願力によって信心をめぐまれ、念仏を申す人生を歩み、
この世の縁が尽きるとき浄土に生まれて仏となり、迷いの世に還って
人々を教化する。
生 活
親鸞聖人の教えにみちびかれて、阿弥陀如来の み心を聞き、
念仏を称えつつ、つねにわが身をふりかえり、慚愧と歓喜のうちに、
現世祈祷などにたよることなく、御恩報謝の生活を送る。
宗 門
この宗門は、親鸞聖人の教えを仰ぎ、念仏を申す人々の集う同朋教団
であり、人々に阿弥陀如来の智慧と慈悲を伝える教団である。
それによって、自他ともに心豊かに生きることのできる社会の実現に
貢献する。
○ 経 典
仏説無量寿経(大無量寿経)、仏説観無量寿経、
仏説阿弥陀経
○ 宗祖親鸞聖人御撰述
顕浄土真実教行証文類(教行信証)(御本典)
御和讃、御消息、尊号真像銘文、一念多念文意、
唯信鈔文意、その他
○ 歎異抄、蓮如上人の御文章、蓮如上人御一代記聞書、
覚如上人・存覚上人の御撰述、七高僧の御撰述、その他
| どうぞ一言(伝言板) |
|
|