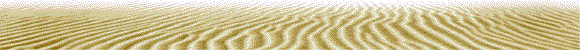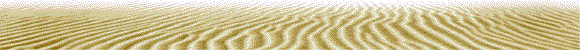
仏教は、さまざまな説き方が
あります。
南無阿弥陀仏の教えは、
その中の一つです。
仏説無量寿経に説かれる
阿弥陀如来の本願の
はたらきで、すぐれた功徳を、
すべての衆生に与え、
「南無阿弥陀仏」一つで、
救われることを、教えて
くださったのが親鸞聖人です。
親鸞聖人を、宗祖と仰ぐ、
浄土真宗の本願寺派。
そこに所属する九州・佐賀の一寺院で
製作しているのがこのホームページです。
「南無阿弥陀仏」の味わいを、電話で
お話ししています。毎週木曜日に、
内容を変更しています。
法話原稿をこのページに掲載して
います。ここで、「見て、聞いて」 ください。
メールマガジン始めました 「こんな話を聞きました」。ユーチューブ 妙念寺
0952
|
記憶してください。)
24はニシ、西。 本願は、18願。
そこで、24-1800は、西本願
第1725回 たのむ 頼む 憑む
令和8年 2月19日~
蓮如上人のお書きいただいた「御文章」には
「たのむ」ということばが、沢山出てきます。
如来をたのむこころの、本願たのむ決定心を たのむべきは弥陀如来
阿弥陀仏を一向にたのむによりて、ただ弥陀一仏をたのむうちに
如来をたのむ身になれば 弥陀をたのむ機を
弥陀をたのめば、
南無とたのむ衆生を
などなどです。
ところが、ここでは弥陀に たのむのではなく、
弥陀を たのむとなっています。
「に」ではなく「を」なのです。
親鸞聖人の教えの中には 弥陀「に」は出て来ずに
みんな弥陀をたのむとなっています。
今 私たちが使っている「たのむ」は 依頼する お願いすると
こちらの希望を頼み込む言葉です。
念仏するから助けて下さいという 取引の心です。
見返りを期待している。信じるから助けて下さい、苦しみを除いて
金が儲かるように、病気が治るようにと・・・・、
ところが、ここでは
こうした依頼の「賴」ではなく、「憑む」という意味だというのです。
さんずいから 一つとって にすいに 馬、その下に心と書く、憑むです。
この「憑む」は、「ああしてください、こうしてください」と
お願いや 注文の心をすべて捨てて、すべて阿弥陀さまに
おまかせし切って安心して日々を重ねることだと言うのです。
思い通りになっても、ならなくても、この人生を
ありのままに受け入れて歩ませていただくということです。
私たちの人生には、よいこともあれば、悪いこともあります。
それを一喜一憂するのではなく、すべて受け取って行こうということ。
歎異抄には、「よきことも、あしきことも、業報にさしまかせて、
ひとえに本願をたのみまいらすればこそ、他力にてはそうらえ。」
とあります。
よきことも、あしきことも業報におまかせする。
これが本願をたのむ、如来をたのむ、他力をたのむと
いうことなのですが、 私たちは どうしても、わが身を頼み、
力んでしまいます。
それが 迷いの根本であることを教えていただいているのです。
すでにおさめとられている私自身であったと目覚めるさせる、
お呼びかけが「弥陀をたのめ」のみ教えなのです。
第1724回 みんな平等に
令和8年 2月12日~
お寺にご縁の薄い方とお話をしていると、なかなか話が
咬み合いません。どうしてなのか、今はやりのAIに聞きました。
浄土真宗の教えは、能力がある特別の人だけではなく
「すべての人が平等に救われる」という独自の信仰で、
しかも、人間の努力ではなく、仏さまのはたらきで
救われると説かれています。
自己責任や自助努力が強調される中、現代人にとって
理解が難しく誤解されることもあります。
「他力」とは「他人任せ」や「努力しない」という
ネガティブな意味が強いものの、自分の力で悟りを開く
「自力」に対し、阿弥陀如来の慈悲にあふれた力(本願力)
仏のはたらきで救われるということで、自分の力ではなく
「他の力」で、仏さまの力で、これを他力の念仏で
救われるといいます。
阿弥陀如来(阿弥陀さま)の、どんな人でも必ず救う
という願い(本願)は、「南無阿弥陀仏」というお念仏を通して、
私たちに届くといいます。
ですから、阿弥陀如来の本願の話を、繰り返し繰り返し
聞き、南無阿弥陀仏を口にする生活を始めると、生きることの
意味や命の大切さに気づかされていくのです。
そして、日常の苦しみや悲しみを通して、心がだんだんと育てられて、
人生の迷いや不安を、これまでの損得や、勝ち負けの
価値観ではなく、新たな視点で受け止める力が育てられ、
これから私が、進むべき道が明らかになってきて、
こころ安らかな気持ちで日々を過ごせるようになるのです。
普通の宗教のように 私が努力して変わっていくのではなく、
仏さまの話を聞いて、新たなものの見方ができるようになると
世界が変わって見えて来て、悩み苦しみも、乗り越えていくことが
出来るようになるのです。
ですから、病気の人でも、高齢者でも 動けなくても、努力出来なくても
みんな平等に、一人残らず問題を解決することが出来るのです。
聞くだけで 誰でもみんな 安心が得られるのです。
第1723回 迷惑をかけるので
令和8年 2月5日~
「子どもに、迷惑をかけたくない」と、よく聞きます。
子どもたちに遠慮しながら生活している方が多いようで、
年忌法要なども、若い方の姿は少なく、年配者だけでお勤めする
ケースが多いものです。
浄土真宗では、「迷惑」という言葉を、少し違った意味合いで
捉えます。
「人に迷惑をかけたくない」という気持ちも大切にしつつ
誰もが「迷惑をかけずに生きられない」という視点です。
私たちは、生まれてからずっと誰かに支えられ、助けられて
生きています。
赤ちゃんは一人で何もできませんし、成長し自分で食事が
出来るようになっても、他の命をいただいて生きています。
生きるということは、誰かの助けによって成り立っており、
人は一人では生きていけず、知らず知らずのうちに
多くの人に迷惑をかけながら生きている、誰にも迷惑を
かけずに生きることは不可能と考えるのが浄土真宗の教えです。
一方 他の多くの宗派では、自らが修行を行い、戒律を守ることで
煩悩を克服し、悟りを開くことを目指します。
このプロセスの中で、他者に迷惑をかけないように
努力することが重視されるのです。
ある方は、「迷惑をかけるな」と教えるのは道徳 「迷惑をかけている」
と教えるのは宗教であるとおっしゃっています。
ところが、段々と都市化して迷惑を「かけたり」
「かけられたり」することが苦手になっていますが、
老いや病気、死といった苦悩に直面すると、誰かに迷惑をかけたり、
かけられたりする時が必ず訪れてくるものです。
お互いが支え合い生かされている生命であることを、
子どもや孫に、はっきりと教えるのは親の責任であると思います。
子どもたちが将来、あわて悩み苦しむことのないように
ちゃんと伝えておきたいものです。
近頃、葬儀や通夜も、遠慮して密かに行われることがありますが、
この世は、いかに多くの方々のお陰で生かされているのか、
親たちが迷惑をかけ、掛けられた方々を 多くの参列者を通して、
教えることが出来る最後のチャンスが、お葬式だといえるのでしょう。
第1722回 造花? 生花?
令和8年1月29日~
寒い中 多くの方が お墓参りにおいでになります。
月二回 一日と15日とか、大切な方の命日など
枯れ花にならないうちに、連れだってお参りになっています。
浄土真宗では、亡くなった方はすぐに阿弥陀如来のお導きによって
お浄土に往生し、仏様となると考えられています。
そのため、お墓は故人の魂が宿る場所と考えるのではなく、
故人を偲びながら、仏に成った亡き人からの声なき声をご聴聞する、
阿弥陀如来の教えに出会う聞法の場所であり、
教えに照らして自身の生き方を省みる場所として大切にされてきました。
たくさんの命をつないで 私は今ここにいる、
たくさんの命を受け継いでいることを感じ、
命を伝えてくださったご先祖様に感謝し、受け継いだ大切な命を
精一杯輝かせて生きることを誓い、自身の命の有限性を味わう場
とされています。
お墓参りは、日々の忙しさの中で忘れがちな自己や
人生を振り返る貴重な機会であり、自身の命のあり方を
見つめ直す大切な機会といえましょう。
ですから、お墓参りは故人やご先祖様に対して
何かをして差し上げる「供養」というよりは、
阿弥陀様とともに、ご先祖様が仏となって私たちを
見守ってくださっていることへの「感謝」を伝える場であり、
家族の歴史を語り継いだり、つながりを感じるための
大切な場所なのです。
そこで、他宗派で行われるような、故人の魂を清めたり
喉の渇きを癒す意味での墓石への散水や、仏前へのお水や
お茶のお供えすることはしません。
お花や灯明は、限りある命を仏様から教えていただくための
手立てとしてお供えします。
そのために、必ず枯れる生花を供え
「生きて、やがて死を迎える」すべてのいのちの
はかなさと尊さを教えていただくため、造花ではなく
生きている生花をおそなえするのです。
お寺の境内地にあるお墓や納骨堂の場合は まずは、
本堂の阿弥陀如来にお参りしたあとで、墓地に向かいます。
節目節目には、庫裏に立ち寄り ご挨拶をし、お寺を維持する
ためのご懇志をお届けする伝統が、浄土真宗にはあります。
まずは、ご家庭での何気ない会話や行動を通して、
お墓やお寺を身近に感じてもらうこと
特別なこととして構えるのではなく、生活の一部として
幼い頃から一緒にお墓参りに行く お墓参りを習慣化して
自然に接する機会を増やしたいものです。
第1721回 いつも私と一緒に
令和8年 1月22日~
元気だった母親が ちょっと病院に行ってくると出かけ、
帰りが遅くなって心配していましたら、乳がんだと言われたと
はにかみながら帰ってきました。
早速手術ということで、慌てて準備をして入院しましたが、
いつも台所に貼ってあった紙を持っていき、病室の壁に、
母親が貼りました。
岩本月州という、大変お念仏を喜ばれた方の言葉ということです。
「常に居ますを佛という。此処に居ますを佛という。
共に居ますを佛という。この佛を南無阿弥陀仏という。
このいわれを聞いて歓ぶを信心という。
称えて喜ぶを念佛という」。と、そこにはありました。
「常に」「ここに」「共に」ということは、
「いつも私と一緒に」ということなのでしょう。
これから手術、手術はうまくいくのか、どこかに転移はしていないのか、
とても不安な時に、南無阿弥陀仏の如来様が いまここに、共に
涙してくだっていると味わうことで、母は まったく不安な様子を見せず
平然と 堂々とした姿をしているのだろうと感じました。
後は、おまかせするだけ、人間の力では、患者の力では
どうすることも出来ない、専門家のお医者さんに、
そして、阿弥陀さまに お任せするほか 方法はありません。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏と ,母親は 不安を乗り越えようと
しているのでしょう。
病院には 沢山の方が 手術や治療を待っています。
ここにいるすべての人が、皆 同じように、今後の不安を
抱きながら 入院していることだろうと思いました。
人間の苦しみ 四苦八苦 どんなに立派な人でも、どんなに
お金がある人でも、若く元気でいる人も、やがては
すべての人が 受け取る苦しみがあるのです。
その苦しみ悲しみを いつも一緒にいて、分かってくださる方が
阿弥陀さまという 仏さまなのです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 と耳に聞こえる
仏さまが、いつもここに、いらっしゃると味わい
かずかずの苦しみを乗り越えていくことが出来るのだよと、
母親を通して阿弥陀さまは 教えていただいているのでしょう。
第1720回 お育ていただく
令和8年 1月15日~
浄土真宗の特徴的な言葉の一つに お育ていただくという言葉があります。
今はやりの AIで、聞いてみましたら 次のような内容が出てきました。
「お育ていただく」とは、仏様の教えや はたらきによって、
私たちが宗教的な、人として成長していくことを指します。
これは、親鸞聖人の宗教観をよく表している言葉と言われます。
この言葉には、私たちが自力、自分の力で成長するだけでなく、
阿弥陀如来(仏様)の慈悲深い願いと はたらきによって、
あるがままの私たちが受け入れられ、育まれるという意味合いが
含まれています。
つまり、仏様が私たちを「お育てくださる」という心温まる感覚です。
これを、如来のお慈悲に抱かれるという表現もします。
浄土真宗での「お育ていただく」ことは、単に知識や教養を身につけ、
立派な人間になることではありません。
むしろ、日々のできごとや事柄など、日常の出来事を通して、
「あなたはどんな人間として生きていますか?」といった、
自分自身への問いかけを受け取ることを意味します。
南無阿弥陀仏 と お念仏を口にしたり、仏様の教えを聞こうとする
気持ちが起こるのは、本来の自分にはない姿であり、仏様の純粋な
願いが自分に表れているのだと、親鸞聖人は味わっておられたそうです。
この「南無阿弥陀仏」のお念仏そのものが、如来の願いとはたらきであり、
私たちをお育てくださるものとされています。
幼い頃からお寺とのつながりがあったり、近くにいるお念仏の人
はじめ、多くの人に支えられて、生かされていると感じたりすることも、
お育てをいただくことと関連しています。
特に、人生の節目で出会う人々や、子どもの言葉やまなざしからも、
私たちが育てられていると感じる機会は多いでしょう。
幼稚園での「ののさま教育」のように、幼い頃から合掌や念仏、
礼拝といった行為を通じて、自然と仏様の心が育まれ、
いのちの尊さや倫理観が培われることも「お育て」の一環です
第1719回 未来は 後ろ 過去は 前
令和8年 1月8日~
これから迎える「未来」は 前にあるのか 後ろにあるのか
どちらにあるのでしょうか。
いつも 前を向いて 歩いていますし、車で走っていると
景色は どんどんと後ろに消えていきますので、
これから訪れる未来は 前方にあり 過去は 後方にあるように
考えています。
ところが、言葉の上では 逆で、未来は後ろ 過去は前として
使っています。
「それでは三日後にお会いましょう」とか、「ひと月後には
完成する予定です」などと、これから来る未来は
後 と言っています。
反対に、過ぎ去った過去は、一昨日のことは、2日前といい、
去年のことも、なんと一年前にといっています。
過ぎ去った過去は 後ろではなく 前と表現しているのです。
どうも未来は、前ではなく、後ろにあるようです。
ですから、前を向いて生きている私たちには、過去は見えても
未来は なかなか見えてこないものなのでしょう。
その証拠には、過去のこと、昔はこうだった、あの時は
ああだったとよく憶えていますが、あしたのこと、明後日のことは
まったく見えず、何も分かってはいません。
私たちは、生まれてからこのかた 前向きではなく、
後ろ向きに、後ずさりしながら生きてきたようです。
後ろ向きだったために、人とぶつかったり、人を傷つけたり、
見えないために、迷いの人生を生きているのでしょう。
そんな私たちに 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏を聞かせ
進む方向を、目的地を教えていただいているのが阿弥陀さまです。
見えない未来を 迷わないように お念仏で導いていただいているのです。
近頃の自動車には、バックするときには、後ろの様子を映してくれて、
カメラが付いていて、少しは安心です。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏は、後ろ向きに進んでいる私たちに
迷わないよう、ぶつからないよう、教えてくれているのです。
目的地は お浄土であることを、お聴聞すると、カーナビのように
間違いなく誘導してくださるのです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏に お任せすれば、見えていなくても
もう安心です。
どんなに迷っていても、どんな障害物があろうとも心配なし、
間違いなく お浄土へ、父も母も行ったお浄土に、間違いなく
到着することが出来るのです。
第1718回 念仏相続
令和8年 1月1日~
新しい年を迎え、今年も喜び多い一年でありますよう、
お念仏を確かに相続していただきたいものです。
ところで、昨年秋の巡番報恩講には、たくさんの皆さまに
お参りいただきまして、誠にありがとうございました。
その時にもお話ししましたが、近頃「相続」という言葉を
よく聞くようになりました。
相続というと、大切な方を亡くされて、その財産やお金を
受け継ぐことだと思っていますが、元々は「念仏相続」という
言葉から始まったもののようです。
この世に誕生し、生きていくには 財産があろうがなかろうが、
男であれ女であれ、誰もがみな様々な苦難に出あい、それを
乗り越えていかねばなりません。
これは、今生きている私たちだけではなく親や先輩達もみんな、
大きな悩み苦しみを持ち、必死にその問題を解決して、一生を
終わられたことでしょう。
そして、その苦悩を解決するのに、もっとも確かな方法が
あることを知り、それを次の世代の子どもや孫たちに伝えようとして、
お念仏の教えを残していただいたのだろうと味わいます。
すべてのものを必ず救いたいという阿弥陀さまの願いである
お念仏、南無阿弥陀仏を口に力強い生活をしていくことで、
辛い苦しい生活は転じられていき、味わい深い豊かで喜び多い
人生となることを、自分が経験し、それを、私たちに残して
いただいているのだろうと思います。
毎日毎日が、老・病・死と向き合い、これから何が起ったとしても、
南無阿弥陀仏のお念仏さえあれば、間違いない、大丈夫であると、
お仏壇や お寺やお墓を通して、伝え残そうとされているのでしょう。
どうか、税金のかかる財産やお金ばかりを受け継ぐだけでなく
親たちが最も残したかった宝ものを、お聴聞することで、気づき
間違いなく、確かに受け取っていただきたいと思います。
南無阿弥陀仏さえあれば、心配ない問題なし、希望に満ちた
明るい未来が開かれてくることを、聞き取り、受け継いで
いただきたいものです。
それには、お聴聞を繰り返して、南無阿弥陀仏を口にする生活を
することで、生き甲斐ある味わい深い、喜び多い生活が
はじまるのです。
ですから、お念仏を口にする生活をすることこそが、
最高の親孝行になると思います。
いくら病院に通っても、医療では解決できない問題が沢山あります。
その根本的な人間的な苦し悩みを、お寺に通い間違いなく治して
いただき、今年も力強く喜び多い毎日をお過ごしいただきたいものです。
第1717回 仏さまにないもの
令和7年 12月25日 ~
こんな話を聞きました。
仏さまにはあって、人間にないものはいろいろあるが、
逆に、人間にあって 仏さまにないものは 何ですかとの質問です。
「苦しみ」「欲望」「怒り、不安、病気や老い 生身のカラザ」
いろいろと考えましたが、
答えは、人間には、背中があるが 仏さまには背中がないということだと
いうのです。
善導大師の般舟讃に「仏心円満無背相」 という言葉のことでしょう。
私たち人間は 都合のよい人には、その正面に向かって和やかに近づき、
頼み事や願いを伝えるものです。
ところが、都合が悪くなると 向き合おうとはせず、すぐに背中を見せて
逃げてしまします。
すべての人を一人残さず救いたいと、はたらき続けておられる仏さまが
あると、聞いても、その仏様に向き合うとはせず、自分には関係無い、
もっと大事な事がある忙しいと、背を向けています。
我を忘れて育ててくれた親に対してでも、いつも背中を見せて
向き合おうとはしていません。
ところが、仏さまは どんな人にも真正面に向き合って、
何としてでも救い取りたいと、呼びかけ、はたらきかけておられると
いうのです。
無視して逃げていくものも その正面に立って、南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏といつも真正面から、呼びかけていただいていると言うのです。
どんなに沢山の人が居るところであっても、この私のためだけに
正面に来て、見守っていただいているというのです。
そのことに気づくことが出来るのか 出来ないか、それで
私の人生は大きく変わってくることでしょう。
誰の世話にもならず、一人で生きていると、我が儘勝手な私ですが、
いつも私の前に 真剣に向き合っていただいている眼差しがあることが
味わえてくると生き方が大きく変わってくるのでしょう。
子どもの頃を思い出してください、演台に立って 発表するとき、
舞台の上で 歌ったり踊ったり演技をするときのように、
私をちゃんと正面から見つめ 応援していただいている方がある、
私は期待され 心配され 感心を持って見つめられているのだと、
そのように味わえてくると、誰も見ていなくても、仏さまだけは
いつも私を正面から じっと見つめ応援していただいているのだと。
どうか緊張せずのびのびと 思いのままに、これまでの成果を 今
ここで 充分に表現していきたいものです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏は 私を見つめ応援して
いただいてありがとうございます。
ちゃんと見て聞いていただいて、いかがでしたか
これでいいのでしょうかとの、問いかけでもあるのです。
今日という1日を、この瞬間を 阿弥陀さまの前で 精一杯
自分の出来ることを励みながら、南無阿弥陀仏とともに
力強く、活き活きと生活していきたいものです。
第1716回 忘れてしまっても
令和7年 12月18日~
こんな話を聞きました。
父方の祖母を、家族そろって見舞いました。
90歳を過ぎ、介護施設で生活している茶目っ気な 明るくチャーミングな
祖母を訪ねました。
部屋に入ると、よく来てくれたねと大変喜んでくれるましたが、
しばらくすると、あなたはどちらさんでしたかね。とにこやかに尋ねます。
孫であることを名乗ると ああそうそうと、懐かしそうに喜んで
くれるのですが、しばらくすると、また どなたさんでしたかねと、
質問します。そのたびに みんなが大声で笑います。
笑い声の絶えない明るい時間でしたが、父親だけは窓際に立ち、
外ばかり見て、その会話の輪に入ってはきません。
楽しい面会が終わり、また来ますね。ありがとありがと
また来てねと、明るくお別れをしましたが、
帰りの車の中で、父親がぽつりと言った一言を、忘れることができません。
実の親に、忘れられてしまうのはつらいなあー、その時は、痴呆症になった
実の母親が、自分のことを忘れてしまっていたことが、大ショックだったの
だろうと、受け取っていましたが、今、思い返すと、そればかりでは
なかったのかもしれません。
もし、自分が母親と一緒に生活することが出来ていたならば、
介護施設ではなく、自宅で一緒に生活していたのなら、あのように
自分のことを、忘れることはなかったのではないかと、悔しく
つらい思いをつぶやいたのではないかと、気づきました。
痴呆症になれば、一緒に生活していても、だんだんと分からなく
なっていくものなのでしょうが、息子とすれば、一緒に生活していたなら、
自分のことを忘れずにいたのではないかと、悔やんでの言葉だったのだろうと、
味わっています。
人間は いかに頑張っても 忘れてしまうことがあります。
どんなに可愛い子供のことでも 年を取ると、やがて忘れてしまうものです。
ところが、阿弥陀さまという仏さまは、こちらが忘れてしまっても
決して忘れることのない 仏さまです。
忘れて 無視していても、決して見捨てることのないのが
阿弥陀さまです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 声に聞こえる仏さまが
阿弥陀さまです。
自分で口にし 自分の耳で聞き、阿弥陀さまが、今 ここに
一緒であることを、どこか、遠くではなく、ここに一緒であると
味わいながら喜ばせていただきたいものです。
私が忘れても、忘れずに 私を励まし、導いてくださるのが
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏の阿弥陀さまなのです。
第1715回 気づくか 気づかないか
令和7年12月11日~
お父さんに続いて 94歳のお母様が亡くなられました。
一人っ子のお嬢さんが、笑わせて撮られた笑顔の遺影に、
「良い写真ですね」とつぶやいてしまいました。
お父様の法名を見ると 院号が着いています、
「お母様もお父様のように院号頂きましょうね。」と言うと、
従姉妹の方が、「どういう意味ですか」と聞かれます。
ご本山の護持に貢献された方に贈られるもので、法名の釈○○の前に
着いているのが院号です。
お念仏の教えが今後も伝わっていくようにと、宗門の護持発展に
貢献された方に贈られるものです。
自分のお寺が繁栄するための祠堂料に加えて、ご本山もお守りしようとの
有り難い思いの方に贈られる敬称です。
院号は 生前に頂戴される方もありますが、いのち終わって
お浄土へお生まれの時に、今生最後のお布施をされることです。
ところで、同じご懇志でも、境内の墓地を整理して、離檀される方が
あります。
今回は、お子さまの無かった方の甥っ子姪っ子が、遠隔値に
お住まいで、墓じまいをされました。
合同の墓と、永代墓とありますが、どこが違うのですかと聞かれます。
永代墓は、門徒数が減ることで、お寺の維持する人数が減って、
残された皆さまにご苦労をかけますので、今後10年20年分ぐらいの
お布施をまとめてお預けしようという有り難い行いです。
一方 合同の墓は、残されたご門徒の方々への思いやりなどはなく、
これでご縁を終わらせてくださいという、どちらかというと、
自己本位の方のお考えのように思えます。
十個近くあったご遺骨を、合同墓に捨てるように立ち去っていかれました。
お寺の法要によく参加し、ご両親の年忌法要を、ちゃんと勤め
される方がある一方、まったくご縁の無い方もあります。
先祖が立派なお墓を建てていても、こどもや孫達がまったく
ご縁の無い方があります。
ちょんとお勤めをされる方々は、経済的にも精神的にも豊かな
生活をしておいでの方が多いように感じますが、
まったくご縁の方々は、暗く辛い人生の方が多いように見受けます。
ご先祖さまのはたらきかけが、あるかないかの違いなのかとも思いますが、
どうも自分を取り巻く多くのはたらきかけに、ちゃんと気づくことが出来て、
それらに感謝し対応する能力がある方と、損得勘定だけで、
自分に有利な方々には、ちゃんと向き合うものの、
静かにそっとした はたらきかけには気づかず、感謝することもなく
無視して日常を送っておられる方は、やはり、どうも、この世の中でも
うまくいかないのだろうと思います。
亡くなった父母、祖父母は、声もなく過去のことで、気づかず
無視している生活、こんな無味乾燥な生活では、人生は、生活は
うまくいかないのだろうと味わっています。
やるべきことは、ちゃんとやった方が、人生は、豊かで
有り難く喜びに満ちた生活になるもののようです。
第1714回 憶えていますか
令和7年12月4日~
ごく自然に お仏壇の前に座って 手を合わせていますが、
その最初はいつ頃だったか憶えていますか。
きっと、おじいちゃんや おばあちゃんに連れられて、いただいたお土産の
お菓子やお年玉を、お仏壇にお供えしたのが最初だったのかもしれません。
朝、学校に行く前に、仏さまにご挨拶をして、帰って来た時も、
仏さまにご挨拶をと、言われ、通信簿をもらってきたときも、
仏さまにまず報告してと、いつも、仏さまとのご縁を結んでくださった方が
おられたからなのでしょう。
生きている人だけではなく、仏間に飾ってある写真の祖父母 曾祖父母、
そして、顔をしらない多くのご先祖様達が みんな阿弥陀さまといっしょになって
この私を守り、導いてくださっているのだと、いつのまにか知らされていました。
私の人生は、自分の力の及ぶことばかりではありません。
人間の力の及ばないことがたくさんあり、自分で出来ることは一生懸命頑張り
力の及ばないことは、思い通りにならないことは、お任せする
しかないことを、先輩達は教えようとしてくれたのでしょう。
そのことを、知らなければ、自分の努力不足を嘆き、能力のないことを
悔やみ苦しんでいたことでしょう。
世の中には、多くの人がいて みんな違った考えを持って生きています。
しかし、共通する部分は 必ずあるものです。
それを、阿弥陀さまの願いとして、私たちに教えていただいているのでないか
自分の我が儘通りなるのが幸せではなく、みんなが喜べること、
皆が納得いくことがあることを、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏の教えとして、
私たちに残してくれているのでしょう。
自分の行いの結果は 必ず自分に帰ってくること、地獄にいくような
生き方をしていても、必ず お浄土へ生まれさせ、仏にして活躍させる。
自分の幸せを優先させるよりも、皆んなが幸せであることが、
本当の喜びと、教えてくれているのでしょう。
自分が努力した以上に 親や兄弟や先輩 太陽や空気や自然、あらゆる力が
私を生かそう 生かそうとはたらきかけていることを、気づかせ感じさせ
感謝できる、喜べる人間に育てようとする、はたらきかけを
気づかせ 味あわせ、感じさせ、喜ばせていただているのです。
気づけ 気づけとの呼びかけが 南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏の
呼びかけ、はたらきかけ、
私の周りにはいらっしゃった御影です。
有り難いことです。南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
第1713回 何を聞くの ?
令和7年11月27日~
浄土真宗は お聴聞の宗教 聞くことが大事、聞くこと一つと言われますが、
いったい何を聞くのでしょうか。
普通 聞くというと これから何をすればいいのか 何が
必要か、ああしなさい、こうしなさいと、私が行うべきことを
聞くことだと 考えます。
ところが、お聴聞というのは、私がやるべきことを聞くのではなく、
私のために、仏さまがすでにはたらきかけていただいていることを、
聞かせてもらうのだというのです。
多くの人が、今さら聞く必要などない、もう充分にやるべきことを
やってきたと、思っています。
そこで
しかし、私がこれからやるべきことではなく、すでに、
私のためにしていただいたことを 私のためのはたらきかけ、
仏さまの願いを、知らせていただくのだというのです、そしてそれを
確認することだと言われます。
例えは余りよくありませんが、これから新たに宝くじを買いましょうではなく、
すでに当選している宝くじをいただいているのに、気づいていない私に
当選くじを持っていますよ、当たっていますよと、教えていただくようなものです。
気づかずにいる私に、すでに、私のためにはたらきかけがあり、
沢山のものをいただき、素晴らしい能力をもっていることを
気づかずにいるこの私に それを教え気づかせていただくのです。
今は人間として悩み苦しんで生きていますが、やがて
必ず 仏になって、すべての人々が 喜び多く 生き甲斐をもって
生きていける、お念仏の教えがあることを、それを伝え知らせることが出来る
仏になるのだと、教えていただいているのです。
ただの平凡な人間と思っていますが、そうではなく間違いなく
やがて仏さまになって みんなのためにはたらく未来があるのです。
そして、先だった先輩達は、阿弥陀さまといっしょになって、ずっと、
はたらきかけていただいている、
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 を口にして、堂々と生きていきなさい
あなたはもう 仏になる仲間 間違いなく仏さまになる人なのですようと。
南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏のお念仏ですよ。
間違いなく 仏に成る人なのですよと、呼びかけていただいているのです。
第1712回 ぼんやりしないで
令和7年11月20日~
暑さ寒さも彼岸までといいますが、ひと月遅れで やっと
暑さがおさまってきたようです。
急に冷え込んだお陰で、柿の葉やモミジなどの紅葉が、今年はいつも以上に
鮮やかです。
折角の色どりを尚一層輝かせようと、山門に近い一部分だけ
ライトアップをはじめました。
寝る前に その消灯に出て つまざき倒れ、左ひざ頭、手の平、
顔の左ホウの一部を、参道の石畳に、強く打ち付けてしまいました。
しばらく、立ち上がることが出来ずにいましたが、顔が腫れ上がるのは
さすがにみっともない、イヤだなあと思い、なんとか起き上がり、
まっすぐ冷蔵庫に、保冷剤を取り出し、近くにあったマスクを当て、
その上から、顔を冷やしはじめました。
そのうち、だんだんと本当に痛い部分がはっきりとしてきて、
顔よりも、どうも手のひら、左ひざ頭のお皿の部分が最も痛く感じます。
お皿は割れてはいないようですが、その痛い部分を見下ろすと、
ズボンが血で赤くそまっています。
おそるおそる覗いてみると、かなり出血しており、このままでは
布団に入るわけにもいかず、どうしたものかと悩みました。
膝小僧のしわしわの部分に、かさぶたができると、正座したときに
出血しそうで、固まらないように、シワをしぼめたり 伸ばしたり
しながら、眺めていると、どんどんと変化していき、傷があるのは、
三カ所のようで、そこが、黒くなっていき、やがてピンクに変わり、
出血は止まったようです。
膝小僧から、くるぶしまで 流れていた血も、赤から黒に
変化してきて、自分の体が、一生懸命に傷を治そうと頑張っている様子が
有り難く感じられてきました。
自然は、本当に素晴らしいものだと、感じながら、痛さを我慢して
しばらく眺めていました。
そして、いつまでも若いと思うな、つま先をちゃんと上げて
いるつもりでも、上がっていないもの、つまずき易くなっていることを、
改めてハッキリ知らされました。
とともに、この程度のケガですんだことに、有り難く、これが、
阿弥陀さまに守られているということだろうと、深く感じ、あじわいました。
ぼんやりとし、不注意に、行動していることを、痛さとともに
はっきりと味わわせていただき、気づかされ、有り難く、感謝の、
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏を、傷が治まっていくのをじっとながめながら
お念仏させていただきました。
第1711回 阿弥陀さまのはたらきかけ
令和7年11月13日~
十年半に一度担当しお勤めする 佐賀組の巡番報恩講 先月、
10月の初旬に、五日間お勤めすることが出来ました。
そのお疲れさん、ご苦労さま会を、総代会、壮年会、婦人会の
メンバーに加えて、連日お手伝いしていただいた方々をお招きして、
日曜日の夕方に開きました。
いつものように机に椅子を置いての会では、なかなか交流ができだろうと、
本堂に机を置き それぞれに、オードブルやお寿司 おでんなどをならべて、
各自が自由に取って食べる、立食パーテー形式にしましたが
予想以上に みるみるとお料理がなくなっていき
その食欲のすごさにびっくりしました。
会の途中で、プロのカメラマンに撮ってもらった、
雅楽が入った法要三日目と、稚児が出た4日目の写真、700枚近くを
スクリーンに大きく映して、皆で見ました。
そこには、日頃なかなか見せない笑顔やご法話を聞き入る真面目な顔、
おやつの時間の、にぎやかで楽しい様子などが写っていましたが、
見ていくうちに、気づいたことがあります。
本堂になかなか座っていただけない方が、お手伝いに来て、
活躍しておられる姿が、あちこちに写っているのです。
見慣れたお顔の中に、これまでお寺では、拝見することのなかったが
方々のお顔が、沢山あり、感激しました。
仏さまの御はからいという言葉がありますが、黙々とはたらいて
いただいている多くの姿を見て、私の周りには、いろいろの
はたらきかけがあるのに、それに気づいていなかったのだけだと、
改めて味わいました。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 耳に聞こえるお念仏とともに
阿弥陀さまは 数々の多くの人を通して、あらゆるところで、
さまざまに はたらきかけていただいているのに、それを見落として、
まったく気づいていないことがいかに多いのだろうと、感じました。
いつもお世話いただく皆さま、そして、今回初めてご苦労いただきました
皆さま、本当に有り難うございました。
そして、その方々も、自分の力だけではなく、阿弥陀さまの
はたらきかけで、先だった親たちの導きで、こうしてお寺にお参りし、
法要に参加いただいたのだろうと、有り難く有り難く味わっています。
仏さまの多くのはたらきに、気づかせていただき 感激し、
感謝しております。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
第1710回 おかげさま お影さま
令和7年11月6日~
「ご家族はお元気ですか」と ひさしぶりに会った人から
尋ねられたときに、「おかげさまで元気です」と答えて、
いいものでしょうか。
直接には、お世話になっていないのに「おかげさまで」と言うのは
どうも抵抗を感じる人がいるのではないかとの疑問に
NHK放送文化研究所が調査したところ「おかげさまで」という
言い方に、抵抗があるのはほんの少数で、ビジネスの世界などでも
広く使われていると言うことです。
この「おかげさま」ということばは 近江商人が、
全国に行商する中で、こうして商売をさせていただけるのは
阿弥陀如来の「御蔭」であると、「おかげさまで」ということばを
大切にしながら全国を巡ったので、この言葉が広まったのだと、
司馬遼太郎さんが『街道をゆく』という紀行文集の中で
おっしゃっています。
また大阪商人は「儲かりまっか」「まあ、ぼちぼちでんな」
という挨拶を交わすと言われますが、昔は「儲かりまっか」と
聞かれると「おかげさんで」と必ず言っていたそうです。
「おかげさんで」とは仏さまのご加護によってなんとか
生きていけることを〈お陰〉と感じて、その〈お陰〉を
感謝する思想なのでしょう。
大阪商人も 非常に宗教的な心をもった人たちであると
思われます、有名な御堂筋は、東西本願寺の別院、御堂が
ある通りのことです。
「おかげさま」という言葉を言い換える 日頃からお力添えをいただき、
誠にありがとうございますなど、 “お力添え”の“お力”は、
相手の力のことを指し、”助けていただいて有り難うございます。
との意味でしょうし、
物事がうまくいっていることを“おかげさま”と同様に、
“ありがたいことに”とも、使っています。
また、スピーチや挨拶状の中では、“ご協力のたまもの”
“ご支援のたまもの”という表現を使って大勢の相手に対して
感謝の意を伝えるために
京都の西本願寺には 阿弥陀堂と 御影堂とがありますが、
御影堂の御影は、「おかげ」とも読めます。
ですから、お陰さまという漢字より、
お影さまの方が浄土真宗では 良いのではないかと感じます。
また「させて頂きます」も、阿弥陀さまのはたらきの「お影さま」と
感じる浄土真宗の教えから生まれた言葉だともいわれます。
第1709回 おまかせ おまかせ
令和7年10月30日~
お寺の坊守さんで 47歳の若さで亡くなった
鈴木(すずき)章子(あやこ)さんという方がおられました。
ガンが見つかって、5年間の闘病生活の後、昭和63年に命終られました。
鈴木さんは、入院してガンの治療に取り組まれましたが、
限られたいのち前では、世間一般の価値観が通用しなくなることに
気づかれて、「お先真っ暗」となり、ここで、はじめて
「生死」の問題と向き合うことになり、悩んでいた時、
次のような手紙を受け取ります。
八十歳を過ぎた実家のお父さんからの手紙には、
「あなたは、一体何をドタバタしているのか。
生死はお任せ以外にはないのだ。人知の及ばぬことは
すべてお任せしなさい。
そのためにお寺に生まれさせてもらって、お寺に
嫁いだのではないか。
生死はあなたが考えることではない。
自分でどうにもならぬことをどうにかしようとすることは、
あなたの傲慢である。
ただ事実を大切にひきうけて任せなさい」とありました。
(『癌告知のあとで』二一頁)
お父さんの言葉に、誰にも代わってもらえない人生であることに
はっきりと、気づいたと言われています。
仏教は、人生の苦悩を克服するために、煩悩をなくしていくことを
本来は 教えるものです。
しかし、煩悩をなくすことなどとても不可能です。
そこで、心の持ち方を転換し、視点を変えることによって、
少しでも苦悩を克服できる方法があると気づかされ、そのことを、
四人の子供達へ伝えるために たくさんの詩を残しておられます。
その中に『変換』と題する詩には
死にむかって進んでいるのではない 今をもらって生きているのだ
今ゼロであって当然な私が 今生きている
ひき算から足し算の変換 誰が教えてくれたのでしょう
新しい生命
嬉しくて 踊っています “いのち 日々あらたなり”
うーん 分かります
人間の力の及こと、及ばないことがある。
自分で やれるだけやったら 後は お任せすればいいだけ、
間違いなく
後がないと、残された日を、1日1日 引き算していくのではなく、
毎日毎日を精一杯生き抜くだけ、いのち終わってもすべてが
終わりではなく、
未来があるのです。
大きな 確かな あしたがあるのです。
第1708回 愚者になりて 往生す
令和7年10月23日~
あるお寺の掲示版に
「よい人になろうと、お寺に通ったのに、どうしようもない
人間だと知らされた」とありました。
私たちは、子どもの頃から、よい人立派な人になろうと、勉強し、
社会に出ても一生懸命に頑張ってきました。
お寺に行くのも、よい人、立派な人になれるようにと、足を運びました。
ところが、浄土真宗のお話を聞いていると、これまで気づかなかった、
自分自身の本質に気づかされてくるのです。
あの人のここが問題、あの人は、間違っていると、
周りの人を批判するばかりで、自分自身の姿は見ることは
出来ていませんでした。
親鸞聖人は、関東の門弟たちに、たくさんの消息、お手紙を
京都から書き送っておらえれます。
その中に、最晩年の88歳の時、書かれた中に
故法然聖人は、「浄土宗のひとは愚者になりて往生す」と
候(そうら)いしことを、たしかにうけたまわり候いし
(今は亡き法然聖人が「浄土の教えに生きる人は愚者になって
往生するのです」と言われたことを確かにお聞きしました)と。
親鸞聖人は、29歳から35歳までの若い間に、東山の吉水で聞いた言葉を、
それから50年以上たって大切な教えとして、関東の門弟たちに
伝えようとしておられるのです。
ここで言う「愚かさ」とは、賢いとか愚かという相対的な意味ではなく、
人間、誰もが持つ根源的な愚かさのことを指しています。
たとえば、欲望にとらわれて自分を見失ったり、自分にとって
都合の悪いものを排除しようと、他者を傷つけ悲しませたり
するような愚かさです。
「愚者になる」とは、そのようにして生きている自分自身を、
他者を見るように、はっきりと見つめ、愚者の自覚を持つことこそが、
仏の教えに出会え、まことに生きることが出来るのだと述べて
おられるのです。
自分の愚かさを自覚するということはなかなかできることでは
ありません。
私たちは少しでも自分の姿をよく見せようとし、自己弁護して
正当化して、自分自身の本当の姿からつい目を背けてしまうからです。
自分の愚かさを認めるところから、他の人を理解し、人々との
深い関わりを持つことが出来、仏の願いが聞こえてくるようになるのです。
浄土真宗は 立派な人間になって救われるのではなく
愚者になって救われる教えであると知らされると、不安がなくなり
なんと有り難いことかと喜ばれるものです。
南無阿弥陀仏の呼び声に答えて、南無阿弥陀仏とお念仏が口にし
先輩達が勧めて頂いている 真実の教えを、素直に、心ゆくまで
味わわせていただきたいものです。
第1707回 裏のはたらき
令和7年 10月16日~
こんな話を聞きました。
明治時代のことでしょうか、京都の西本願寺にお参りした人が
はじめて、水道というものに出会いました。
ひねるだけで 水が出てくるのに驚いて、旅館の人に尋ねました。
これは、どこで買えるのですかと、これは職人さんが
取り付けてくれましたが、金物屋さんにあるのではないでしょうか。
金物屋さんに立ち寄り、水道の蛇口を幾つか求めて帰りました。
帰ると早速、壁に取り付けて、みんなを集めて、蛇口をひねりますが、
当然、水は出てきません。
水道の蛇口だけで、出るわけかがないのに、それを知らなかった
という話です。
これを聞いて、素直に笑ってはおれません、同じような生活を私たちは
毎日送っているのかもしれません。
まどみちを さんの詩に
「水道のせん」というのがあります。
水道のせんをひねると 水が出る 水道のせんさえあれば
いつ どんなところでも きれいな水が出るものだというように
とおい谷間の取入口も 山のむこうの浄水池も 山の上の配水池も
ここまでうねうねと土の中を はいめぐってきているパイプも
それらのすべてを つくった人も いっさい関係ないかのように
牛乳びんさえあれば 牛乳がやってくるかのように
電灯のたまさえあれば 電灯がともるかのように
水道せんひねると 水が出る
とあります。
私たちは 表面的な目に見えることしか感じていません。
そこにつながる大きな働や力、さまざまなご苦労があったことに
気づくことなく、あれもこれも、みんな当たり前になって、感謝も
喜びもない、無感動な生活をしています。
気づくのか、気づかないか、見えるか見えないかで、人生の味わいは
大きく違ってくるものです。
そして、こうしてお念仏を口にすることが出来ているのも、沢山の
はたらきが、ご縁があってのことです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏に出あい、お聴聞することで
表だけではなく、その裏に隠れている多くのはたらきに、
思いに気づかせていただき、はじめて
感動的な有り難い豊かな人生を受け取ることが出来るのです。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のはたらきによって、
私に届いている大きなはたらきかけを感じ、気づかせて
いただくことが
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
第1706回 無税の相続
令和7年 10月9日~
おかげさまで 10年半に一度の 佐賀組の巡番報恩講は
10月1日から 五日間 多くの方にお参りいただき有り難い法要となりました。
日頃は 一日だけ法要にお参りして、それで終わりの方が多いのですが、
今回は 連続してお参りいただく方が多かったように感じました。
ご講師の渡辺崇之先生の軽快なお話に、笑いと笑顔が絶えることのない
明るく賑やかな法要となり、有り難いことでした。
ところで、毎日の法座の最後に、総代と住職が挨拶していますが、
今回は、こんな話をしました。
それぞれのお宅に上がり込んで、月忌参りや法要に伺って30年あまり、
お念仏にご縁があるお宅と、まったくご縁の無いお宅とでは、まるで
違うことをつくづく感じます。
相続という言葉がありますが、相続というと今、税金のかかる
ことばかりをイメージされる方が多いと思いますが、もともとは、
念仏相続という言葉から出てきものではないかと思います。
昔は、長男が家を継ぎ、財産も家も家業も 全部一人で受け継いでいました。
他の兄弟には、その権利はありませんでした。
現代では 兄弟がみな平等に遺産を相続できるようになってきました。
財産は、分配すれば、段々と少なくなっていくものですが、
お念仏の教えは、全員に平等に伝えても 減ることはなく、子どもや孫へ
いつまでも、そのまま受け継ぐことができるものです。
物は、使えばすぐなくなってしまうものですが、お念仏の価値観は
どんなに分けても、減ることはなく、代々伝えていくことができるものです。
税金のかかる相続ばかりではなく、先だった親たちが最も喜ぶ、お念仏を通して
感じる力、思いやりのこころ、感謝の気持ち、喜びを受け取っていき
それを確実に次の世代へ伝えていただきたいものです。
どんな宝ものにもまして、このお念仏の価値観は 有り難い財産です。
歳を取っても、病気をしても、どんな災害に見舞われても、これほど
価値があり確かなものはありません。
それを、次の世代に受け継ぐには、まず、大人の私たちがお聴聞をして、
喜ぶ姿を見せること、あんな生き方が理想だと思えるように、
力強く、明るく活き活きとした姿を見せてあげることでしょう。
それには、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏を、確かに受け取り
味わう力を身に着けることがまずは第一です。
この秋には、秋の法座も予定しています。
一月は ご正忌報恩講 そして、3月には 次の真覚寺さんでの
巡番報恩講 まずは、大人がお聴聞をして、その喜びを、感じ取って
いくことが、お念仏相続の もっとも早道だろうと、思います。
第1705回 みんな 一人残らず
令和7年 10月2日~
テレビを見ていると、観光地や事件事故でも、スマホを
手に撮影する人々の姿をよく見かけます。
今は、写真や動画を、誰でも簡単に撮ることが出来るようになりましたが、
カメラ好きで、展示会をよく開いている方からこんな話を
聞いてことがあります。
子どもの運動会で写真を撮りたいので、カメラを貸してくれと ずっと昔に
友だちから頼まれたことがありました。
そこで、誰でも簡単にとれる簡易なカメラを準備すると、友人は
初めての子どものためだから、もっと良いものを貸してくれとの注文です。
自分が日頃使っているカメラは 扱いが難しいから無理だと
いっても聞いてくれません。
無理矢理、大きな望遠レンズの着いた高価なカメラを持って友人は
運動会へ行き、大量の写真を撮って意気揚々と帰ってきました。
ところが、どれもピントや絞りがうまくいかず、まともに写った
ものは一つもなかったということです。
どんなに高級なカメラでも それを使う知識や技能がないと
何の役にも立ちません。
見かけはヤスっぽい全自動のカメラですが、
知識のない人にとっては、それが一番ありがたい立派なカメラです。
これと似て、どんなに立派な教えがあっても、
その教えの通りに修行したり、戒律を守ったり出来ない人にとっては
何の意味もありません。
すべての人を必ず救うというお念仏の教えだから、技能や知識を
持たず、努力することも出来ない人でも、間違いなく
救われることが出来るのです。
これこそが、最も立派で有り難い教えと言えるでしょう。
ある運動会でのこと、やっと歩けるようになった子どもたちの
かけっこで、わずか10メートルほどの決勝点に向かって、
すぐに走り出す子どももいれば、ゴールではなく親の方に、
来てしまう子ども、大きな声の応援に驚いて、
スタートラインの上で 泣き動けなく成った子どももいます。
いつまでたっても、泣くだけで、動けない子どもに、先生が
抱き上げで、ゴールまで走ってくれた姿を見て、あああれが
阿弥陀さまの一人も漏らさず必ず救うということだなあと、
有り難く見せてもらったという 話も聞きました。
阿弥陀さまは、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏となって、
一人も漏らさず救うと、今、はたらいていただいているのです。
いろいろ有り難い立派な教えがあっても、この私には
お念仏で救われる教え これしかないのです。
第1704回 世界中が雨の日も
令和7年 9月25日~
こんな話を聞きました。
10年ほど前の 朝の連続テレビ小説 「とと姉ちゃん」が
現在 お昼休みの時間に 再放送されています。
その主題歌は、宇多田ひかりさんの 「君に花束を」という曲です。
すばらしい歌だと聞いていますが、ある音楽番組に
この宇多田ひかりさんが出演、 司会者が質問して
「ご自分の歌で好きな歌は何ですか」との問いに、
この「君に花束を」が
「その中でも 好きな部分はどこですか」との質問に
世界中が雨の日も
ですと答えていました。
世界中が雨の日も 太陽とは
どこかで聞いた言葉のように思えますが、日頃お勤めしている
正信偈の 譬如日光覆雲霧 雲霧之下明無闇 を思い出しました。
私たちは貪りや憎しみ、愚痴などの煩悩に覆われて、
阿弥陀様のはたらきに、なかなか気づくことができませんが、
たとえ雲や霧が覆っていても、雲や霧の下にも明るさが
届いているように、阿弥陀さまのはたらきは、届いているのです。
空が、どれほどあつい雲におおわれていても、雲の下に闇はないように、
どれほどの愚かさを抱えた凡夫であっても、阿弥陀さまのはたらきは、
その愚かさが障りとならないと親鸞さまは仰っています。
自分の力で 煩悩を無くすことが出来なくても、
決して煩悩が妨げにはならないということ。
しかし親鸞さまは、
雲の上を見ようとするのではなく、雲の下に闇のないことを
驚かれました。
光はとどいている。どれほど私の愚かさの雲霧があつくとも、
阿弥陀さまのみ心は届いてくださっていた。そのことに驚かれたのです。
宇多田ひかりの 「君に花束を」
世界中が雨の日も
「その歌詞の君の笑顔の 君とは 誰ですか」との問いに
今はなき 母親 藤圭子だと、答えていました。
母親の愛 そして阿弥陀さまのはたらき どんな雨の日も
霧の日も、そのままの私を いつも見守ってくれる
そのはたらきに、気づくことができる時、ありがたさが
沸いてくるものです。
どんな時も、見守り続けてくださる はたらきがあるのです。
第1703回 あなたは どちら
令和7年9月18日~
秋の彼岸法座のご案内に、こんなことを書きました。
ある念仏者の言葉に、「人生いろいろというが、
私は二つしかないと思う、阿弥陀さまのお慈悲を聞くか、
聞かないか」の違い。
聞くことが出来れば、有り難く恵まれた人生だったと喜べるし、
聞かねば、苦しく辛い無価値な人生だったと感じられてしまうもの。
あなたは どちら・・・。
との葉書を出しました。
阿弥陀さまのお慈悲 はたらきを、お聴聞するか しないか
そのチャンスが あるか ないかで、
人生は まるで違って見え、感じられるのです。
周りから見れば、同じような人生を送っていても、有り難かったと
喜びながら 充実した生き方ができる人と、こんなに努力したのに
苦労したのに 誰も分かってくれない。
いいことは 一つもなかった、悔しい 腹が立つ と
憤りながらの苦しい人生を送る人との、違いが出てくるのです。
仏さまの話を聞くことができた人は、自分の努力 頑張りばかり
ではなく、周りの人々の努力 頑張り 思いやりなどが少しづつ
見え感じられるようになるのです。
見る目が 感じる力が育ってくると、私の努力よりも
私に対する もっともっと大きな、多くの はたらきかけがあることに
気づくことが出来るのです。
そうすると、もったいない こんなことでは 申し訳ないと
感謝とともに もっと頑張ることができるようになるものです。
お聴聞のご縁がなく、周りが見えない人は 自分のことしか
見ることができず、ひとり孤独で、悪戦苦闘する感覚ばかりで
感謝も 喜びも 生き甲斐もなく
苦しい つらい人生であると感じられてしまうのです。
そうした 感じる力 知る力を身につけるには、
仏さまの話を 仏さまのはたらきを、お慈悲を聞いていくことで、
いかに有り難い人生であるか、何と 多くの人々が 私のために
はたらきかけていただいているかに、気づき はっきり感じ
喜び、感謝の気持ちが起こってくるのです。
そのお聴聞のご縁、この 10月 1日からの巡番報恩講の五日間
またとない 尊いチャンスです。最後のご縁です。
仕事を休んでも 大事な用事を後回しにしても
このご縁にあうことは、もっとも価値があることと思います。
聞いてくれ 聞いてくださいと
先だった父母 祖父母 多くの先輩達が そろって南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏 呼びかけていただいているのです。
今しかない あしたでは遅い 今 聞いてくれと
願われているのです。
そして、 豊かな有り難い人生を 受け取って、
喜び多い感謝の毎日を送ってほしいと。
第1702回 誰も皆 86,400
令和7年9月11日~
一周忌で、「よくお聴聞されておられたご主人は、仏さまとなって、
今も 私たちのためにはたらいておられることでしょう。」
と、お話をし、最後の合掌をした後、床の間に置かれた遺影の前に、
ご本人のものと思われる腕時計が、置いてあるのに気づきました。
のぞき込んで、「あら、ちゃんと動いていますよ。」というと、
年配の妹さんが、「あらあーと」と、驚きの大きな声を出されました。
「この腕時計だけではなく、今、ご本人もちゃんと働きかけておられるのに、
こっちが気づかないだけなのでしょうね」
「そうやろね、そうやね・・・」 との高齢の妹さんの感動の声を
聞きながら帰ってきました。
時計、時間といえば、こんな話を聞きました。
すべての人に、86、400円、毎日毎日お渡ししますと言われると
とても、嬉しく有り難いものです。
だだ、次の日に持ち越すことはできず、その日のうちに
使い切ってしまわなければならないというのです。
自分の好きなものを、自由に買えて、うれしいものですが、残すことが
出来ない、使い切ってしまい貯金が出来ないのは、残念なことです。
同じように、私たちすべての者に、毎日毎日、86、400秒、
分にならすと1440分、24時間が
与えられているのです。
誰もがみんなが頂いている、86、400秒の時間ですが、
当たり前になって、感動もなく、余り喜んでもいません。
そればかりか、意識もせずにぼんやりと、無駄に使い切っています。
時には 誰かの行動や、言葉に腹を立てて、くやしい、
許せにないと、イライラ くよくよと、そのことばかりに心奪われて、
長い時間、悶々と無駄な時間を過ごすることもあります。
折角いただいている毎日毎日の86、400秒、無駄遣いをすることなく、
出来れば、喜び多い時間を多く持ちたいものです。
お金と同じく 自分の為だけに使うのではなく、
誰かの役立つこと、喜びを分けてあげることにも、挑戦するなど
意味ある使いかたを 考えて見ることも大事なことでしょう。
もし、南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏のお念仏を口にするご縁があれば、
平凡で 当たり前の毎日が、意味深く、有り難く、喜び多い、
素晴らしい価値ある時間であることが確認出来ることでしょう。
つらいこと、苦しいことで悩み続け、時間を無駄に使い切るより、
仏さまも 亡き父母も喜んでくださる、南無阿弥陀仏、
南無阿弥陀仏を口に、味わい深い、喜び多い、豊かな時間を
味わいたいものです。
第1701回 見る 感じる力
令和7年 9月4日~
ご本山の朝のお勤めのご法話で
私たちは見えるものだけを大事にしていますが、見えないものも
有り難く大事なものがあることに、気づいていないのではないかという
お話です。
見えないものもあるというと、金子みすゞさんの「星とたんぽぽ」の詩を
思い出します。
青いお空のそこふかく、 海の小石のそのように
夜がくるまでしずんでる、昼のお星はめにみえぬ。
見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。
ちってすがれたたんぽぽの、かわらのすきに、だァまって、
春のくるまでかくれてる、つよいその根はめにみえぬ。
見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。
本当に大事なもの 有り難いものは 見えないものが多いようです。
親の愛や思いやり、優しさなどを、見ること、感じることができるか
出来ないかで、 その人の人生は大きく違ってくるものでしょう。
見る力がないのか 見ようとしないのか。
それが、見えるように 感じられるようになってくるのは、
学校教育などの知識の教育だけでは不十分で、
仏さまのお話、ご法話を聞かせていただくことで
今まで気づかなかった大事で、有り難いものに気づき、
見過ごしていることに気づき、感じられるようになってくるのでしょう。
仏さまのお話を聞かせていただく中で、少しづつ
変化が訪れてくると、人生はまるで違って見えてくることに気づきます。
見る力 感じる力、味わう力、それを育てていただくことが出来きるのが、
仏法に出遇うということだと、思います。
まわりが少し見えるようになってくると
いかに多くの力に守られ育てられているか、なんと有り難く
素晴らしことかに気づかせていただけるのです。
どうか、次の世代へも この見る力、感じる力を 伝え残して
行きたいものです。
それには、南無阿弥陀仏のみ教えを受け継ぐことが、もっとも確実で
近道だと味わいます。
第1700回 感謝・喜びの効果
令和7年 8月28日~
こんな話を 聞きました。
龍谷大学の臨床心理学の先生から「感謝の効用」のお話を聞きました。
その先生は、自分の講義を受けている学生さんたちに、3カ月間、
小さな習慣を続ける実験に参加してもらったそうです。
それは、寝る前に「今日も おかげさまで 一日を 終えることができました。
ありがとうございました 」と、感謝の言葉を 3回繰り返すことです。
そして、実験に参加し学生さんには「 もし 何か 生活に 変化があれば、
メモして おいてください 」と、頼まれたそうです。
毎晩 3回 感謝の言葉を唱えることに、どんな意味があるのだろうかと
半信半疑だったようですが、3カ月たった頃、学生さんたちからは、
「 笑顔が増えてきた 」「 憂鬱な 気分が減った 」「 家族関係や
人間関係がよくなった 」「 身体的な 疲れが減った 」「 バイト先で
気遣いができるようになった 」などの 報告が あがってきたそうです。
どんな人にも、辛く苦しいことばかりではなく、うれしいこと、
感謝すべきことが必ずあるものです。
毎日 毎日 感謝の言葉を口にする、この習慣がきっかけとなって、
うれしいこと、感謝できることに 目が向くようになってくると、
神経伝達物質やホルモンのバランスよくなることが、いろいろの実験や、
研究でだんだんとわかってきたといいます。
「 幸せだから感謝するのではない。感謝できることが幸せである 」
という言葉があります。
幸せは、地位や名誉や財産などだけで決まるのではなく、ものの見方、
感じ方によって大きく変わってくるものです。
これまでの長い人生の中では、苦しいこと悲しいこと、つらいこと、
いろいろと困難なことに、どなたでも出会われたことでしょう。
しかし過去ではなく、今の自分を喜ぶことが出来る人こそ
幸せといえるでしょう。
思えば親鸞聖人のご生涯は、大変ご苦労の多いものでした。
大飢饉を何度も経験され、罪人とされ流罪にもなり、晩年には息子さんを
義絶するという悲しい出来事もありました。
社会一般のものさしでは、とても幸せとは言えない人生だったでしょうが、
もし聖人にお尋ねすることが出来れば、きっと「いろんなことがあったが、
多くの尊いご縁に よって 阿弥陀さまの ご本願に遇わせていただけた。
私ほど幸せな人生はなっかた 」とおっしゃるのではないでしょうか。
お念仏を称えることは、お念仏を聞くこと。お念仏を聞くとは、
阿弥陀さまの願いに遇わせていただき、阿弥陀さまのお慈悲の中に 今
私が生かされていると 知らされることです。
〝 感謝の言葉 〟でもある〝 お念仏・南無阿弥陀仏 〟を、称えて生きる
人生とは、まさに導かれ 護られている 有り難く、喜びいっぱいの
幸せな人生であることに、はっきりと気づかされ、味わう生活です。
親鸞聖人は 念仏者に恵まれる精神的喜びのことを「心多歓喜の益
( 心に よろこびが多いという利益 )」「 知恩報徳の益( 如来の恩を知り
その徳に報謝するという利益 )」そして最後に(やがて仏になると定まった
正定聚の位に入る )「 入正定聚の益・にゅうしょうじょうじゅのやく」との
十種の利益があると、『教行信証』に、お念仏を 口にする人が感じる喜びを
はっきりと示していただいています。
(本願寺新報二〇二四年七月二十日号掲載) 高田 文英師
龍谷大学教授 福井県鯖江市・西照寺衆徒を参照しました。
第1699回 スパイスをきかす人生
令和7年 8月21日~
電話法話の原稿を 大きな活字で印刷しようとしていますが、
その2冊目の校正をしていて、20年以上前のこんな 文章に出会いました。
お参りした時に、こんな質問を受けました。
「宗教は、どうして必要なんでしょうかね」と。
お料理が、得意そうな方でしたので、こんな答えをしました。
私たちは、毎日毎日食事をしています。
ところが、それを、いつも喜んで食べている方と、何の感動も持てず
淡々と食べている人、中には、文句をばかり言う人、
昔食べてあれは美味しかったと、目の前のものを
味わえない人など 様々な人がいます。
同じことなら、喜んで美味しく食べたいものですが、
中には、お世辞にも美味しいと言えない料理もあるものです。
どんなに高価な材料を使った料理でも、どうももう一つ
美味しさに欠けることもあります。
人生もおなじことではないかと思います。
周りからみれば、何不自由のない恵まれた生活、経済的にも
社会的にも、何の問題もない生活なのに、何か一つ足りない。
ちょうど高い材料を使って料理していながら、もう一つ味わいの少ない
お料理と共通するところがあるようです。
お料理なら、ほんの少しのスパイスをきかすだけで、もっともっと
美味しく魅力的になることもあります。
おそばには ワサビ、うどんには七味、そうめんにはショウガと、
おなじ麺類でも、違いがあります。
それぞれの料理を引き立たせて、尚一層美味しくするものがあるものです。
それを、ちゃんと知っている人と知らない人。
折角、誰かが薦めてくれるのに、大丈夫大丈夫と、いつもお醤油だけを
かけて食べているような生活を送っている人もいます。
人生でも、ほんのひと工夫、見方を変えることで 大きく
味わいが変わってくるのに、それを知らずに一生を終わって
いく人も多いようです。
宗教とは、多くの経験し、さまざまな失敗や過ちを
繰り返した先輩たちが、同じ誤りをしないように、もっと喜びを感じ
味わいを深める生き方があることを、伝え教えようとしたものでは
ないかと思います。
南無阿弥陀仏のお念仏を口にすることで、ものの見方が変えられて
同じ人生でも、ひと味違う、味わう力、味覚が育てられることを
先輩、ご祖先たちは伝えようとしているのではないかと感じます
同じ人生ならば、先輩のすすめを受け取って、味わい深い人生を、
喜び多い 感動的な人生を、送りたいものです。
第1698回 有り難い方の お通夜で
令和7年 8月14日~
先頃 いつもお参りいただいた有り難い方が 亡くなられまいした。
そのお通夜の席で こんなお話をしました。
〇〇さん 92歳の堂々とした ご一生でした。
子どものころ、鳥栖で空襲を受け苦労した話を、先日新聞に語って
おられましたが、成長後、〇〇会社に勤務 定年後は、地元で
自治会活動で活躍され、その誠実なお姿は、ここに参加されている
皆さんお一人お一人が、それぞれの場で充分にお感じになって
いることでしょう。
私が存じ上げる 〇〇さんは、お父様のご命日にご自宅に伺い
一緒にお勤めしていただく 真面目でありがたいお方でした。
お手元にお経さんの本が渡っていると思いますが、その本を
いつも持って、六ぺージからのお正信偈のおつとめしておられました。
ご自宅でばかりではなく、お寺でお彼岸や報恩講など 行事の折りには
必ずお参りになり、いつも大きな声で ご一緒に、
もう何百回と、お勤めをしておりました。
出来ますれば これから、みなさんも、〇〇さんとご一緒の
つもりで、お勤めをしていただければ有り難いことです。
お勤めの内容は、 お釈迦様が説かれた仏教ですが、それぞれの能力に
見合って、具体的にさまざまに数多く説かれています。
その中で、親鸞聖人という方が、これこそが、私のために説かれた教え
この教えでこそ、人間らしく堂々と生きていくことの出来る有り難い
教えであると、ご自分で味わい、私たちに勧めていただく内容で、
この教えこそが、お釈迦さまがもっとも説きたかった内容であると
まとめていただいているものです。
これから、みんな必ず老病死を迎えますが、その苦しみ
悩みを、乗り越えていくことの出来る 人間らしく生きぬく事のできる
南無阿弥陀仏の教えが説かれています。
このお勤めの後をした後で、毎回、必ずお話していたことが
ありますが、それは お勤めのあと、また お話しいたします。
まずは、〇〇さんとご一緒のつもりで、お勤めいたしましょう。
◎ 正信偈のおつとめ
ご一緒に おつとめいただきまして、ありがとうございます。
こうして、いつもお勤めした後、必ずお話していたことは
毎回 同じこと、ただ一つです。
お手元の経本の表紙に 浄土真宗とあります。
私たちの 科学的な頭では いのちが終われば、すべて無くなると
思っていますが、お釈迦様は この世だけではなく、自分の行いによって、
次の世界へ生まれていくのだと、教えていただいいます。
ほとんどの人は、自分で作った罪で、地獄へ生まれることになるのですが、
南無阿弥陀仏の人は お浄土へ生まれて 仏さまになって 活躍すると
教えていただいています。
ですから、もう〇〇さんは、仏さまとして 今すでにここで
はたらいていただいているのです。
残された私たちが出来ることは 仏さまになられた方が、喜んで
いただけるような生き方をすることでしょう。
それには、お念仏の教えに出あい、喜び多い生活をさせて
いただくことでしょう。 ・・・・・
このような お話をしました。
第1697回 見ていない 見えていない世界
令和7年 8月 7日~
悲しい事件が 起こりました。
外国から技能実習生として日本に来ている 青年が 住まいの近くの人を
傷つけ、殺害するという、どうしようもない悔しい事件です。
今、近くのコンビニの店員さんも、その多くは外国の若い人で
親切、丁寧で 日本人の若者には、とても出来ないほど、
立派な対応をしてくれます。
日本は 現在大変な、労働力不足だそうで、農業 工業 水産業
製造業あらゆる部門で、日本人が働きたくない、
大変な仕事を、彼らが受け持ってくれています。
技能実習法という法律では、「技能実習は、労働力の需給の調整の
手段として行われてはならない」とあるものの、現実は そうは
いかないように見受けます。
残念なことは、生活習慣の違いから、住居地で深夜まで騒いだり、
生活ゴミの出し方で、近所とのトラブルがあったりもするようですが、
受け入れる企業によって、生活の環境は大きく違っているようです。
どうも、私たちは、自分とは関係無い、余所のことだと
無関心で見て見ぬふりをしています。
お念仏の生活とは、自分の立場からだけで世間をみるのではなく
仏さまの目に 気づかせていただくことだとうと味わいます。
日頃、利害関係、知り合いかどうかなどを基準に、
世間を見ているようで、本当に狭い目でしか、世の中を見ていません。
自分に代わって、大変な仕事を、日本人が嫌がって逃れている
ことを、暑い中汗をかき、早朝や深夜、危険な仕事を
外国の若者が、最低賃金で頑張ってくれていることに、気づき、
こころに留め、見守ることが、出来るようになりたいものだと、思います。
私はちゃんと世の中を見て、何でも分かったつもりになって
いますが、仏さまから見れば、自己中心で 傲慢などうしようもない
人間に見えていることでしょう。
悲しい事件でしたが、そのことを私に気づかせてくださるため、
ご苦労だったのだと、受け止めさせていただいています。
観無量寿経が説かれるご縁となった 提婆達多が阿闍世をそそのかして
頻婆娑羅王を害させるという王舎城の悲劇、そのご縁で釈尊が
韋提希をお導きになって、阿弥陀仏の浄土を教えてくださったように
私のためのご苦労くださった方々であったと 味わえてなりません。
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏
 妙念寺
妙念寺
電話法話一覧表へ (平成9年)~
掲載者 妙念寺住職 藤本 誠
電話法話一覧表
| 第1551回 かけがえのない君へ | 10月20日~ |
| 第1552回 朝のどまんなかに | 10月27日~ |
| 第1553回 片道か 往復か | 11月 3日~ |
| 第1554回 誓いと 願い | 11月10日~ |
| 第1555回 言葉で 救う | 11月17日~ |
| 第1556回 人間にわかる言葉で | 11月24日~ |
| 第1557回 お念仏は 公の言葉 | 12月 1日~ |
| 第1558回 伝え 伝えて | 12月 8日~ |
| 第1559回 お仏壇の前で | 12月15日~ |
| 第1560回 何事も お念仏の助縁 | 12月22日~ |
| 第1561回 遇い難くして 今遇う | 12月29日~ |
| 第1648回 まだ仕事が残っています | 8月29日~ |
| 第1649回 あんたが悪い | 9月 5日~ |
| 第1650回 自分の姿を鏡で見る | 9月12日~ |
| 第1651回 はじめての道 はじめての人生 | 9月19日~ |
| 第1652回 法座 & フォークソング | 9月26日~ |
| 第1653回 墓友 ~この世からの仲間~ | 10月 3日~ |
| 第1654回 ハチドリのひとしずく | 10月10日~ |
| 第1655回 後になって 気づく | 10月17日~ |
| 第1656回 救われる私 | 10月24日~ |
| 第1657回 私が仏になる | 10月31日~ |
| 第1658回 私は 私でよかった | 11月 7日~ |
| 第1659回 願いを知る | 11月14日~ |
| 第1660回 親の足を洗う | 11月21日~ |
| 第1661回 周りに迷惑をかけて | 11月28日~ |
| 第1662回 ハッピーバースデーだね | 12月 5日~ |
| 第1663回 絵本の読み聞かせ | 12月12日~ |
| 第1664回 良いことをするときには | 12月19日~ |
| 第1665回 浄土真宗は 有り難いですね | 12月26日~ |
| 令和 7年 |
| 第1666回 私の宝ものです | 1月 2日~ |
| 第1667回 これもご報謝 | 1月 9日~ |
| 第1668回 世間か 娑婆か | 1月16日~ |
| 第1669回 マルテンを見ると | 1月23日~ |
| 第1670回 大丈夫 大丈夫 順調 順調 | 1月30日~ |
| 第1671回 良かったね 母さん | 2月 6日~ |
| 第1672回 今 ここに 生きる | 2月13日~ |
| 第1673回 鏡で見ると | 2月20日~ |
| 第1674回 アリガトウ | 2月27日~ |
| 第1675回 対治 と 同治 | 3月 6日~ |
| 第1676回 籠を水に | 3月13日~ |
| 第1677回 いつもいっしょ | 3月20日~ |
| 第1678回 私と 仏さま | 3月27日~ |
| 第1679回 自分自身を 採点すると | 4月 3日~ |
| 第1680回 相続していますか | 4月10日~ |
| 第1681回 知恩報徳 | 4月17日~ |
| 第1682回 実を結ぶために | 4月26日~ |
| 第1683回 よいいっしょ 良い一生 | 5月 1日~ |
| 第1684回 何が起ころうと 大丈夫 | 5月8日~ |
| 第1685回 グッドタイミング | 5月15日~ |
| 第1686回 期待され 待たれている私 | 5月22日~ |
| 第1687回 因果応報 自業自得 | 5月29日~ |
| 第1688回 言えば 良かった | 6月 5日~ |
| 第1689回 呼びかけ続ける | 6月12日~ |
| 第1690回 安心して堂々と生きる | 6月19日~ |
| 第1691回 尊いご縁で | 6月26日~ |
| 第1692回 ヨシ 間違いなし | 7月3日~ |
| 第1693回 水道の蛇口 電灯のたま | 7月10日~ |
| 第1694回 未来を開く ことば | 7月17日~ |
| 第1695回 感じる力 知る力 | 7月24日~ |
| 第1696回 無駄な いのちは 一つもない | 7月31日~ |
| 第1697回 見ていない 見えていない世界 | 8月7日~ |
| 第1698回 有り難い方の お通夜で | 8月14日~ |
| 第1699回 スパイスをきかす人生 | 8月21日~ |
| 第1700回 感謝・喜びの効果 | 8月28日~ |
| 第1701回 見る 感じる力 | 9月4日~ |
| 第1702回 誰で皆 86,400 | 9月11日~ |
| 第1703回 あなたは どち ら | 9月18日~ |
| 第1704回 世界中が雨の日も | 9月25日~ |
| 第1705回 みんな一人残らず | 10月 2日~ |
| 第1706回 無税の相続 | 10月 9日~ |
| 第1707回 裏のはたらき | 10月16日~ |
| 第1708回 愚者になりて 往生す | 10月23日~ |
| 第1709回 おまかせ おまかせ | 10月30日~ |
| 第1710回 | |
| 第1711回 |
 妙念寺
妙念寺
短くやさしい法話(動画)
記載者 住職 藤本 誠
| 私も一言(伝言板) | このホームページトップへ |